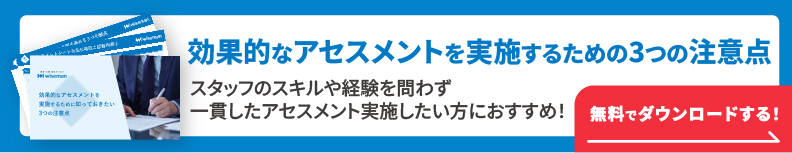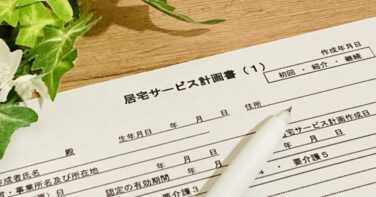介護におけるアセスメントシート23項目とは?適切な書き方を解説
2024.12.19

通所介護計画書を作成するうえで、アセスメントは重要なプロセスです。
アセスメントが正しくできなければ、利用者のニーズを満たすケアプランが作成できません。
アセスメントを実施する際、情報を整理するうえでも適切なアセスメントシートを作成する必要があります。
しかし、アセスメントシートは23項目あり、それぞれの内容について正確に把握しなければなりません。
本記事では、介護におけるアセスメントシートや記載する23項目について解説します。
23項目の書き方はもちろん、記載例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
アセスメントシートを記載する上で知っておきたい3つの観点を記載しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
介護におけるアセスメントとは

本章では、介護におけるアセスメントについて、以下の内容を解説します。
- アセスメントの目的
- アセスメントシートとケアプランの関係
- 課題分析項目の改正
あらためて、アセスメントの意義について確認しましょう。
アセスメントの目的
ケアプラン作成においては、アセスメントは通所介護契約書を作成するうえで介護サービス利用者から必要な情報を聞き出すプロセスを指します。
アセスメントは利用者のケアプランを最適化するための業務です。
そのため、利用者が介護サービスを利用する前段階だけでなく、ケアプランを再作成する際にも実施されます。
なお、アセスメントを実施した際、利用者の情報を記載する書類はアセスメントシートと呼ばれます。
アセスメントシートの書式には決まりがありません。
Web上にあるフォーマットを利用するのはもちろん、ケアマネージャーが独自に作成しても問題ありません。
アセスメントシートとケアプランの関係
アセスメントで作成するアセスメントシートと、ケアプランは密接に関係しています。
アセスメントでいかに情報を聞き出すかによってケアプランの質は変わります。
アセスメントシートを作成する際は、利用者に寄り添いながら情報を聞き出しましょう。
また、アセスメントシートは利用者にケアを実施する他職種にも共有されます。
アセスメントシートに記載した内容を、さまざまな職種の観点から多角的に分析することで、より質の高いケアプランが実現できます。
課題分析項目の改正
アセスメントシートにはさまざまな課題分析項目が記載されますが、項目は介護の現状に合わせて改定される場合があります。
現在の課題分析項目は2023年に改定されたものであり、当時はアセスメントする内容が大幅に追加されたことで話題になりました。
厚生労働省はすべての項目の情報収集を求めるものではないと通知していますが、アセスメントの際に確認すべき項目は実質的に増加しています。
課題分析項目が改正される頻度は少ないですが、厚生労働省から発表があった際は、必ずチェックしましょう。
アセスメントシート23項目の記載方法

本章では、アセスメントシート23項目の記載方法について解説します。
ここでは23項目を基本情報に関する9項目と、課題分析に関する14項目に分けたうえで、それぞれの一覧や記載例を説明します。
基本情報に関する9項目の一覧
基本情報に関する9項目は以下のとおりです。
| 標準項目名 | 項目の主な内容(例) |
| 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報、居宅サービス計画作成の状況(初回、初回以外)について記載する項目 |
| これまでの生活と現在の状況 | 利用者の現在の生活状況、これまでの生活歴等について記載する項目 |
| 利用者の社会保障制度の利用情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険等)、年金の受給状況(年金種別等)、生活保護受給の有無、障害者手帳の有無、その他の社会保障制度等の利用状況について記載する項目 |
| 現在利用している支援や社会資源の状況 | 利用者が現在利用している社会資源(介護保険サービス、医療保険サービス、障害福祉サービス、自治体が提供する公的サービス、フォーマルサービス以外の生活支援サービスを含む)の状況について記載する項目 |
| 日常生活自立度(障害) | 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 |
| 日常生活自立度(認知症) | 「認知症高齢者の日常生活自立度」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 |
| 主訴・意向 | 利用者の主訴や意向について記載する項目家族等の主訴や意向について記載する項目 |
| 認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、区分支給限度額等)について記載する項目 |
| 今回のアセスメントの理由 | 今回のアセスメントの実施に至った理由(初回、要介護認定の更新、区分変更、サービスの変更、退院・退所、入所、転居、そのほか生活状況の変化、居宅介護支援事業所の変更等)について記載する項目 |
2023年度の改正で、基本情報に関する項目は利用者のより細かい点までアセスメントを行う方針になりました。
基本情報に関する項目の記載例
基本情報に関する項目の記載例は以下のとおりです。
| 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 利用者から聞き出した情報を記入 |
| これまでの生活と現在の状況 | 40代息子家族と同居夫は5年前に他界次男・長女がいるが、いずれも遠方で生活しているため、協力を得ることは難しい |
| 利用者の社会保障制度の利用情報 | 利用者から聞き出した情報を記入 |
| 現在利用している支援や社会資源の状況 | 週1回のデイサービスを利用 |
| 日常生活自立度(障害) | 歩行は安定しており、買い物・散歩なども自身で行えるが、腰痛がひどいときはトイレや入浴が困難になる |
| 日常生活自立度(認知症) | ほぼ自立している |
| 主訴・意向 | ほぼ自立しているうえに、家族のサポートもあるが、家族の不在時が心配腰痛の悪化を防ぎ、身体機能を維持したい |
| 認定情報 | 利用者から聞き出した情報を記入 |
| 今回のアセスメントの理由 | 本人が身体機能の維持や、家族が不在の際に支援を受けられる介護サービスを受けることを希望したため |
課題分析に関する14項目の一覧
課題分析の14項目は以下のとおりです。
| 標準項目名 | 項目の主な内容(例) |
| 健康状態 | 利用者の健康状態及び心身の状況(身長、体重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、褥そうの有無等)、受診に関する状況(かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、その他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等)、服薬に関する状況(かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況等)、自身の健康に対する理解や意識の状況について記載する項目 |
| ADL | ADL(寝返り、起きあがり、座位保持、立位保持、立ち上がり、移乗、移動方法(杖や車椅子の利用有無等を含む)、歩行、階段昇降、食事、整容、更衣、入浴、トイレ動作等)に関する項目 |
| IADL | IADL(調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の運転等)に関する項目 |
| 認知機能や判断能力 | 日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている場合の中核症状及び行動・心理症状の状況(症状が見られる頻度や状況、背景になりうる要因等)に関する項目 |
| コミュニケーションにおける理解と表出の状況 | コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況(視覚、聴覚等の能力、言語・非言語における意思疎通)、コミュニケーション機器・方法等(対面以外のコミュニケーションツール(電話、PC、スマートフォン)も含む)に関する項目 |
| 生活リズム | 1日及び1週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度(活動の内容・時間、活動量等)、休息・睡眠の状況(リズム、睡眠の状況(中途覚醒、昼夜逆転等)等)に関する項目 |
| 排泄の状況 | 排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状況等、後始末の状況等、排泄リズム(日中・夜間の頻度、タイミング等)、排泄内容(便秘や下痢の有無等)に関する項目 |
| 清潔の保持に関する状況 | 入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況(皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等)、寝具や衣類の状況(汚れの有無、交換頻度等)に関する項目 |
| 口腔内の状況 | 歯の状態(歯の本数、欠損している歯の有無等)、義歯の状況(義歯の有無、汚れ・破損の有無等)、かみ合わせの状態、口腔内の状態(歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程度、腫れ・出血の有無等)、口腔ケアの状況に関する項目 |
| 食事摂取の状況 | 食事摂取の状況(食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備をする人等)、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量(栄養、水分量等)、食事制限の有無に関する項目 |
| 社会との関わり | 家族等との関わり(家庭内での役割、家族等との関わりの状況(同居でない家族等との関わりを含む)等)、地域との関わり(参加意欲、現在の役割、参加している活動の内容等)、仕事との関わりに関する項目 |
| 家族等の状況 | 本人の日常生活あるいは意思決定に関わる家族等の状況(本人との関係、居住状況、年代、仕事の有無、情報共有方法等)、家族等による支援への参加状況(参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等)、家族等について特に配慮すべき事項に関する項目 |
| 居住環境 | 日常生活を行う環境(浴室、トイレ、食事をとる場所、生活動線等)、居住環境においてリスクになりうる状況(危険個所の有無、整理や清掃の状況、室温の保持、こうした環境を維持するための機器等)、自宅周辺の環境やその利便性等について記載する項目 |
| その他留意すべき事項・状況 | 利用者に関連して、特に留意すべき状況(虐待、経済的困窮、身寄りのない方、外国人の方、医療依存度が高い状況、看取り等)、その他生活に何らかの影響を及ぼす事項に関する項目 |
課題分析に関する項目は、利用者の体調や身体機能などに関する情報をより細かく聞き出す内容に設定されています。
課題分析に関する項目の一覧
課題分析に関する項目の記載例は以下のとおりです。
| 健康状態 | 過去に膝・大腿部を骨折した経験あり 高血圧・高脂血症の服薬あり 腰痛あり |
| ADL | ほぼ自立 ただし、腰痛が悪化すると階段の上り下り・入浴・トイレなどが困難になる |
| IADL | ほぼ自立 |
| 認知機能や判断能力 | 記憶力・判断能力に問題はない |
| コミュニケーションにおける理解と表出の状況 | コミュニケーション能力に問題ない社交的であり、相手に配慮した会話ができる |
| 生活リズム | 年相応に睡眠が浅くなってはいるものの、おおむね問題はない 朝方の生活であり、昼夜逆転の傾向はなし |
| 排泄の状況 | 腰痛がひどいときは自立した排泄は困難になるものの、おおむね問題はない 排泄の頻度にも問題はない |
| 清潔の保持に関する状況 | 入浴・整容に問題はないが、腰痛が悪化した際は自立した入浴は困難 それもあって入浴の頻度は週4回程度に減っている |
| 口腔内の状況 | 部分入れ歯を使用しており、メンテナンスのために2ヶ月に1回程度の歯科検診を受けている |
| 食事摂取の状況 | 自立 |
| 社会との関わり | 近所に友人が多く、定期的に外食をともにしている ただし、腰痛の影響もあって、外出の頻度は週4回程度 |
| 家族等の状況 | 家族との関係は良好今でも年に3回ほど旅行に行く遠方に住む家族とは定期的に連絡を取っているが、お盆・年末年始に会う程度 |
| 居住環境 | 一軒家腰痛が悪化していなければ階段の上り下りに問題はない |
| その他留意すべき事項・状況 | 遠方に住む家族との関係は良好だが、先方の奥様・ご主人に気を使っている 同居している息子家族に対しても、負担をかけたくないと強く思っている |
なお、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて、「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
質の高いアセスメントを実施する5つのポイント

より良いアセスメントシートを作成するなら、質の高いアセスメントを実施しなければなりません。
アセスメントの質を高めるなら、以下のポイントを意識しましょう。
- 利用者に寄り添って情報を深掘りする
- 家族へのヒアリングも行う
- 必要があれば専門家に同席してもらう
- アセスメント力を高める
- アセスメントシートを効率的に管理する
アセスメントの質向上は、ケアマネージャーにとって重要な課題です。
それぞれのポイントを正確に把握しましょう。
利用者に寄り添って情報を深堀りする
アセスメントは利用者に寄り添って情報を深掘りすることが基本です。
体調・日常生活での困り事・本人や家族の希望など、多角的な観点から情報を集めれば、よりニーズに沿ったケアプランを作成できます。
必要な際は地域包括支援センターや医療機関など、他の専門機関から情報を得ると、より正確に利用者の状況を把握できます。
なお、アセスメントは利用者の体調や事情を配慮しつつ、相手とともに考えるスタンスで臨みましょう。
ケアマネージャーから一方的に質問するようなやり方は避け、できる限り相手の意向を尊重する方法にすれば、利用者の自立心を損ないません。
また、情報を聞き出す際は質問をなるべく具体的なものにしましょう。
情報が具体的であるほど、利用者に最適な介護サービスが明確になります。
家族へのヒアリングも行う
アセスメントにおいて、家族へのヒアリングは不可欠です。
利用者と家族の関係は介護において重要なものであり、家族の意向も踏まえることで、より質の高いケアが実践できます。
また、家族へのヒアリングは利用者が話した内容を補完するうえでも欠かせない取り組みです。
利用者本人の記憶が曖昧な際は、家族に事実確認を行いましょう。
一方で、利用者やその家族の意向を聞きすぎることには注意が必要です。
利用者やその家族が介護サービスの範囲や制度を理解しているとは限りません。
そのため、場合によっては要求が過剰になり、カスタマーハラスメントに発展する恐れがあります。
介護に対する利用者やその家族の認識が誤っている際は、適宜フォローし、介護サービスについて理解してもらえるようにしましょう。
必要があれば専門家に同席してもらう
必要があれば、専門家に同席を求めましょう。
利用者が言いづらいことや、家族でも把握していないことがある際は、主治医や担当の専門家に同席してもらえば、より具体的な情報が得られます。
専門家から情報を得られれば、ケアプランのすり合わせもしやすくなります。
特に、利用者に持病がある際は医学的観点は重要です。
健康状態に配慮したケアプランを作成するうえでも、主治医や専門医の意見は積極的に取り入れましょう。
アセスメント力を高める
もちろん、ケアマネージャー本人のアセスメント力も重要です。
利用者の状況を的確に把握し、情報を引き出すスキルを身につければ、より質の高いケアプランを作成できます。
アセスメント力を高めるなら、ケアマネージャー向けの研修や勉強会に参加しましょう。
アセスメントに関するさまざなスキルを学べます。
経験豊富な先輩のケアマネージャーに相談することも効果的です。
また、他職種とも積極的に交流しましょう。
他の専門家の知識を身につければ、多角的な観点からアセスメントを実践できます。
アセスメントシートを効率的に管理する
作成したアセスメントシートは効率的に管理しましょう。
アセスメントシートは利用者の重要な情報の宝庫であり、ケアプラン作成はもちろん、状況の観察などを行う際にも活用します。
定期的に内容を確認したり、他職種と共有したりすることもあるため、スピーディーに情報を取り出せるように効率的な管理を徹底しましょう。
例えばアセスメントシートを電子化し、パソコンやタブレットなどで閲覧できるようにすれば、管理の手間を減らせます。
アセスメントシートを紙のまま保存すると管理に手間がかかるため、電子化は積極的に検討しましょう。
アセスメントシートの効率的な作成・管理にはすぐろくケアマネがおすすめ

アセスメントシートを効率的に作成・管理するなら、弊社ワイズマンのすぐろくケアマネの導入をご検討ください。
すぐろくケアマネはケアマネージャーが求める機能を搭載したソフトであり、アセスメントや他職種との情報共有をスムーズに実践できます。
また、利用者ごとの進捗管理も簡単にできるうえに、タブレットからアクセスも可能です。
すぐろくケアマネはアセスメントを含めた、ケアマネージャーのさまざまな業務を効率化できます。
気になる方は、ぜひ無料でご覧いただける資料をダウンロードしてください。

ケアプランにおけるアセスメントは非常に重要であり、これを基にケアプランを作成するのが正しい流れです。しかし実際には、ケアマネジャーが先にケアプランを作成し、後から法令遵守の観点で、アセスメントシートを完成させるというのが常態化しています。これは単にアセスメント項目を複雑なものにしてしまったがゆえでしょう。ケアマネジャーが担当できるプラン数は増えていますが、アセスメントを初めとした、整備しなければならない帳票が多すぎるのも、ケアマネジャーが人気職とはならない要因の一つと考えられます。ケアマネの業務負担軽減策はICTの活用を初めとして、議論されていますが、現状は諸々の法定書類を整備しておかないと“運営基準減算”の対象となってしまうため、必ず作成しておきましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
アセスメントシートの23項目を理解してより良いケアプランを作成しよう

アセスメントシートの23項目は、いずれもアセスメントに欠かせない情報に関連しています。
アセスメントの際は、それぞれの項目の内容を理解し、適切に聞き出せるようにしましょう。
なお、アセスメントシートの項目は厚生労働省の改正によって内容が変更される場合があります。
厚生労働省から最新の情報が出た際は、すぐに確認するように心がけましょう。
アセスメントシートを効率的に作成・管理するなら、ワイズマンのすぐろくケアマネがおすすめです。
ぜひ、導入をご検討ください。

監修:伊谷 俊宜
介護経営コンサルタント
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。