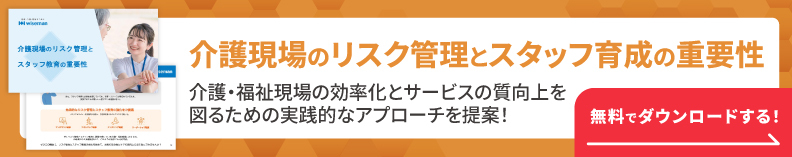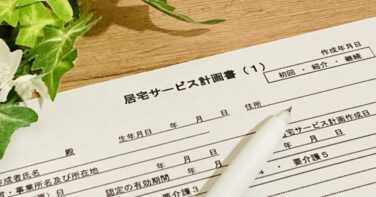ケアプランにおける居宅療養管理指導とは|書き方や具体例を解説
2025.01.22

ケアプラン作成において、居宅療養管理指導は利用者の在宅生活を支えるうえで重要な役割を果たします。
しかし、訪問看護指示書との違い・具体的な記載方法・算定要件など、わかりにくい点も多いのではないでしょうか。
本記事では、ケアプランにおける居宅療養管理指導をわかりやすく解説し、書き方や具体例・算定要件と対象者・注意点などを詳しく説明します。
質の高いケアプラン作成に役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。
なお、株式会社ワイズマンでは、介護現場でのリスク管理やスタッフの教育について課題を感じている方に向けて「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場の効率化とサービスの質向上を図るための実践的なアプローチを提案しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
ケアプランにおける居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導とは、利用者が自宅で安心して生活を送れるよう、看護師などが医療的な視点から療養上の管理や指導を行うサービスです。
居宅療養管理指導では、病状の観察・服薬管理・医療機器の使用方法指導・栄養指導・リハビリテーションの指導などを実施します。
ケアプランに居宅療養管理指導を具体的に記載することで、他の医療・介護サービスとの連携をスムーズにするうえで不可欠です。
また、利用者の状態に合わせた適切なケアを提供するうえでも役立ちます。
訪問看護指示書との違い
居宅療養管理指導と訪問看護指示書は、どちらも看護師等が在宅で医療的なケアを提供するうえで重要な役割を果たしますが、その目的や内容には違いがあります。
下記の表に違いをまとめました。
| 項目 | 居宅療養管理指導 | 訪問看護指示書 |
| 目的 | 利用者の在宅生活の維持・向上のための療養上の管理・指導 | 医師の指示に基づく具体的な医療処置の実施 |
| 内容 | 病状観察・服薬管理・医療機器使用方法指導・栄養指導・リハビリ指導などケアプランに記載し、他のサービスとの連携を図る | 医師の指示に基づく点滴・注射・創傷処置・カテーテル管理など医療保険が適用される |
| 作成者 | 看護師・准看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など | 医師 |
| 対象者 | 要介護者・要支援者 | 病状が安定しており、医師の指示が必要な医療処置を必要とする者 |
両者を適切に理解し、使い分けることで、利用者にとってより効果的な在宅ケアを提供できます。
ケアプランへの居宅療養管理指導の記載方法

ケアプランに居宅療養管理指導を記載する際は、利用者の現状や課題、目標を明確に示すことが重要です。
具体的には、以下の点に注意して記載しましょう。
- 利用者の病状や生活状況を具体的に記載する
- 居宅療養管理指導の目的を明確に記載する
- 具体的な指導内容を記載する
- 期待される効果を記載する
- 実施頻度や期間を記載する
- 担当者(ケアマネジャー)の氏名を記載する
上記の情報を漏れなく記載することで、他の医療・介護専門職との情報共有がスムーズになり、利用者にとってより適切なケアを提供できます。
また、利用者の目線から見てわかりやすいケアプランを作成しましょう。
利用者が理解しやすい内容なら、ケアプランのスムーズな共有が可能です。
具体的な記載例
本章では、居宅療養管理指導の具体的な記載例を、病状別にいくつか紹介します。
ケアプラン作成の際の参考にしてください。
| 病状 | 居宅療養管理指導の記載例 |
| 糖尿病 | 血糖値コントロール不良のため、適切な食事療法、運動療法、服薬管理について指導を行う。低血糖症状の出現時やシックデイ時の対応についても指導し、重症化予防に繋げる。週1回訪問し、血糖値測定、食事内容の確認、運動指導を実施する。 |
| 高血圧 | 血圧コントロール不良のため、減塩指導、適切な服薬管理、家庭血圧測定の指導を行う。併せて、生活習慣病予防のための運動や休養についても指導し、健康状態の維持・改善を図る。月2回訪問し、血圧測定、服薬状況の確認、生活指導を実施する。 |
| 認知症 | 認知機能の低下が見られるため、安全な生活環境の整備、服薬管理、日常生活の工夫について指導を行う。家族への介護負担軽減のための相談支援や地域資源の活用についても助言する。月1回訪問し、認知機能の評価、生活状況の確認、家族への相談支援を実施する。 |
| 脳血管疾患後遺症 | 麻痺によるADL低下が見られるため、リハビリテーションの指導、日常生活動作の訓練、福祉用具の活用について指導を行う。再発予防のための生活指導や服薬管理についても助言し、生活の質の向上を目指す。週2回訪問し、リハビリテーションの実施、ADL訓練、生活指導を行う。 |
居宅療養管理指導は、利用者の状況に合わせて、具体的な内容を記載する必要があります。
また、ケアプランは利用者の生活に寄り添い、自立を支援するためのものであるため、利用者本人の意向を尊重しながら作成しましょう。
関連記事:施設ケアプランの文例|第1表・第2表ごとに記入例をご紹介
ケアプラン(居宅サービス計画書)の文例|第1表や第2表などの書き方を解説
なお、介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方に向けて、「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
居宅療養管理指導の算定要件と対象者

居宅療養管理指導を算定するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件を正しく理解し、適切にサービスを提供すれば、利用者の在宅生活をより効果的に支援できます。
本章では算定できるケース・できないケースに分けて解説するので、ぜひ参考にしてください。
算定できるケース
居宅療養管理指導が算定できるケースは、主に以下のとおりです。
| 要件 | 説明 |
| 通院困難な状況 | 利用者が、家族や介護者の手を借りずに通院することが困難な状態であること。 |
| 療養上の指導の実施 | 利用者またはその家族に対し、医師による療養上の管理・指導が実際に行われていること。 |
| 継続的な管理・指導の必要性 | 一時的なものではなく、継続的な管理・指導が必要な状態であること。 |
| 訪問診療または往診の実施 | 要支援・要介護者の居宅に、月1回以上訪問診療または往診を行っている医師が居宅療養管理指導を行うこと。 |
| 情報通信機器を用いた場合 | 初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定が可能。訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居宅療養管理指導についても算定可能。上限は月4回まで。 |
上記の要件をすべて満たしている場合、居宅療養管理指導を算定できます。
特に、利用者の状況が「通院困難」であるかどうかは重要なポイントです。
単に「通院が面倒」のような理由だけでは算定できません。
算定できないケース
以下のようなケースでは居宅療養管理指導を算定できません。
| 状況 | 説明 |
| 通院可能な状況 | 利用者が家族や介護者の手を借りずに、自身で通院できる状態である場合。 |
| 継続的な管理・指導が不要 | 病状が安定しており、継続的な管理・指導を必要としない場合。 |
| 医師による指導が実施されていない | 医師による療養上の管理・指導が実際に行われていない場合。 |
居宅療養管理指導は、利用者の状態に合わせて適切に提供されるべきサービスです。
上記のようなケースでは、ほかの適切なサービスの利用を検討する必要があります。
かかりつけ医と連携を取りながら、利用者にとって最適なケアプランを検討しましょう。
算定要件を満たすための注意点

居宅療養管理指導を適切に算定するためには、以下のような注意点があります。
- 算定要件の確認と記録の徹底
- 関係機関との連携
- 定期的な評価と見直し
- 倫理的な配慮
それぞれの注意点を意識することで、算定漏れを防ぎ、適正な報酬を得られる可能性が高まります。
算定要件の確認と記録の徹底
居宅療養管理指導を算定するためには、利用者の状態や提供したサービス内容が算定要件を満たしているかを確認することが重要です。
確認した内容はケアプランや関連書類に明確に記録しておきましょう。
記録が不十分な場合、算定要件を満たしていても、適切に評価されない可能性があります。
記録すべき算定要件は以下のとおりです。
| 確認事項 | 記録内容 |
| 対象者であるか | 利用者の病状・病名・日常生活の状況など、対象者であることを裏付ける具体的な情報 |
| 医学的管理の必要性 | 病状の不安定さ・治療内容の複雑さなど、医学的管理が必要である理由 |
| 指導内容 | 具体的な指導内容・指導日時・指導時間・指導者名など |
| 指導の効果 | 指導による利用者の状態の変化・改善点など |
関係機関との連携
居宅療養管理指導は、主治医・訪問看護師・薬剤師など、ほかの医療・介護専門職との連携が不可欠です。
利用者の状態やケア内容に関する情報を共有し、連携してケアを提供することで、より効果的な療養管理指導を実施できます。
また、連携内容についても記録に残しておきましょう。
すぐに記録を確認できるようにしておけば、ケアプランの進捗状況の調整などがスムーズにできます。
定期的な評価と見直し
利用者の状態は変化する可能性があるため、居宅療養管理指導の内容も定期的に評価し、必要に応じて見直す必要があります。
作成時だけでなく、サービス提供中に利用者の状態が変化した場合も、速やかにケアプランを見直しましょう。
定期的な評価と見直しは、質の高いケアを提供するうえで欠かせません。
状況に合わせて常に最適化することで、より利用者のニーズに適合したサービスを提供できます。
倫理的な配慮
居宅療養管理指導を行う際には、利用者のプライバシー保護や自己決定権の尊重など、倫理的な配慮も重要です。
利用者の意思決定を尊重し、利用者本位のケアを提供するように心がけましょう。
また、利用者の情報は個人情報保護法に基づき、適切な情報管理を行う必要があります。
個人情報の漏洩は利用者からの信頼を失うだけでなく、訴訟のリスクを高めます。
居宅療養管理指導を踏まえたケアプラン作成ならすぐろくケアマネを導入しよう

居宅療養管理指導を踏まえ、より質の高いケアプラン作成を目指すなら、ぜひ弊社ワイズマンのすぐろくケアマネを導入しましょう。
すぐろくケアマネは居宅介護支援事業所向けに開発されており、より良質なケアプラン作成に役立つ介護ソフトです。
すぐろくケアマネは利用者の基本的な情報はもちろん、ケアプランの進捗などもスピーディーに確認できます。
加えて、アセスメントやモニタリングも効率的に実践できるため、ケアプランの評価や修正にも役立てられます。
居宅介護支援事業所にとって、すぐろくケアマネは欠かせないツールです。
ぜひ無料でダウンロードできるカタログをご覧ください。

居宅療養管理指導のケアプランへの位置づけは、多くのケアマネが頭を悩ませる項目ではないでしょうか。ローカルルールが蔓延する業界なので、保険者によって解釈の違いがある可能性はありますが、居宅療養管理指導は保険給付外サービスであるため、原則ケアプランへの記載は不要です。生活保護受給者の場合、自治体の生活支援課などから介護券発券のためケアプラン提出を求められるため、ケアプランの2表に記載するケースが多いのが現状です。このケースでも本来ケアプランへの記載は不要で、強いて言えば3表の週単位以外サービスに記載する形でもOKです。もちろん2表に記載してはいけないというわけではなく、記載した方がベターなのは間違いありません。ケアマネへの負荷が大きくなっているので、こういうところでも簡略化を図りたいところです。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
居宅療養管理指導は質の高いケアプランの作成に不可欠

居宅療養管理指導は、質の高いケアプランを作成するうえで不可欠な要素です。
看護師など医療の専門家が自宅で過ごすうえで必要な指導を行うことにより、利用者が安心して過ごせるようになります。
ただし、適切な居宅療養管理指導を実施するには、意識すべき注意点やポイントがあります。
また、算定要件を満たしているかどうかも必ず確認しましょう。
居宅療養管理指導を踏まえてケアプランを作成すれば、サービスの質向上につながります。
ワイズマンのツールも活用し、より利用者に寄り添ったケアプランの作成を目指しましょう。

監修:伊谷 俊宜
介護経営コンサルタント
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。