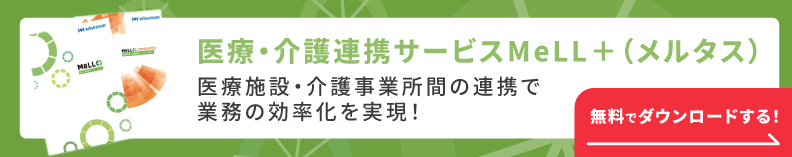地域包括ケアシステムが推進される理由とは?制度の背景や課題を解説
2025.01.22

高齢化が進む現代社会において、医療や介護のニーズはますます複雑化する状況で、重要なキーワードとなるのが地域包括ケアシステムです。
地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、医療・介護・生活支援などが包括的に提供される体制づくりを目指しています。
本記事では、地域包括ケアシステムが推進される理由に加え、その仕組みや地域別の事例などを解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
目次
地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、可能な限り自立した生活を送れるように、医療・介護・住まいなどを包括的に提供する体制です。
おおむね30分以内に必要なサービスが提供される範囲を「日常生活圏域」とし、各種サービスが切れ目なく提供されることを目指しています。
超高齢社会を迎える日本では、医療や介護を必要とする高齢者が増加の一途をたどっています。
従来のように病院や施設でケアを提供するだけでなく、地域全体で高齢者を支える仕組みが不可欠です。
そのため、現在は地域包括ケアシステムのニーズが高まっており、日本各地で積極的に推進されています。
地域包括ケアシステムが推進される背景
地域包括ケアシステムが推進される背景には、日本の高齢化の急速な進展があります。
現在の日本は、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、超高齢化社会が本格化すると予測されています。
その結果、医療や介護への需要の増加に対し、病院や施設だけでは対応しきれなくなることが懸念されるようになりました。
加えて、認知症患者の症状を緩和させるためにも、地域による支援は不可欠です。
また、高齢者人口の増加だけでなく、単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加も、地域包括ケアシステムの推進と密接に関係しています。
昨今の日本は、核家族化や少子化が進み、家族による介護が難しくなるケースが増えているため、地域社会による支援の重要性が増しました。
地域包括ケアシステムは、認知症の方が地域で安心して暮らせるためのサポート体制の構築も目指しています。
以上のように、地域包括ケアシステムが推進される背景には、高齢者や医療・介護にまつわるさまざまな問題があります。
参照:医療介護総合確保推進法(医療部分)の概要について|厚生労働省
地域包括ケアシステムの仕組み
地域包括ケアシステムは、複数の構成要素と「4つの助」と呼ばれる考え方によって支えられているシステムです。
本章では、地域包括ケアシステムの仕組みについて解説します。
地域包括ケアシステムの構成要素
地域包括ケアシステムは、主に以下の構成要素から成り立っています。
| 構成要素 | 内容 |
| 住まい | 高齢者が安心して住み続けられるための住居の確保や、住宅改修などの支援を実施 |
| 医療・看護 | かかりつけ医による健康管理・病院での治療・訪問看護など、医療・看護サービスを提供 |
| 介護・リハビリテーション | 訪問介護・通所介護・施設介護など、必要な介護サービスを提供し、リハビリテーションを通して自立支援を実施 |
| 保健・福祉 | 健康相談・保健指導・介護予防教室の開催など、高齢者の健康増進や生活の質の向上を支援 |
| 介護予防・生活支援 | 介護が必要になることを予防するための支援・生活に必要なサービスを提供し、自立した生活をサポート |
地域包括ケアシステムを支える4つの助【自助・互助・共助・公助】
地域包括ケアシステムは、「自助」「互助」「共助」「公助」と呼ばれる4つの「助」の連携によって支えられています。
それぞれの「助」は役割があり、いずれも持続可能なシステムを構築するうえで欠かせません。
それぞれの「助」の内容は以下のとおりです。
| 4つの助 | 内容 |
| 自助 | 高齢者自身が健康管理や介護予防に積極的に取り組み、自立した生活を維持するための努力をすること |
| 互助 | 家族・友人・近隣住民同士が支え合い、助け合うこと |
| 共助 | 介護保険などリスクを共有する被保険者の負担 |
| 公助 | 行政による生活保護や介護保険制度などの社会保障サービス、公的な支援の提供 |
地域包括ケアシステムと関連制度の関係性
地域包括ケアシステムは、単独で機能するのではなく、さまざまな関連制度と連携することで、より効果的な支援を実現しています。
本章では、特に重要な以下の連携について解説します。
- 介護保険制度
- 医療保険制度
- その他の制度
いずれの制度も地域包括ケアシステムの構造を理解するうえで不可欠なものです。
正確に把握しましょう。
参照:地域づくりにおける地域包括ケアシステム|厚生労働省
地域包括ケアシステム|厚生労働省
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
地域包括ケアシステムと介護保険制度の連携
介護保険制度は、地域包括ケアシステムを支える重要な柱です。
要介護認定を受けた高齢者は、介護保険サービスを利用することで、自宅での生活を続けたり、施設でのケアを受けたりできます。
地域包括ケアシステムは、介護保険サービスを他のサービスと組み合わせ、より包括的な支援を提供することを目指しています。
| 制度 | 役割 | 連携のポイント |
| 介護保険制度 | 要介護状態の高齢者に対するケアサービスの提供 | 要介護認定の申請支援・ケアプラン作成への協力・サービス提供事業者との連携 |
地域包括支援センターは、介護保険サービスの利用相談やケアプラン作成の支援など、介護保険制度と密接に連携しながら活動する施設です。
地域包括支援センターが中心となることで、利用者に寄り添った適切なサービスを提供できます。
医療保険制度との関わり
医療保険制度も、地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担っています。
病気の治療・予防・健康管理など、医療サービスは高齢者の生活を支えるうえで欠かせません。
地域包括ケアシステムは、医療機関との連携を強化することで、在宅医療や訪問看護などのサービス提供をスムーズに実践できる体制を整備しています。
| 制度 | 役割 | 連携のポイント |
| 医療保険制度 | 病気の治療・予防・健康管理に関するサービスの提供 | かかりつけ医との連携強化・訪問診療や訪問看護の推進・医療機関との情報共有 |
地域包括ケアシステムを支えるその他の制度
介護保険制度や医療保険制度以外にも、地域包括ケアシステムを支えるさまざまな制度が存在します。
例えば、障害者総合支援法・生活保護法・高齢者の居住の安定確保に関する法律などです。
いずれの制度も、それぞれ異なる分野の支援を提供しています。
さらに地域包括ケアシステムとの連携によって、高齢者の多様化したニーズに対応したサービスを受けられる体制を実現しています。
| 制度 | 役割 | 連携のポイント |
| 障害者総合支援法 | 障がいのある人への包括的な支援 | 介護と福祉の連携強化・地域での生活支援の充実 |
| 生活保護法 | 生活に困窮する人への最低限度の生活保障 | 生活困窮者への医療・介護サービスの提供 |
| 高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 高齢者の住まいの確保と居住の安定 | 高齢者向け住宅の整備促進・住まいと介護サービスの連携 |
それぞれの制度が適切に機能することにより、個々の利用者の事情に寄り添ったサービスの提供が可能です。
地域包括ケアシステムの3つの事例

本章では、地域包括ケアシステムの事例を紹介します。
紹介する事例は以下のとおりです。
- NPO法人が中心となって多様な自立支援を実現|大阪府大阪市
- 介護予防ボランティアによる介護予防や地域交流の実施|群馬県前橋市
- 住民参加型の生活支援サービスを活用した街づくり|愛知県名古屋市
いずれの事例も、地域包括ケアシステムを推進・構築するうえで役立つものです。
ぜひ参考にしてください。
NPO法人が中心となって多様な自立支援を実現|大阪府大阪市
大阪府大阪市では、NPO法人のフェリスモンテが主体となり、高齢者支援や地域交流支援だけでなく、子育て支援・障がい者支援などの多様な支援を提供しています。
フェリスモンテは「お互い様のたすけあい活動」と称し、住み慣れた地域で暮らしやすくするためのさまざまな活動を実践しています。
さらに制度の変化に合わせ、公的事業・委託事業・自主事業に分けて活動を変容させるなど、柔軟に対応している点も特徴です。
フェリスモンテの活動は高齢者だけでなく、子育て世代や就職困難者など、さまざまな立場の人の自立支援を実現しています。
参照:NPO法人による自主サービスと公的サービスの一体的提供|厚生労働省
介護予防ボランティアによる介護予防や地域交流の実施|群馬県前橋市
群馬県前橋市では、介護予防ボランティアが中心となり、介護予防や地域交流の取り組みを積極的に実施しています。
本事例は、介護予防ボランティアが高齢者が歩いて通える身近な場所で介護予防プログラムに参加できるように取り組んでいる点が特徴です。
手軽に取り組める健康体操の指導や、イベントの実施などを行った結果、前橋市では地域交流のためのサロン・グループの数が増大しました。
参照:介護予防ボランティアによる「ピンシャン!元気体操」の普及促進と介護予防|厚生労働省
住民参加型の生活支援サービスを活用した街づくり|愛知県名古屋市
愛知県名古屋市では、NPO法人の介護サービスさくらが中心となり、持続可能な地域包括ケアシステムを実現しています。
有償ボランティアから始まった介護サービスさくらは、デイサービスや訪問介護など、さまざまな介護事業を複合的に展開している点が特徴です。
介護サービスさくらは行政と協業し、高齢者向け改善住宅の巡回員や福祉施設の指定管理を実践するなど、積極的に助け合いの輪を広げています。
参照:NPO法人による住民参加型の生活支援サービスの取り組み|厚生労働省
地域包括ケアシステムの4つの課題

地域包括ケアシステムの実現には以下のような課題が存在します。
- 人材の不足
- 認知度が低い
- 地域格差が生まれやすい
- さらなる連携の強化
本章では、それぞれの課題について解説します。
人材の不足
地域包括ケアシステムを支えるには、医師・看護師・介護職員・ケアマネージャー・社会福祉士など、多職種連携による質の高いサービス提供が不可欠です。
しかし、専門職の人材は不足しています。
特に、少子化による介護職員の不足は深刻です。
高齢化の進展に伴い、さらに需要が高まることが予想されています。
質の高いサービスを提供するためには、人材の確保と育成が急務です。
認知度が低い
地域包括ケアシステムの認知度が低いことも課題です。
制度の目的や内容が十分に理解されていないため、サービスの利用が進まない・地域住民の協力が得られないといった問題が生じています。
地域包括ケアシステムを推進するためには、制度の周知徹底を図り、地域住民への理解を深めることが重要です。
行政による広報活動だけでなく、地域住民への積極的な情報提供や、地域活動への参加促進など、多角的な取り組みが必要です。
地域格差が生まれやすい
地域包括ケアシステムは、地域の実情に応じて構築されるため、地域によってサービスの質や量に差が生じる可能性があります。
都市部と地方では、高齢化の進展状況や医療・介護資源の絶対量が大きく異なるため、地域格差の拡大が懸念されます。
すべての地域で均質なサービスを提供するためには、地域間の格差を是正するための財政支援や、地域資源の有効活用策の実施が不可欠です。
さらなる連携の強化
地域包括ケアシステムでは、医療・介護・予防・住まい・生活支援に類するさまざまなサービスが連携して提供されます。
しかし、それぞれのサービスを提供する機関の間で連携が不十分な場合、サービスがスムーズに提供されず、利用者の負担が増加する可能性があります。
多職種間の連携を強化するためには、情報共有システムの整備や、関係機関間の合同研修の実施など、具体的な取り組みが必要です。
また、地域住民・NPO・ボランティア団体との連携も重要であり、地域全体で高齢者を支える体制を構築していく必要があります。
地域包括ケアシステムを推進するならMeLL+を活用しよう

地域包括ケアシステムを推進するなら、弊社ワイズマンのMeLL+をご活用ください。
MeLL+は医療機関や介護施設などの多職種のスムーズな情報共有や、緊密な連携を実現するうえで役立つツールです。
利用者情報の共有はもちろん、スタッフや専門家同士のオンライン会議なども実践できるなど、さまざまな機能を搭載しています。
さらにワイズマンは、ソリューションの一環として、ICT導入をサポートしている点も魅力です。
適切に活用すれば、理想的な地域包括ケアシステムを構築できる可能性が高まります。

自助・互助・共助・公助は、地域包括ケアシステムの説明でよく耳にするキーワードです。中でも、国が重要視しているのは、「自助」と「互助」です。急激に高齢化が進み人口は減少フェーズに突入し、社会保障費は増大の一途を辿っています。このような背景から、「共助」「公助」の大幅な拡充を期待することは難しく、「自助」「互助」の果たす役割が大きくなることを意識した取組が必要と国も資料内で明記しています。
自助のモデルで有名なのは、財政破綻し市内唯一の病院が閉鎖となった夕張市です。病院が閉鎖してしまい、病死者が増加してしまうと心配されたのですが、実際には、病院が無くなったことにより、市民の健康意識が高まった結果、夕張市内での「老衰死」が増加し、「病死」が減少したのです。夕張モデルは自助のモデルケースでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
地域包括ケアシステムの推進は社会の課題

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられる理想的な仕組みです。
しかし、その実現にはさまざまな課題があるため、当事者は解決に取り組む必要があります。
地域包括ケアシステムの推進における課題を整理し、解決策を探ることは、高齢者だけでなく、すべての人々が安心して暮らせる地域社会の実現につながります。
弊社ワイズマンのツールを活用し、理想的な地域包括ケアシステムを実現してください。

監修:伊谷 俊宜
介護経営コンサルタント
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。