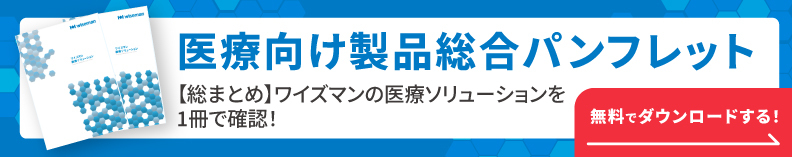医療DXとは|求められる背景・導入ステップ・課題などを解説
2025.04.18

昨今の医療業界において、医療DXは重要な課題です。
医療サービスの質向上や業務効率化など、数多くのメリットが期待できます。
しかし、同時にセキュリティ対策の必要性や初期費用の問題など、医療DXの推進にはいくつかの課題も存在します。
本記事では医療DXの導入ステップや課題などについて解説します。
実際に医療DXに取り組む際の参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
ワイズマンが提案する医療ソリューションに関する情報を1冊の資料に集約しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
医療DXとは

まずは、医療DXの定義や求められる背景についてお伝えします。
医療DXは、医療業界のさまざまな課題と関連しているものです。
医療DXの定義
医療DXとは、デジタル技術を活用して医療の質・効率・患者体験を向上させる取り組みのことです。
厚生労働省は医療DXについて、以下のように記載しています。
医療DXとは、保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤(クラウドなど)を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることです。
参照:医療DXについて|厚生労働省
医療DXは単なるIT化とは異なり、デジタル技術を深く組み込むことで、医療現場全体の変革を促します。
例えば、電子カルテの導入による情報共有の効率化・オンライン診療による患者の利便性向上・AIを活用した診断支援などが代表的な施策です。
医療DXが求められる背景
医療DXが求められる背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。
| 少子高齢化による医療ニーズの増大 | 高齢化が進むにつれて、慢性疾患を持つ患者が増加し、医療ニーズはますます多様化・高度化しています。 限られた医療資源でこれらのニーズに対応するためには、業務効率化と医療の質向上が不可欠です。 |
| 医療スタッフの働き方改革 | 医師の長時間労働は深刻な問題となっており、その是正が急務です。 医療DXによって、事務作業の自動化や情報共有の効率化が進むことで、医療スタッフの負担を軽減し、より患者に向き合う時間を増やすことが期待されています。 |
| 医療機関の経営悪化 | 診療報酬の抑制や競争激化などにより、多くの医療機関が経営難に直面しています。 医療DXによる業務効率化や新たな収益源の創出は、医療機関の経営改善に貢献すると考えられています。 |
| 患者のニーズの変化 | 患者は、より便利で質の高い医療サービスを求めています。 オンライン診療や遠隔医療など、デジタル技術を活用した新しい医療サービスの提供は、患者満足度向上につながります。 |
上記のような背景から、医療DXは、医療業界が持続可能な形で発展していくために不可欠な取り組みであると捉えられます。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
ワイズマンが提案する医療ソリューションに関する情報を1冊の資料に集約しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
医療DXの5つのメリット

医療DXの導入は、さまざまなメリットにつながる取り組みです。
主なメリットには、以下のようなものがあります。
- 業務効率化による医療スタッフの負担軽減
- 医療サービスの質の向上
- 患者の利便性の向上
- ほかの医療機関との連携強化
- 設備停止のリスク回避
それぞれについて、順番に解説します。
業務効率化による医療スタッフの負担軽減
医療DXの推進により、手作業で行っていた業務の自動化や、情報の一元管理を実現すれば、医療スタッフの負担の軽減が可能です。
例えば、オンライン予約システムを導入することで、電話対応の時間を削減し、医療スタッフがケアに集中しやすい環境を構築できます。
また、電子カルテの導入により、紙カルテの管理や保管にかかる手間を省き、必要な情報を迅速に検索できるようになります。
これにより、医療スタッフはより患者に向き合う時間を増やせるため、医療サービスの質の向上も可能です。
医療サービスの質の向上
医療DXは、医療サービスの質を向上させることにも貢献する取り組みです。
例えば、遠隔診療の導入により、地理的な制約のある患者や、通院が困難な患者も、専門医の診察を受けられます。
また、AIを活用した診断支援システムは、医師の診断精度を向上させ、より的確な治療を提供できます。
さらに、患者のバイタルデータをリアルタイムでモニタリングすることで、異常の早期発見や、重症化の予防も可能です。
患者の利便性の向上
医療DXは、患者の利便性も大きく向上させます。
例えば、オンライン予約やオンライン診療を導入すれば、患者は自宅や職場から、都合の良い時間に診察を受けられるため、スムーズな通院が可能です。
また、スマートフォンアプリを活用することで、診察予約・問診票の記入・診療費の支払いなどを、オンラインで完結させられます。
これにより、患者は病院での待ち時間を減らし、よりスムーズに医療サービスを受けられます。
ほかの医療機関との連携強化
医療DXは、医療機関同士の連携を強化するうえでも重要な役割を果たす施策です。
医療情報ネットワークを構築することで、患者の診療情報を、複数の医療機関で共有できます。
そのため、患者はどの医療機関を受診しても、一貫した医療サービスを受けられるうえに、重複した検査や投薬を避けられます。
また、災害時などには、医療機関同士が連携して、迅速かつ適切な医療の提供が可能です。
設備停止のリスク回避
医療機器のIoT化を進めることで、故障や不具合の予兆を早期に検知し、設備停止のリスクを回避できます。
また、センサーで取得したデータを分析することで、機器のメンテナンス時期を予測し、計画的なメンテナンスを実施することが可能です。
これにより、医療機器の安定稼働を維持し、医療サービスの提供を滞りなく実行できます。
医療DXの4つのデメリット

医療DXの導入にあたっては、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。
- 初期費用やランニングコストの発生
- セキュリティ対策が必須
- デジタル人材の確保が困難
- 患者に敬遠されるリスク
本章では、医療DXを導入する際に注意すべき4つのポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
初期費用やランニングコストの発生
医療DXにおいて、初期費用やランニングコストは無視できない要素です。
医療DXを導入するためには、初期費用としてシステム導入費用や設備投資費用が発生します。
また、導入後もシステムの運用・保守費用、セキュリティ対策費用などのランニングコストがかかります。
オンライン診療システムを例に挙げると、導入費用に加えて、システムの運用や保守・セキュリティ対策など継続的な費用が発生します。
費用対効果を十分に検討し、経営を圧迫しない範囲で導入を進めることが重要です。
セキュリティ対策が必須
医療情報は非常に機密性の高い個人情報であり、漏洩した場合の影響は計り知れません。
そのため、医療DXを推進するうえで、セキュリティ対策は最重要課題の一つです。
不正アクセス対策・情報漏洩対策・ウイルス対策など、多岐にわたるセキュリティ対策を講じる必要があります。
セキュリティ対策には専門的な知識が必要となるため、専門業者への依頼も検討しましょう。
デジタル人材の確保が困難
医療DXを効果的に活用するためには、ITに関する知識やスキルを持ったデジタル人材が不可欠です。
しかし、医療機関においては、デジタル人材が不足しているのが現状です。
既存のスタッフへの研修や教育・外部からの専門家の採用など、デジタル人材の育成・確保に力を入れる必要があります。
患者に敬遠されるリスク
高齢者を中心に、デジタル技術に不慣れな患者も少なくありません。
医療DXを導入することで、かえって患者の利便性を損ねてしまう可能性があります。
例えば、オンライン診療を導入しても、操作方法がわからず利用をためらう患者もいる可能性は十分想定できます。
そのため、患者のITリテラシーに合わせた丁寧な説明やサポート体制を整えることが重要です。
医療DXを導入するなら、デジタル技術に不慣れな患者にも安心して利用してもらえるよう、配慮が必要です。
医療DXの導入ステップ

医療DXの導入ステップは以下のとおりです。
- 現状分析と課題の明確化
- 目標設定と計画策定
- システム選定と導入
- 運用と評価・改善
医療DXを成功させるためには、計画的な導入が不可欠です。
本章では、医療DXの導入ステップをそれぞれ順番に解説します。
現状分析と課題の明確化
最初に行うべきは、現状の医療機関の状況を詳細に分析し、課題を明確にすることです。
業務プロセス・IT環境・スタッフのスキル・患者のニーズなど、さまざまな角度から現状を把握します。
例えば、「待ち時間が長い」「予約が取りにくい」「紙カルテの管理が煩雑」などが課題として挙げられます。
課題を明確にすれば、導入すべきシステムやツールが定まるため、スムーズな医療DXの推進が可能です。
目標設定と計画策定
現状分析で課題が明確になったら、医療DXによって達成したい具体的な目標を設定しましょう。
目標は、数値で測定可能なものにすると、効果測定がしやすくなります。
例えば、以下のような目標です。
- オンライン予約システムの導入により、患者の待ち時間を平均30分短縮する。
- 電子カルテの導入により、事務作業時間を20%削減する。
- オンライン診療の導入により、患者満足度を80%以上にする。
目標を設定したら、目標達成のための具体的な計画を策定しましょう。
システム選定と導入
計画に基づいて、実際にシステムを選定し、導入を行います。
システム選定の際には、以下の点を考慮することが重要です。
| 機能 | 必要な機能が搭載されているか、使いやすいかなどを確認します。 |
| 価格 | 予算に合った価格であるかを確認します。 |
| ベンダー | 信頼できるベンダーであるか、サポート体制が充実しているかなどを確認します。 |
| セキュリティ | セキュリティ対策が万全であるかを確認します。 |
システム導入時には、既存システムとの連携・データ移行・スタッフへの研修など、さまざまな作業が必要です。
ベンダーと連携しながら、スムーズな導入を目指しましょう。
運用と評価・改善
システム導入後も、定期的に効果を評価し、改善を続けることが重要です。
目標達成度・患者満足度・業務効率などを測定し、課題があれば改善策を講じます。
具体的には、以下のような取り組みです。
| 効果測定 | 設定した目標が達成できているかを定期的に測定します。 |
| 患者アンケート | 患者にアンケートを実施し、満足度や改善点などを把握します。 |
| スタッフからのフィードバック | スタッフからシステムの使い勝手や改善点などのフィードバックを収集します。 |
| システム改善 | 効果測定・患者アンケート・スタッフからのフィードバックを基に、システムを改善します。ベンダーと連携しながら、定期的にアップデートや機能追加を行います。 |
医療DXは、一度導入したら終わりではありません。
継続的な運用と改善を通じて、医療サービスの質向上・業務効率化・患者満足度向上を目指しましょう。
医療DXの課題と対策

医療DXの導入はさまざまな課題が想定されるため、適切な対策を講じる必要があります。
本章では、医療DXの課題と対策について、以下のように解説します。
- セキュリティ対策を徹底する
- DX人材の育成や医療スタッフのリテラシー向上を目指す
- 補助金などで資金を調達する
- 標準化・相互運用性の確保
医療DXを成功させるためにも、それぞれの対策を正確に理解しましょう。
セキュリティ対策を徹底する
医療DXを推進するうえで、セキュリティ対策は重要です。
医療情報は患者の個人情報であり、漏洩や改ざんは患者に深刻な損害を与える可能性があります。
また、個人情報の漏洩は医療機関の運営にも大きな影響を及ぼしかねません。
具体的な対策としては、以下のものが挙げられます。
| アクセス制御の強化 | 職員のID・パスワード管理を徹底し、アクセス権限を必要最小限に設定する。 |
| ファイアウォールや侵入検知システムの導入 | 不正アクセスを遮断し、サイバー攻撃を早期に発見する。 |
| データの暗号化 | 重要な医療データを暗号化し、万が一の情報漏洩に備える。 |
| セキュリティ教育の実施 | 職員に対して定期的なセキュリティ教育を実施し、セキュリティ意識の向上を図る。 |
| インシデント対応計画の策定 | 万が一のセキュリティインシデント発生時に、迅速かつ適切な対応を行うための計画を策定する。 |
上記の対策を講じることで、サイバー攻撃のリスクを低減し、安全な医療DXを実現できます。
DX人材の育成や医療スタッフのリテラシー向上を目指す
医療DXを成功させるためには、システムを導入するだけでなく、それを使いこなせる人材の育成が不可欠です。
DXを推進できる専門的な人材の確保はもちろん、既存の医療スタッフ全体のデジタルリテラシー向上も重要な課題となります。
具体的な対策としては、以下のものが挙げられます。
| DX推進チームの設置 | 医療DXを専門的に推進するチームを設置し、リーダーシップを発揮できる人材を育成する。 |
| 外部研修への参加促進 | 職員に外部のDX研修やセミナーへの参加を促し、最新の知識や技術を習得する機会を提供する。 |
| OJT(On-the-Job Training)の実施 | 実際にシステムを運用しながら、知識やスキルを習得するOJTを実施する。 |
| eラーニングの導入 | 時間や場所にとらわれずに学習できるeラーニングを導入し、職員のデジタルリテラシー向上を図る。 |
| ベンダーによる研修の活用 | システム導入時に、ベンダーによる研修を実施してもらい、操作方法や活用方法を習得する。 |
医療機関全体のDXリテラシーを高め、システムを最大限に活用できる体制を構築することが重要です。
補助金などで資金を調達する
医療DXの導入には、初期費用やランニングコストが発生するため、国や地方自治体が提供する補助金や助成金を活用することが有効な手段です。
医療DXに関連する補助金・助成金の例としては、以下のようなものが挙げられます。
| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウェア・サービスなど)を導入する際に、経費の一部を補助する制度。 |
| 地域医療介護総合確保基金 | 都道府県が地域の実情に応じて、医療・介護の連携強化や在宅医療の推進などの事業を実施する際に活用できる基金。 |
補助金・助成金を活用することで、初期費用を抑え、医療DXの導入を促進できます。
各自治体の情報を確認し、積極的に申請を検討しましょう。
標準化・相互運用性の確保
医療DXを推進するうえで、異なる医療機関やシステム間でのデータ連携を可能にするための標準化・相互運用性の確保が重要な課題となります。
電子カルテや診療情報提供書などの情報を標準化することで、医療機関間の情報共有がスムーズになり、患者はより質の高い医療サービスを受けられます。
具体的な対策は以下のとおりです。
| HL7 FHIRなどの標準規格の採用 | HL7 FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)などの国際的な標準規格を採用し、データ形式や通信プロトコルを統一する。 |
| 医療情報標準化に関するガイドラインの遵守 | 厚生労働省が策定する医療情報標準化に関するガイドラインを遵守し、標準的なデータ形式や用語を使用する。 |
| 相互接続性のテストの実施 | 異なるシステム間の相互接続性をテストし、データ連携が正常に行われることを確認する。 |
| 医療情報連携ネットワークへの参加 | 地域や全国の医療情報連携ネットワークに参加し、他の医療機関との情報共有を促進する。 |
標準化・相互運用性を確保することで、医療機関間の連携が強化され、地域医療全体の質の向上が期待できます。
医療DXを導入するならワイズマンの医療向け製品を活用しよう
医療DXを導入するなら、ぜひ弊社ワイズマンの医療向け製品をご活用ください。
ワイズマンは中小規模の医療機関向けの製品やサービスを提供しています。
電子カルテはもちろん、診療報酬の請求に役立つ会計システムなども扱っているため、自院の課題を解決するうえで役立ちます。
また、ワイズマンはDXの経験や知識がない病院・クリニック向けのトータルサポートも実施している点も魅力です。
システムの運用方法やセキュリティ対策なども踏まえた、手厚い支援を受けられるため、安心して医療DXの導入を任せられます。

医療DXのメリットは、業務効率化による医療スタッフの負担軽減、医療サービスの質の向上、患者の利便性の向上、他の医療機関との連携強化、設備停止のリスク回避などが期待されます。これにより、患者はより良い医療をスムーズに受けられ、医療従事者はより患者に向き合う時間が増やせます。
一方、デメリットとして、初期費用やランニングコストの発生、セキュリティ対策が必須となる点、デジタル人材の確保が困難なこと、そして患者に敬遠されるリスクなどが挙げられます。
導入する際の課題としては、セキュリティ対策の徹底、DX人材の育成と医療スタッフのリテラシー向上、補助金などを活用した資金調達、そして標準化・相互運用性の確保が重要です。医療DXを成功させるためには、これらの課題への対策を的確に講じ、医療情報の標準化、情報共有の促進などの対策が急務となるでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
ワイズマンが提案する医療ソリューションに関する情報を1冊の資料に集約しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
医療DXでより良い医療サービスを提供しよう
医療DXは、医療業界全体に変革をもたらす可能性を秘めています。
積極的にDXに取り組み、より良い医療サービスを提供することで、患者の満足度向上・スタッフの負担軽減・医療機関の経営改善につなげていきましょう。
医療DXについてお悩みの方は、ぜひワイズマンにご相談ください。
現状分析から課題の明確化・システム選定・導入や運用まで、トータルでサポートを受けられるので、スムーズなDX推進が可能になります。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。