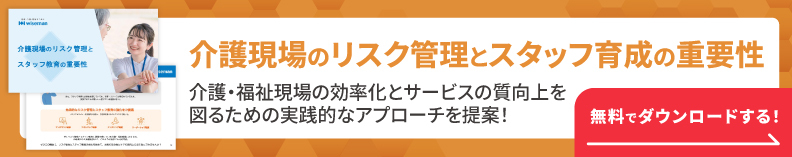訪問看護指示書とは?ルールや交付してもらえない場合の対処法
2023.02.15

訪問看護指示書とは、自宅で医療を受けるための重要な文書です。主治医が訪問看護ステーションに交付する書類であり、介護保険や医療保険を利用して訪問看護サービスを受ける際に必要とされています。訪問看護指示書には種類がいくつかあるため、それぞれの特徴を理解しておくことがポイントです。
本記事では、訪問看護指示書の概要や種類を紹介します。交付されない場合の対処法についても解説しているので、併せて参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは、介護現場でのリスク管理やスタッフの教育について課題を感じている方に向けて「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場の効率化とサービスの質向上を図るための実践的なアプローチを提案しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
訪問看護指示書とは?【在宅看護に関する文書】

訪問看護指示書とは、指定された訪問看護事業者が訪問看護サービスを提供する際に、主治医から交付される文書です。
訪問看護は介護保険と医療保険のいずれかを利用できますが、これらの保険を使うためには、法律により主治医の書面による指示が必要と定められています。なお、訪問看護指示書の有効期限は、主治医が交付してから6ヶ月です。
指示書の種類

訪問看護指示書には下記のような種類があります。
- 訪問看護指示書
- 特別訪問看護指示書
- 在宅患者訪問点滴注射指示書
- 精神訪問看護指示書
それぞれの違いを把握したうえで、適切な指示書を利用しましょう。
訪問看護指示書
訪問看護指示書とは、在宅医療を受ける際に必要な書類です。利用者の個人情報や病状などをまとめており、訪問看護指示書にしたがって訪問看護を提供します。
また訪問看護指示書を発行できると、利用者は週3回まで訪問看護を受けられます。ただし、1回あたりの訪問時間は30~90分までである点に注意が必要です。
特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書は、訪問看護指示書が交付されている方を対象に交付されます。
病状が突然悪くなったときや終末期、退院直後など、頻繁に訪問看護が必要であると主治医が認めた場合に交付される文書です。
訪問看護指示書で受けられる訪問看護サービスは週3回までですが、これよりも多く受けたい場合には、特別訪問看護指示書の交付が必要です。
なお、特別訪問看護指示書は、訪問看護指示書を交付した医師に交付してもらわなればいけません。有効期限は、看護の対象となる疾患の診療を受けた日から14日以内です。
在宅患者訪問点滴注射指示書
在宅患者訪問点滴注射指示書とは、在宅介護をするうえで点滴が必要と判断された方のための指示書です。週3日以上の点滴が必要と認められた場合、主治医が訪問看護ステーションに対して交付します。
週1〜2回の場合は、訪問看護指示書の中に点滴内容の詳細な指示があれば「在宅患者訪問点滴注射指示書」の交付は不要です。
精神訪問看護指示書
精神科訪問看護指示書とは、精神科の主治医が訪問看護の必要性を認めた場合に交付される指示書です。すべての医師が交付できるのではなく、精神科を担当する医師のみが交付することが可能です。また、精神訪問看護指示書を交付すると、看護師以外に精神保健福祉士や保健師も訪問できます。
ただし、訪問看護指示書と併用できない点に注意が必要です。なお、有効期限は1~6ヶ月です。
訪問看護指示書で特に確認が必要な項目

訪問看護指示書にしたがって訪問看護サービスが提供されるため、すべての項目においてしっかりと内容を確認しなければいけません。そのなかでも、以下の項目は特に注意しましょう。
- 訪問介護指示期間
- 主たる傷病名
- 点滴注射指示期間
- 現在の状態および状況
- 留意事項および指示事項
- 医療機関名および依頼先
それぞれについて解説します。
訪問介護指示期間
訪問看護指示書の指示期間は、1~6ヶ月と定められています。6ヶ月を超えた期間を記入してしまうと、訪問看護指示書が無効となるため注意しましょう。
| 記入例 | ポイント | |
| 有効 | 令和7年4月1日〜令和7年9月30日 | 9月末に設定しているため、6ヶ月以内になっている |
| 無効 | 令和7年4月1日〜令和7年10月1日 | 10月1日が期限になると、6ヶ月を超えている |
なお、指示期間の記入がない場合は、発行から1ヶ月が指示期間です。
点滴注射指示期間
点滴注射指示期間とは利用者に対して点滴や注射を行う際に、その期間を具体的に記載する重要な項目です。指示期間は医師が利用者の状態に基づいて決定し、適切な治療を提供するための指針です。
指示期間は最長1週間で、月に何度でも交付してもらえます。指示期間内における治療の進捗や効果を評価し、次回の指示書作成に反映すれば利用者の状態に合った最適な医療を提供することができます。
主たる傷病名
主たる傷病名とは、利用者の主病名を記載する欄です。主たる傷病名に書かれた内容によって、訪問看護における保険の種類が決まります。例えば、末期の皮膚癌であれば医療保険が適用されますが、末期でなければ介護保険が適用されます。
医療保険と介護保険では自己負担額が大きく変わるため、記入内容をしっかりと確認しましょう。
参考:令和6年度 集団指導
現在の状態および状況
現在の状態および状況の欄には、利用者の現状が記載されています。症状や服薬している薬剤の種類や量、投薬方法などを詳細に記載しておくことで、適切なサービスを提供することが可能です。
また、日常生活において自分で行えることや、認知症の症状の有無などを記載する項目もあります。訪問看護を受ける方の状態を詳細に把握できるように、些細なこともまとめておくのがポイントです。
留意事項および指示事項
留意事項および指示事項は、訪問看護を受ける際に気をつけてほしいことを記載する項目です。
例えば、食事や入浴といった日常生活の中で普段から見られる危険行動や、訪問看護師に意識してケアしてほしいことなどを記載します。
留意事項および指示事項の記載内容にあわせて、訪問看護サービスが提供されるため、間違いのないようにまとめておきましょう。
医療機関名および依頼先
訪問看護指示書の項目で特に注意して確認したいのが、医療機関名および依頼先の捺印です。捺印がないと訪問看護指示書は使用できないため、漏れがないかよく確認しましょう。捺印がない場合は交付した医療機関に連絡して、再交付の手続きを依頼してください。
具体的に確認したいポイントは、以下のとおりです。
- 訪問看護指示書を記載した日
- 医療機関名(住所や連絡先を含む)
- 担当医師名
- 医師の捺印
なお、介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方に向けて、「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
訪問看護指示書を交付してもらえない場合の対処法

訪問看護指示書は、必ずしも交付してもらえるわけではありません。依頼しても交付してもらえないときは、適切な対処法を試みてみましょう。ここでは、具体的な対策を紹介します。
交付の必要性を明確にする
訪問看護指示書の必要性を明確にすることは、スムーズな医療提供に欠かせないステップです。訪問看護を行う事業所や担当のケアマネジャーは、利用者の具体的な状況やニーズを主治医に詳細に伝えることで、訪問看護の重要性を説得力を持って説明できます。
この際、利用者からの許可を得たうえで、事業所が主治医に向けて正式な説明文書やFAXを送ることが有効です。これにより、主治医が利用者の現状を理解しやすくなり、訪問看護指示書の交付に対する同意を得やすいです。
具体的な説明には、利用者の現在の健康状態や家庭環境、日常生活のサポートがどのように必要かなどを含めると良いでしょう。また、訪問看護が利用者の生活の質向上にどれほど寄与するかを具体的に示すことも重要です。訪問看護指示書の必要性をしっかりと主治医に伝えれば、必要な支援を受けられる可能性が高まります。
指示してもらいたい内容を明確にする
主治医には、出してもらいたい指示を明確に伝えましょう。例えば、以下のような内容を明確にするのがポイントです。
- 利用者が日々の生活で困っていることはなにか
- 訪問看護を受けるメリットはなにか
主治医は利用者が診療に来たときの状態しか把握していないこともあるため、日々の様子も併せて伝えることで、交付の必要性を感じてもらいやすいでしょう。

日本は超高齢社会に突入しており、高齢者の医療ニーズが増加しており、厚生労働省が「地域包括ケアシステム」を推進し、「住み慣れた自宅での療養」を支援していること。病院ではなく、自宅での医療や介護を求める高齢者が増えていること。などの背景から、訪問看護のニーズは拡大しております。訪問看護は、医療処置や生活支援を自宅で受けるために重要なサービスですが、指示書がなければサービスの提供を行うことができません。訪問看護を受ける利用者の多くは、日々の健康管理や生活の維持に大きな支援を必要としています。主治医、訪問看護師、ケアマネジャーが連携し、指示書の内容を適切に活用することで、利用者の生活の質を向上させることができます。指示書の役割と重要性を十分に理解し、適切なケアにつなげていきましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
訪問看護指示書を交付してもらって適切な看護を提供しよう

訪問看護サービスを提供するには、訪問看護指示書を主治医から交付してもらう必要があります。場合によっては、主治医に訪問看護サービスの必要性を明確に伝えなければいけません。
また、訪問看護を提供する訪問看護ステーションでは、利用者がスムーズにケアを受けられるように適切な関わりやコミュニケーションが必要です。多くの利用者のケアに入る関係上、一人一人の利用者との関わりが希薄になってしまうケースもあります。業務を効率化することで、利用者やご家族や医療機関とのコミュニケーションに時間を割くことができ、満足のいくケアを提供できます。
業務の効率化で多くの事業所が行っているのは、介護ソフトを利用した記録業務の電子化・効率化です。
当記事の筆者が働く事業所でも「ワイズマンの介護ソフト」が導入されており、最大限の時間を使って利用者と関われるようになっています。
働いている事業所で介護ソフトが導入されていない場合は、ぜひ担当者に導入の相談をしてみましょう。
介護ソフトの資料請求や、デモンストレーションをご希望の方はこちらから簡単にお問い合わせいただけます。
>>「訪問看護ソフト(訪問看護ステーション管理システムSP)」

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。