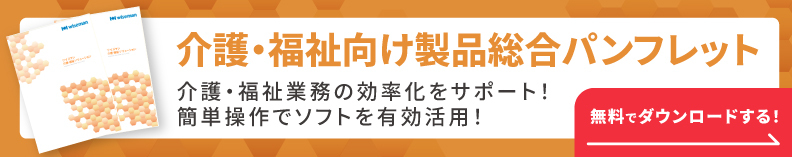看護の倫理問題とは?事例から学ぶ看護師のための倫理的思考
2025.04.18

看護師として、倫理的な問題にどう向き合うべきなのか、看護現場で働く者にとって大きな課題です。
看護の現場では、患者の生命や尊厳、プライバシーにかかわる重要な問題が日々発生します。これらはすべて看護師にとって倫理的な問題となり、適切な対応が求められます。しかし、具体的にどのように対処すれば良いのか明確な答えは用意されていません。
本記事では、看護の倫理問題について深く掘り下げていきます。看護倫理の4原則や具体的な事例を交えて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
目次
看護における倫理問題の基本とは
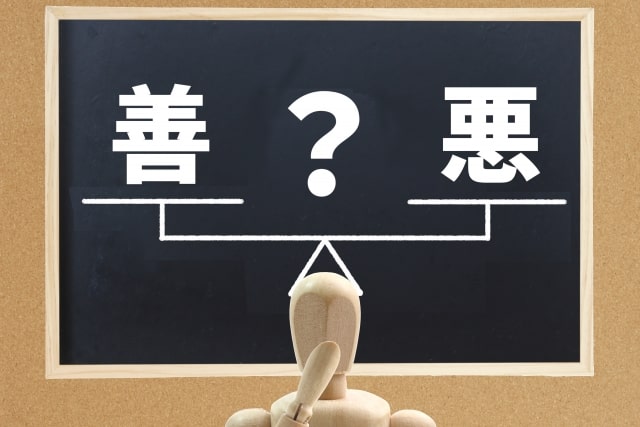
看護における倫理問題と向き合うために、下記の基本情報を確認しておきましょう。
- 看護の倫理問題とは
- 看護師が倫理問題を学ぶ必要性
- 倫理的感受性を高めるためのポイント
看護の倫理問題とは
看護の倫理問題とは、看護師が日々の業務において直面する、患者さんの権利、尊厳、幸福を尊重するための行動や判断に関する葛藤や課題のことです。
看護師は、患者さんの生命を預かる重大な責任を負っており、その過程で倫理的な決断を迫られる場面が数多く存在します。これらの問題は、単に法律や規則を守るだけでなく、患者さんにとって最善の利益となるように、倫理的な観点から深く考慮しなければなりません。
看護の倫理問題は、看護師個人の価値観や信念だけでなく、医療チーム全体での議論や倫理的な枠組みに基づいて解決を目指すことが大切です。
看護師が倫理問題を学ぶ必要性
看護師が倫理問題を学ぶことは、質の高い看護を提供するために必要不可欠です。倫理的な知識を持つことで、看護師は患者さんの権利を擁護し、倫理的なジレンマに直面した際に、より適切な判断ができます。
また、倫理的な視点を持つことは、患者さんとの信頼関係を築き、より良いケアを提供するための基盤として役立ちます。
看護倫理を学ぶ主なメリットは、以下のとおりです。
| メリット | 詳細 |
| 患者の権利擁護 | 患者さんの自己決定権を尊重し、十分な情報提供に基づいた同意を得るための知識とスキルを習得できる |
| 倫理的ジレンマへの対応力向上 | 複数の倫理的価値が対立する状況で、倫理的な原則に基づいて最適な解決策を見つけるための思考力を養える |
| チーム医療の質の向上 | 多職種との連携において、倫理的な視点から意見を述べ、より質の高い医療を提供できる |
| 法的リスクの軽減 | 医療関連法規を遵守し、倫理的な問題に適切に対応すれば、訴訟などの法的リスクを軽減できる |
倫理的感受性を高めるためのポイント
倫理的感受性とは、倫理的な問題に気づき、その重要性を理解する能力のことです。看護師が倫理的な問題に適切に対応するためには、倫理的感受性を高める必要があります。
倫理的感受性を高めるためには、日々の臨床経験を振り返り、倫理的な視点から考察する習慣を身につけることが大切です。
倫理的感受性を高めるための具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 倫理に関する学習
- 事例検討
- 倫理委員会への参加
- 自己の価値観の明確化
- 患者の視点の理解
日々の業務の中で倫理的な問題意識を持ち、積極的に学習や議論に参加して、より質の高い看護を提供しましょう。
看護倫理の4原則

看護倫理は、日々の看護実践における倫理的な判断を支える基盤となるものです。下記の医療倫理学に基づいた看護倫理の4原則を押さえて、適切な対応を行いましょう。
- 自律尊重
- 善行
- 無危害
- 公正
自律尊重
自律尊重とは、患者さんが自身の意思に基づいて自由に決定し、行動する権利を尊重することです。看護師は、患者さんが十分な情報に基づいて意思決定できるよう支援し、その決定を尊重する義務があります。
患者さんの自己決定権を尊重し、意向に沿った看護を提供することが重要です。
善行
善行とは、患者さんにとって最善となるように行動することです。看護師は、患者さんの幸福を追求し、苦痛を軽減するために、専門的な知識と技術を駆使して最善のケアを提供する必要があります。
ただし、善行は患者さんの価値観や意向を無視してはならず、自律尊重の原則とのバランスが重要です。
無危害
無危害とは、患者さんに危害を加えないことです。看護師は、意図的、非意図的を問わず、患者さんに不必要な苦痛や損害を与えないように努める必要があります。
医療行為には常にリスクが伴いますが、リスクを最小限に抑え、安全なケアを提供することが重要です。
公正
公正とは、すべての患者さんを平等に扱い、公平な医療を提供することです。看護師は、患者さんの社会経済的地位、人種、宗教、性的指向などに関わらず、必要な医療サービスを平等に提供する義務があります。
限られた医療資源を公平に分配することも、公正の原則に含まれます。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
看護現場でよくある倫理的問題と解決策

看護現場では、日々多くの倫理的な問題に直面します。看護現場でよくある倫理的問題は、次のとおりです。
| 倫理的問題 | 具体例 |
| 終末期医療における倫理的問題 | 延命治療、尊厳死 |
| 認知症患者への対応 | 意思決定能力の低下、虐待 |
| インフォームドコンセント | 患者への十分な説明と同意 |
| 医療資源の配分 | 限られた資源をどう分配するか |
特に頻繁に遭遇する倫理的問題を取り上げ、それぞれの問題に対する解決策を具体的に解説します。
終末期医療における倫理的問題:延命治療、尊厳死
終末期医療における倫理的問題は、患者の尊厳、自己決定権、医療者の倫理観が複雑に絡み合います。延命治療の選択、尊厳死の希望、疼痛管理など、看護師は患者と家族の意向を尊重しながら、最善のケアを提供しましょう。
問題点:
- 患者の意思決定能力が低下している場合、誰が患者の最善の利益を代弁するのか。
- 延命治療を続けることが、本当に患者のQOL(生活の質)を高めるのか。
- 尊厳死を希望する患者に対し、どのように寄り添い、支援するのか。
解決策:
- 多職種連携:医師、看護師、ソーシャルワーカー、倫理委員会などが連携し、患者の状況を総合的に評価します。
- 患者・家族との十分なコミュニケーション:患者の意思、価値観、希望を丁寧に聞き取り、共有します。
- 倫理的コンサルテーション:倫理的な問題について専門家の意見を求め、客観的な視点を取り入れます。
- アドバンス・ケア・プランニング(ACP):患者が意思決定能力のあるうちに、将来の医療やケアについて話し合い、文書化します。
認知症患者への対応:意思決定能力の低下、虐待
認知症患者への対応は、看護師にとって倫理的な課題が多い領域です。意思決定能力の低下した患者の権利擁護、BPSD(行動・心理症状)への対応、虐待の早期発見と防止など、多岐にわたる問題に直面します。
問題点:
- 認知症患者の意思決定能力をどのように評価するのか。
- 患者の行動制限は、どこまで許容されるのか。
- 虐待の兆候を早期に発見し、どのように対応するのか。
解決策:
- 意思決定支援:患者の残存能力を最大限に活かし、可能な限り自己決定を尊重します。
- 非薬物療法:BPSDに対して、環境調整、回想法、音楽療法など、薬物療法以外の方法を優先的に検討します。
- 多職種連携:医師、看護師、介護士、家族などが連携し、患者の状況を共有し、支援体制を構築します。
- 虐待防止:虐待のリスクが高い状況を把握し、早期介入を行います。
インフォームドコンセント:患者への十分な説明と同意
インフォームドコンセントは、患者が自身の治療について十分な情報に基づき、自らの意思で決定する権利を保障するものです。看護師は、患者が理解しやすい言葉で説明し、十分な時間をかけて同意を得る必要があります。
問題点:
- 患者が専門用語を理解できない場合、どのように説明すれば良いのか。
- 患者が治療のリスクを理解した上で、同意を拒否した場合、どのように対応するのか。
- 緊急時など、十分な説明時間が確保できない場合、どのように同意を得るのか。
解決策:
- 平易な言葉での説明:専門用語を避け、図やイラストなどを用いて、視覚的に理解を促します。
- 質問の機会の提供:患者が疑問や不安を自由に質問できる雰囲気を作り、丁寧に答えます。
- 同意の再確認:治療開始前にも、患者の意思を再確認し、同意を得ます。
- 記録:説明内容、患者の理解度、同意の有無などを、診療録に詳細に記録します。
医療資源の配分:限られた資源をどう分配するか
医療資源は有限であり、すべての患者に十分な資源を提供できるとは限りません。看護師は、公平性、効率性、倫理的妥当性を考慮し、限られた資源を適切に配分する必要があります。
問題点:
- 重症患者と軽症患者のどちらを優先すべきか。
- 高額な医療技術を、誰に提供すべきか。
- 緊急時、限られた医療資源をどのように分配するのか。
解決策:
- トリアージ:緊急度や重症度に応じて、患者の治療優先順位を決定します。
- ガイドラインの遵守:医療資源の配分に関するガイドラインを遵守し、客観的な基準に基づいて判断します。
- 倫理的議論:医療チーム内で、倫理的な問題について議論し、合意形成を図ります。
- 透明性の確保:医療資源の配分に関する決定プロセスを公開し、透明性を確保します。
倫理的ジレンマに陥ったときの考え方と対応

看護の倫理的問題に直面した際に、倫理的ジレンマに陥るケースがあります。倫理的ジレンマに陥ったときの考え方を確認して、適切な対応を心がけましょう。
看護倫理ジレンマとは?具体例で解説
看護倫理ジレンマとは、看護師が複数の倫理的原則の間で板挟みになり、どちらの行動を選択しても何らかの倫理的問題が生じる状況を指します。看護の現場では、患者さんの権利、幸福、そして専門職としての責任の間で葛藤が生じることがあります。このような状況下で、看護師は最善の決断をするために、倫理的な思考プロセスが必要です。
具体的な例として、終末期医療における延命治療の選択が挙げられます。患者本人が延命を望まない場合でも、家族が延命を強く希望する場合、看護師は患者の自律尊重の原則と、家族の意向を尊重する気持ちの間で葛藤します。
また、医療資源が限られている状況下で、どの患者に優先的に資源を配分するかという問題も、倫理的ジレンマの一例です。患者の状態、年齢、予後などを考慮し、公平な判断を下さなければなりません。
倫理的ジレンマは、看護師にとって精神的な負担が大きく、燃え尽き症候群の原因となるため、適切に対応するための知識とスキルを身につけることが大切です。
倫理的ジレンマに陥ったときの考え方:倫理的意思決定モデル
倫理的ジレンマに直面した際には、客観的かつ体系的に問題を分析し、意思決定を行うための倫理的意思決定モデルを活用することが有効です。倫理的意思決定モデルは、以下のステップで構成されます。
- 状況の明確化:
- 情報の収集
- 選択肢の検討
- 倫理原則の適用
- 意思決定
- 行動の実行と評価
倫理的ジレンマへの対応:多職種連携、専門家への相談
倫理的ジレンマに陥った場合、一人で悩まずに、多職種連携によるサポート体制を活用することが大切です。医師、看護師、ソーシャルワーカー、臨床倫理の専門家など、さまざまな専門家と意見交換を行えば、多角的な視点から問題を検討できます。
また、倫理委員会や倫理コンサルテーションなどの制度を利用することも有効です。
多職種連携においては、それぞれの専門分野の知識や経験を共有し、患者にとって最善の利益となる意思決定を目指します。看護師は、患者の代弁者として、患者の意向や価値観を尊重し、倫理的な視点から意見を述べましょう。
倫理的ジレンマは、正解が一つとは限りません。重要なポイントは、関係者全員が納得できるプロセスを経て、最善の結論を導き出すことです。
看護師が知っておくべき倫理的問題を抑制するコツ

看護師として日々の業務を行う中で、倫理的な問題への直面は避けられません。患者さんの権利を守り、安全な医療を提供するために、倫理的問題を未然に防ぐための知識とスキルを身につけましょう。
患者の権利擁護:患者の尊厳を守る
患者の権利擁護は、看護師のもっとも重要な役割の一つです。患者は、人として尊重され、平等な医療を受ける権利を持っています。具体的には、以下のような権利があります。
- 自己決定権
- 知る権利
- プライバシーの権利
- 尊厳を保持される権利
これらの権利を尊重し、擁護するために、看護師は常に患者の立場に立ち、患者の意思を尊重したケアを提供してください。
守秘義務:患者情報の保護
看護師は、業務上知り得た患者さんの個人情報や診療情報を厳重に保護する義務があります。患者情報の保護は、患者さんとの信頼関係を築き、安心して医療を受けていただくために必要不可欠です。守秘義務を遵守するために、以下の点に注意しましょう。
- 患者さんの情報を、許可なく第三者に開示しない
- 患者さんの情報を、業務に必要な範囲を超えて利用しない
- 患者さんの情報を、安全な方法で管理する(電子カルテの適切な管理、書類の施錠など)
- 患者さんの情報について、SNSやインターネット上に書き込まない
日々の業務の中で、常に守秘義務を意識し、適切な情報管理を心がけましょう。
専門職としての責任:自己研鑽、倫理綱領の遵守
看護師は、常に最新の知識や技術を習得し、自己研鑽に励みながら看護倫理綱領を遵守する必要があります。看護倫理綱領とは、看護師が業務を行う上で守るべき倫理的な原則や行動規範をまとめたものです。
具体的には、日本看護協会が定める「看護者の倫理綱領」などがあります。
- 人権の尊重
- 安全な看護
- 自己決定の尊重
- プライバシーの保護
- 専門性の向上
- 他職種との連携
高齢者看護における倫理的問題:事例で学ぶ

高齢者看護の現場では、特有の倫理的問題に直面することが多くあります。高齢者の尊厳を守り、最善のケアを提供するためには、これらの問題に対する深い理解と倫理的な判断が不可欠です。
高齢者看護における倫理的問題について、具体的な事例を通して学びましょう。
認知症患者への対応:意思決定支援、BPSDへの対応
認知症患者の看護では、患者の意思決定能力が低下している場合に、どのように患者の意向を尊重し、最善の利益を追求するかが重要な倫理的課題となります。また、BPSD(行動・心理症状)への対応も、患者の尊厳を損なわないように配慮する必要があります。
| 倫理的問題 | 事例 | 倫理的配慮 |
| 意思決定能力の低下 | 認知症の進行により、治療方針の決定が困難な患者に対し、家族が患者の意向を無視した決定をしようとする。 | 患者の過去の意向や価値観を尊重し、可能な限り患者本人の意思を確認する。家族への十分な説明を行い、患者の最善の利益を考慮した合意形成を目指す。 |
| BPSDへの対応 | 興奮や暴力行為のある認知症患者に対し、安易に身体拘束を行う。 | 身体拘束は、患者の自由を著しく制限する行為であり、原則として禁止される。BPSDの原因を特定し、非薬物療法を中心に、患者の安全を確保しつつ、尊厳を尊重したケアを提供する。 |
終末期医療:QOLの維持、看取りのケア
高齢者の終末期医療においては、延命治療の選択、苦痛の緩和、尊厳を保った看取りなど、多くの倫理的課題が存在します。患者のQOL(生活の質)を最大限に尊重し、患者や家族の意向に沿ったケアを提供することが重要です。
| 倫理的問題 | 事例 | 倫理的配慮 |
| 延命治療の選択 | 回復の見込みがない高齢患者に対し、家族が延命治療を強く希望する。 | 患者本人の意思が不明な場合、家族と十分に話し合い、患者の過去の価値観やQOLを考慮した上で、最善の利益となる治療方針を決定する。 |
| 苦痛の緩和 | 終末期の患者が強い苦痛を訴えるが、鎮痛薬の使用による意識レベルの低下を懸念する家族がいる。 | 患者の苦痛を緩和することが最優先であることを家族に説明し、十分な情報提供と同意を得た上で、適切な鎮痛療法を行う。 |
| 尊厳を保った看取り | 病院での看取りを希望しない患者に対し、医療スタッフが病院での看取りを強要する。 | 患者の意思を尊重し、可能な限り患者が希望する場所で、尊厳を保った看取りができるように支援する。 |
高齢者虐待:早期発見と対応
高齢者虐待は、高齢者の人権を侵害する重大な倫理的問題です。虐待が疑われる場合は、速やかに医療機関や関係機関に相談し、高齢者の安全を確保する必要があります。
| 倫理的問題 | 事例 | 倫理的配慮 |
| 身体的虐待 | 高齢者の体に不自然な傷やアザがある。 | 高齢者の安全を最優先に考え、速やかに医療機関や関係機関に相談する。 |
| 心理的虐待 | 家族が高齢者に対し、侮辱的な言葉を浴びせたり、無視したりする。 | 高齢者の精神的な苦痛を軽減するために、心理的なサポートを行うとともに、家族への指導や支援を行う。 |
| 経済的虐待 | 家族が高齢者の年金や財産を不正に使用する。 | 高齢者の経済的な自立を支援するために、成年後見制度の利用などを検討する。 |

看護の倫理問題とは、医療現場において患者・家族・医療者それぞれの価値観が交差する中で、「何が患者にとって最善か」を考える実践的課題です。患者の意思が確認できない場合や、本人と家族の意向が一致しない場面など、現実の看護では正解のない選択を迫られることが少なくありません。そのような場面では、患者の尊厳や自己決定の尊重、公正性、利益と不利益のバランスといった倫理原則をふまえ、看護師が状況に応じて柔軟に判断し、行動することが求められます。倫理的思考とは、「問い続ける力」であり、チームでの共有や対話を通じて深めていくべきものです。事例を通して自らの価値観を見直し、「なぜ迷うのか」「どのような視点があるか」を考えることは、倫理的感受性と判断力を高め、よりよい看護の実践に繋がります。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
看護現場で働くために倫理的問題について理解を深めよう

看護の倫理的問題は答えのない問いです。患者さんや家族の立場になり、それぞれの希望を叶える倫理的な思考が求められます。
自分一人で倫理的問題を解決できない場合は、専門家との意見相談や事例を参考に、最適な答えを導き出してください。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。