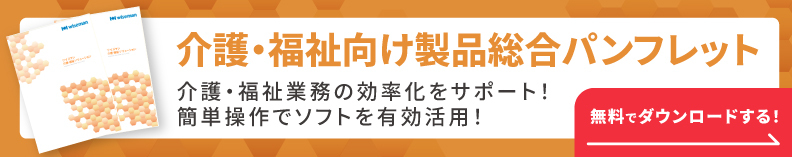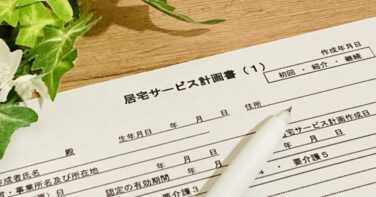居宅介護支援(ケアマネ)のICT活用|メリットや介護ソフト選びのポイント
2023.02.15

介護の仕事は利用者のケアを行うことだけではありません。
利用者や、その家族に適切なケアプランを提供する居宅介護支援(ケアマネ)も重要な仕事です。
居宅介護支援は、利用者のケアプランを作成したり、ほかの事業所と情報の連携を図ったり、実績をもとに介護給付費請求を行ったりと、膨大な情報を取り扱います。
しかし、マンパワーによる作業量には限界があるため、ICTの活用が検討されています。そこで居宅介護支援でICTを活用することで、どのようなメリットがあるのかについて解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは日々の煩雑な業務にお困りの方に向けて「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料配布しています。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は是非ご活用ください。
目次
介護現場で進むICT導入

本章では、介護現場でICT導入が進められている理由や背景について考察します。
ICTとは
ICTとは、「Information and Communication Technology」の略称で、日本語では情報通信技術と訳されます。
ICTにはパソコンやスマートフォン、タブレット端末を使ったメールやチャット、SNS、ECサイト取引などがあり、私たちの身近な生活に広がっています。介護現場においても業務の効率化を目的として、ICTを導入する事業所が増えてきました。
本記事では、介護現場の中でも居宅介護支援におけるICT活用について取り上げます。
居宅介護支援のICT活用とは
近年、居宅介護支援の現場でICTを取り入れる動きがあります。ICT導入の活発化において、令和6年度の介護報酬改定の影響は無視できません。
介護報酬改定により、ICTを活用している居宅介護支援事業所ではケアプラン連携データシステムの活用、かつ事務職員の配置している場合、居宅介護支援費の取扱件数を以下のように変更することが決定されました。
【基準】
“指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合は、利用者の数が49またはその端数を増すごとに一とする。”
出典:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
【報酬】
| 居宅介護支援費(Ⅱ) | 取扱件数の下限を45件未満を50件未満に変更 |
| 居宅介護支援費(Ⅱ)(ii) | 取扱件数の下限を45件以上60件未満を50件以上60未満に変更 |
上記の変更は、居宅介護支援サービスの質を維持したうえで、業務効率化を促進するために実施されています。
居宅介護支援における基本報酬に影響が出る改定となったため、ICTの導入は事業所にとって重要な施策となりました。
参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
厚生労働省によるICTの利用促進
高齢化社会の進行に加え、少子化による介護人材不足が懸念される中、介護人材の定着化と業務負担の軽減は急務です。そのため、ICTの活用による業務効率化は欠かせません。
そこで厚生労働省は、ICT導入支援事業として補助金を設けることで介護現場でのICT利用の促進を図っています。
なお、ICT支援事業を利用するには、要件を満たす必要があります。例えば、介護ソフトのベンダーが異なっても、記録業務・情報共有業務・請求業務が一気通貫できることなどが挙げられます。
居宅介護支援(ケアマネ)でICTを活用するメリット

ICT活用のメリットと聞くと、業務の効率化や生産性の向上を頭に思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
ここでは、居宅介護支援におけるICT活用のメリットについて解説します。
業務効率化
ICT導入による最大のメリットは、やはり業務効率化です。
従来のアナログな方式の場合、手書きによる記入や書類の保管など、さまざまな業務が負担になりがちでした。
特に居宅介護支援は事務作業が中心であるため、アナログな作業のままではスタッフへの負担が増えるだけでなく、人件費の増加を招きます。
しかし、ICT導入によって書類を電子化すれば、手書きによる記入や書類の保管などに手間がかかりません。
また、スマートフォンやタブレット端末を利用することにより、介護記録の作成から請求業務までまとめて作業できます。
訪問介護職員にとっても居宅介護支援事業所にとっても大幅な業務時間の短縮につながります。
スタッフ間の円滑な情報共有
ICT機器を使用することにより、全スタッフに対するスムーズな情報共有が可能です。
情報を電子化すればリアルタイムで情報共有できるので、緊急事態が発生しても、スタッフが状況を把握しやすくなります。
また、手書きのような記入ミスも発生しにくくなるため、情報の正確性も向上します。
出勤していないスタッフへの情報連携が取れるうえに、履歴が残ることで「言った、言わない」のトラブルを防げる点も大きなメリットです。
印刷費などの削減
ICT機器でデータ管理を行うことによって、ペーパーレス化が可能となり、トナーや用紙代など印刷にかかるコストの削減につながります。
従来の紙媒体の書類は、作成に時間がかかるうえに、保管する際にスペースが圧迫されるなど、管理面にもデメリットがありました。
しかし、ICTによって書類を電子化すれば、保管用のスペースを設ける必要がなくなり、保管コストも削減できます。
加えて紙媒体には経年劣化の問題がありますが、電子化すればメンテナンスは不要です。
ペーパーレスは業務効率化を実現するうえで、達成すべき目標のひとつです。
特に1人ケアマネのような小規模の居宅介護支援事業所の場合、紙媒体の書類では作成や保管にかなり手間がかかります。
無駄な作業やコストを減らすためにも、ICTによるペーパーレス化は積極的に取り組みましょう。
セキュリティの強化
紙媒体でデータを取り扱う場合、紛失・消失などによる情報漏洩やデータ改ざんのリスクを伴います。とりわけ居宅介護支援事業所で取り扱う書類には、利用者に関する個人情報が含まれるため厳重な管理が必要です。
ICT機器やクラウドを活用してデータ保存しておけば、情報漏洩のリスクが軽減され、セキュリティの強化につながります。
さらにパスワードやアクセス権限を厳重に管理することで、適切なデータ運用が可能です。
しかし、ICTを導入しても、セキュリティが万全なわけではありません。
ICTを導入する際は、セキュリティ性に優れたシステムやソフトを導入し、スタッフのミスで情報漏洩が発生することがないよう、運用面でも細心の注意を払いましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは日々の煩雑な業務にお困りの方に向けて、「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
居宅介護支援(ケアマネ)でICTを導入する流れ

ICT導入支援事業に交付申請を行うためには、都道府県へICT機器や介護ソフト導入に関する計画を提出することが義務付けられています。
しかし、実際にどうやって導入を進めれば良いかわからないこともあるのではないでしょうか。ここでは居宅介護支援におけるICT導入の流れについて解説します。
ICT機器・ソフトウェアの導入計画を立てる
まず、事業所にICT機器・ソフトウェアを導入する目的と導入時期を明確にします。
ICTの導入は、ただ機器やソフトウェアを購入することではありません。
ICT化によって事業所の課題を解決し、より良いサービスの提供を実現することが、ICTを導入する目的です。
そのため、事業所の課題を洗い出し、ICTを導入する目的を明確にしましょう。
「この業務を効率化したい」「よりスムーズにサービスを提供したい」など、目的が明確になれば、導入すべきツールを決定しやすくなります。
また、無駄なICT機器やソフトウェアを導入する必要がなくなるため、コストも抑えられます。
導入するICT機器・ソフトウェアを選定する
次に事業所の目的に最適なICT機器・ソフトウェアを導入するため、製品機能・価格・効果・サポート体制などを総合的に比較したうえで選定しましょう。
ICT機器やソフトウェアは、多角的な視点で選定するようにしましょう。
例えば、価格を重視するあまり、安価なツールを選んでも、必要な機能が搭載されておらず、業務を効率化できないリスクがあります。
また、ITスキルが低いスタッフが多い状況で高性能なツールを選ぶと、使いこなせず、持て余すことになりかねません。
現場で運用することを見据え、さまざまな観点から適切なICT機器・ソフトウェアを吟味しましょう。
ICTの導入に伴い業務内容の変更箇所を確認する
ICTの導入に伴い、利用者情報の管理方法や介護記録の入力方法などの業務上の変更点について検討・整備を行います。
事業所の状況によっては、ICTの導入で業務プロセスが大きく変化することが想定されます。
しかし、業務プロセスが変更されると、スタッフがついていけず、かえって現場に混乱をもたらす事態になりかねません。
ICTを導入する際は、業務内容の変更箇所を確認し、現場にも共有するように心がけましょう。
前もって変更箇所を把握しておけば、スタッフがスムーズにICTを受け入れやすくなります。
職員に使い方に関する周知・研修を行う
ICT機器の使用方法・システムを確認し、デモ操作を行いながら一連の実績入力や記録方法の確認を行います。操作上で何か不具合があれば、職員からのフィードバックを導入業者に伝えて対応を依頼しましょう。
職員に対して定期的に研修を行うことにより、ICT機器に関する知識習得や操作の習熟が実現しやすくなります。
また、ICT機器やソフトウェアを提供するベンダーによっては、ツールの使用方法の説明やサポートをしてくれる場合があります。
ITスキルが低いスタッフにも丁寧に説明してくれるので、積極的に活用しましょう。
ICTを導入
ICTを導入した時点で終わりではなく、導入後の効果測定を実施して課題の抽出や対策を検討します。
ICTの導入によって、業務負担の軽減や記録時間の短縮がどの程度達成されたのか検証を行います。
検証の過程で新たな課題が見つかったり、ICTの効果が発揮されていないことがわかったりした際は、早急に対応策を検討しましょう。
ICT導入に満足せず、PDCAサイクルを回して改善を繰り返すことで、さらなる業務の改善が実現できます。
居宅介護支援ソフトを選ぶポイント

連絡機関との調整・アセスメント・ケアプランなどの帳票作成がメイン業務となるケアマネジャーにとって、介護ソフトは欠かせません。ICTを推進するうえでも居宅介護支援ソフトの選定は非常に重要です。
ここでは居宅介護支援ソフトを選ぶ際のポイントをいくつか挙げるので、参考にしてください。
他事業所との連携
居宅介護支援では訪問介護をはじめ、訪問看護や訪問リハビリテーション、福祉用具レンタルなど他事業所と情報共有を取る場面が多くみられます。
その点、「ワイズマンの介護ソフト」は他事業所・法人内・医療と介護事業所間での情報共有が可能です。
また、ワイズマンの居宅介護支援向けの介護ソフトは、ケアプランの管理や利用者の情報管理など、居宅介護支援を実施するうえで必要な機能が搭載されています。
そのため、業務効率化だけでなく、サービスの質のさらなる向上も期待できます。
さらにワイズマンは運用にあたって、手厚い運用支援を実施する点も特徴です。
初めてICTを導入する事業所でも、丁寧にサポートしてくれるため、スムーズな導入が実現できます。
セキュリティ
居宅介護支援では大量の個人情報を管理する必要があるため、セキュリティには細心の注意を払わなければなりません。そのため、セキュリティに適切な対策を講じているソフトウェアを選ぶ必要があります。
加えてログインパスワードを定期的に変更したり、机の周りにメモを残したりしないなど、運用面での配慮も不可欠です。
ICTを適切に運用するうえで、スタッフのITリテラシー向上は必須です。
定期的に研修を実施するなど、スタッフの教育も積極的に実施しましょう。
サポート体制
居宅介護支援ソフトを選ぶうえで、サポート体制は重視すべきポイントです。
ICTは便利な反面、システム障害などのトラブルが起こると業務が停止するリスクがあります。
そのため、トラブルが発生してもスピーディーに事態を解決できる体制作りは欠かせません。
不明点や不具合が生じた際に備えて、迅速な対応が可能なベンダーを選びましょう。特に土日祝日のサポートの有無や平日の営業時間については、十分確認しておくことが重要です。
また、スタッフには居宅介護支援ソフトの操作方法に加え、トラブルが起こった際の対応方法も共有しておきましょう。
ベンダーからのサポートを受ける前に、スタッフで適切な対応ができる体制を整えておけば、トラブルを解決しやすくなります。
業務や利用者への影響も抑えられるので、ICTの導入と並列して、必ずマニュアルを作成しましょう。
制度改正および報酬改定の対応
制度改正や介護報酬改定に対応していることも、介護ソフトを選定するうえで重要なポイントとなります。万が一、改正や改定に対応していない介護ソフトを使用した場合、介護給付費請求の際、誤って処理される恐れがあるためです。
制度改正や介護報酬改定に対応しているか不明な場合は、導入前にベンダー担当者に確認しておきましょう。
なお、最近は制度改正や介護報酬改定があっても、アップデートするだけで自動的に対応できる製品が居宅介護支援ソフトが増えています。
このようなタイプの居宅介護支援ソフトなら、書類の書式変更や業務プロセスの変更への対応もスムーズにできます。

居宅介護支援(ケアマネジメント)の現場では、膨大な情報管理と事務作業が求められます。近年、ICT(情報通信技術)の活用が進み、業務の効率化や情報共有の迅速化が図られています。特に、令和6年度の介護報酬改定では、ICT活用を前提とした基準が見直され、導入の必要性が高まっています。
ICTを導入することで、ケアプランの作成・管理、記録業務、請求処理の電子化が可能となり、作業負担の軽減が期待されます。また、クラウドシステムを利用することで、他事業所とのリアルタイムな情報共有が可能となり、より質の高いケアの提供につながります。
ただし、導入にあたってはセキュリティ対策やスタッフ教育が不可欠です。適切な介護ソフトの選定と継続的な運用改善が、ICT活用の成功の鍵となります。今後の介護業界において、ICTの活用は不可避の課題となり、積極的な取り組みが求められます。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は是非ご活用ください。
居宅介護支援においてICT化は重要な取り組み

居宅介護支援において、ICT導入によって得られる効果は業務の効率化だけでなく、サービスの品質向上や利用者満足度の向上にも影響します。しかし、居宅介護支援ではICT化がほとんど進んでおらず、紙媒体によるやりとりをいまだに続けている事業所が少なくありません。
コストやセキュリティの観点から考えても、ICT導入によって得られるメリットは非常に大きいものです。ICTの導入に合わせて操作や機能に関して、定期的に職員向けの研修を実施することも必要です。
もし介護ソフトを導入するなら、ぜひ「ワイズマンの介護ソフト」をご検討ください。
ワイズマンの居宅介護支援ソフトなら、アセスメントからモニタリング・評価までの一連の流れをスムーズに支援できるため、業務効率化につながります。
もし、今働いている事業所に介護ソフトが導入されていないなら、業務効率化を図れるように担当者に導入を相談してみてください。これから居宅介護支援のケアマネジャーとして働くのであれば、事業所に介護ソフトが導入されているかチェックされることをおすすめします。
介護ソフトの資料請求や、デモンストレーションをご希望の方はこちらから簡単にお問い合わせいただけます。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。