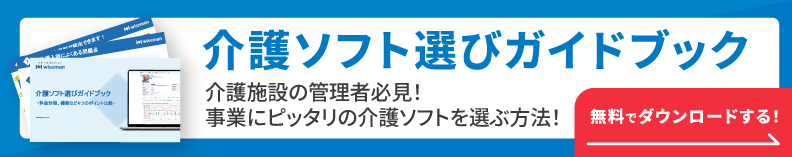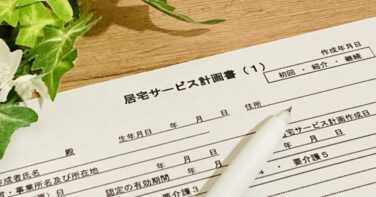居宅介護支援の初回加算とは?算定要件やポイントを解説【2025最新版】
2023.02.27

居宅介護支援の初回加算は、新規の利用者に対する居宅サービス計画や介護予防サービス計画作成を評価する加算のことです。初回加算ができる場合とできない場合の違いや、どういうときに新規になるのか分からないなど、疑問を持っている担当者もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では初回加算の算定要件やポイントについて、詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
なお、株式会社ワイズマンでは介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて「介護ソフト選びガイドブック」を無料配布しています。
介護ソフトの導入時によくある問題と対策についても記載していますので是非ご活用ください。
居宅介護支援の初回加算とは?

居宅介護支援事業所が、利用者と初めて行うサービス計画の作成を評価する加算のことを「初回加算」といいます。居宅介護支援と介護予防支援において加算されます。
利用者と初めてかかわる際は、まず担当のケアマネジャーが利用者宅を訪問し、以下のような点についてヒアリングを行います。
- 利用者の心身状態
- 日常生活の様子
- 利用者本人やご家族の希望
利用者の日常生活や身の回りに関するさまざまな情報を収集し、利用者がその方らしく生活できるよう、ケアプランを作成します。また、ケアマネジャーは介護サ―ビス事業所とも連携しながら、調整役としても活躍します。
このように、初回はさまざまな情報収集ややり取りが必要です。それらを居宅介護支援事業所側の「手間」ととらえ、加算を行うことにしています。この記事では、居宅介護支援に特化して解説をします。
居宅介護支援事業所では、さまざまな加算を申請できますが、それぞれの要件を正しく理解し、適切に対応する必要があります。特に、初回加算は利用者との初回対応時に発生するため、算定条件や申請時のポイントを押さえておかなければなりません。
詳細な要件や適用のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
居宅介護支援における初回加算の単位数
初回加算は、新規にケアプランを作成する利用者に対して適用される加算です。
この加算は、ケアマネジャーが初回の対応で行う情報収集や調整の手間を評価するために設けられています。
単位数の詳細は、以下のとおりです。
- 居宅介護支援費:300単位/月
- 介護予防支援費:300単位/月
介護報酬の算定は、この単位を基準に行われ、地域ごとの基準に応じて単価が異なります。また、単位数は3年に一度見直しが行われるため、最新の改定内容を確認しましょう。
初回加算を算定するには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 新規で居宅サービス計画を作成する場合
- 要支援者が要介護認定を受けた場合
- 要介護状態区分が2区分以上変更された場合
- 運営基準減算に該当していないこと
上記の要件を満たしていれば、居宅介護支援事業所は初回加算を適用できます。特に、新規の利用者対応では、適切な情報収集やケアプランの作成が求められるため、算定条件を正しく理解し、適用漏れのないように注意しましょう。
居宅介護支援における初回加算の算定要件
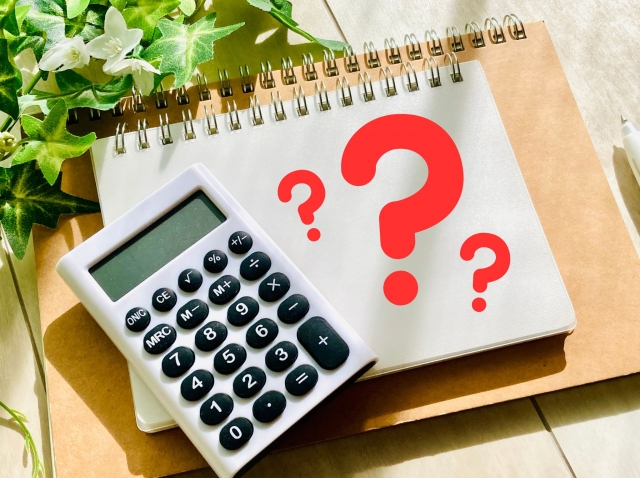
居宅介護支援において、初回加算をするための4つの要件について解説します。利用者の身体状態が変化すると新たに初回加算ができる場合もあります。一つひとつの要件について詳しく見ていきましょう。
新規に居宅サービス計画を作成する
新規に居宅サービス計画を作成すると、初回加算ができます。新規とは、過去2ヵ月以上に渡って居宅支援サービスの提供がされておらず、居宅介護支援費が算定されていない利用者に対して、ケアプランの作成を行った場合をいいます。
この場合、実際に契約をしているかどうかは関係ありません。前回契約をしていたとしても、2ヵ月以上が経過していれば、再度ケアプランの作成時に算定ができるということです。
要支援者が要介護認定を受けた際に居宅サービス計画を作成する
要支援者が要介護認定を受けて居宅サービス計画を作成すると、算定が可能となります。
要介護認定は介護サービスの必要度を表しています。介護サービスの必要度は、コンピュータによる一次判定と学識経験者による二次判定で決定されます。コンピュータによる一次判定では、5分野(直接生活介助・間接生活介助・BPSD関連行為・機能訓練関連行為・医療関連行為)について推計されます。そのうえで、要介護認定等基準時間が算出された結果と認知症加算が合計され、要支援1~要介護5が判定されるのです。
一方、要介護者が要支援者に変更となった場合でも、初回加算が算定可能です。この場合はこれまでケアプランの作成を担っていた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターの委託で新規に予防ケアプランを作成するケースでも算定要件を満たします。
要支援から要介護へあるいは要介護から要支援へ変わった場合は、新しいケアプランを作る必要があります。その際には、あらためて利用者の身体状況や日常生活に関する情報の取得、サービス事業所との調整が必要です。それを新たな「手間」とみなすため初回加算が算定できるのです。
なお、株式会社ワイズマンではすでに介護ソフトを導入しているが、介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて、「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。ダウンロードしてご活用ください。
要介護状態区分が2区分以上変更された際に居宅サービス計画を作成する
要介護状態区分が2区分以上変更となり、居宅サービス計画をあらためて作成した場合も、初回加算の要件を満たします。要介護(要支援)状態区分と心身状態の具体例は以下の表の通りです。
| 要介護(要支援)状態区分 | 心身状態の具体例 |
| 要支援1 | 家事、身支度などで支援を要する |
| 要支援2 | 家事、身支度に加えて、入浴や排せつにおいても支援を要する |
| 要介護1 | 入浴、排せつ、身だしなみ、衣服の着脱などで一部介護を要する |
| 要介護2 | 入浴、排せつ、身だしなみなどで一部介助または全介助を要する |
| 要介護3 | 入浴、排せつ、身だしなみ、衣服の着脱などで全介助を要する |
| 要介護4 | 入浴、排せつ、身だしなみ、衣服の着脱などの全般において全介助を要する |
| 要介護5 | 生活全般において、全面的な介助を要する |
この表からも分かるように、要介護状態区分が2区分以上変わると、心身状態も大きく変わります。それによってサービス計画にも大きな変更が予想できるため、初回加算が算定できるのです。
例えば、要介護2から要介護5といったように介護度が重くなる場合だけでなく、要介護3から要介護1のように軽くなる場合においても算定が可能です。
2区分以上の変更があった場合の初回加算の適用例
要介護状態が2区分以上変わると、心身の状態も大きく変化するため、新たに居宅サービス計画を作成する必要があります。そのため、初回加算の対象となります。
介護度が大幅に変わることで、必要な介護サービスや支援内容が根本的に変わるためです。
利用者の生活環境や支援ニーズが大きく変わる場合には、ケアマネジャーが利用者の生活状況や支援ニーズを確認し、新しいケアプランを作成する必要があります。
具体的には、以下のような例があります。
- 要支援2 → 要介護2(軽度な支援中心の生活から、身体介護が必要な状態へ移行する場合)
- 要介護1 → 要介護3(部分的な介助で生活できていた状態から、全介助が必要になる場合)
- 要介護4 → 要介護2(心身機能の回復により、介護度が軽減された場合)
上記のように、利用者の生活状況や必要な介護サービスが大きく変化する場合には、初回加算を適用できます。
加算要件を満たしているかどうか、事業所ごとに確認しながら適用漏れのないようにしましょう。
2区分以上の変更があっても初回加算が算定できないケース
要介護状態区分が2区分以上変わっても、すべてのケースで初回加算が適用されるわけではありません。特定の条件を満たさない場合は、加算の対象外となることに注意が必要です。
居宅サービス計画の作成が「新規」とみなされる条件を満たしていない場合、初回加算は適用されません。
他の加算との併用が認められていないケースや、一定期間内にサービス提供が継続されている場合も、算定不可となります。
具体的には、以下のような場合には適用されません。
- 要支援 → 要介護 → 要支援(途中で支援事業所の登録がない場合、再度初回加算は算定不可)
- 要支援 → 非該当 → 要支援(一時的に非該当になった場合は、新規作成とはみなされず算定不可)
- 運営基準減算(50/100)の適用中(運営基準減算が適用されている期間は初回加算を請求できない)
- 退院・退所加算と併用する場合(退院・退所加算を適用した場合、初回加算との同時算定はできない)
初回加算を適用するためには、単に介護度が変わるだけでなく、新たなケアプランの作成と認められる条件を満たすことが必要です。
算定が可能かどうかは、自治体のルールや国保連の指導内容を確認しながら、適切に判断するようにしましょう。
運営基準減算に該当しない
運営基準減算に該当しない条件下でも、初回加算は算定できます。運営基準減算とは、ケアプラン作成等についての運営基準を満たしていないときに適用される項目です。所定単位数の100分の50相当が減算され、2ヵ月以上に渡って運営基準減算が継続していると、所定単位は算定できません。
居宅介護支援における減算要件は以下の通りです。この要件に該当しないようにすれば、初回加算が算定できます。
(1)居宅サービス計画の新規作成・変更にかかる減算条件
- 介護支援専門員が、利用者宅を訪問し本人やそのご家族と面接していない
- 介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない
- 介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容を利用者とそのご家族に説明し、文書によって利用者の同意を得たうえで、その計画を利用者と担当者に交付していない
(2) 介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときの減算
- 新規に居宅サービス計画を作成した場合
- 利用者が要介護認定を受けており、要介護更新認定を受けた場合
- 利用者が要介護認定を受けており、要介護状態区分の変更について認定を受けた場合
(3) 居宅サービス計画作成後、計画実施についての把握(モニタリング)状況による減算
- 介護支援専門員が、1ヵ月の間に利用者宅を訪問して面接を行なっていない場合
- 介護支援専門員が、1ヵ月以上に渡りモニタリングの結果を記録していない場合
上記の場合の減算される期間は、減算事由の発生した月から、当該事由が解消されるまでに至った月の前月までです。
居宅介護支援における初回加算のポイント

居宅介護支援における初回加算にはいくつかの条件があり、場合によっては初回加算ができなくなるなど、注意すべき点もあります。3つのポイントを解説します。
報酬請求が初めての場合は算定できる
報酬請求が初めてであれば算定できます。たとえ契約をしていても、これまでに一度も報酬請求をしなかった場合は新規として扱われ、初回加算を算定できます。
また、転居等の理由により介護予防支援事業所が変更になった場合においても、初回加算の算定ができます。転居先の介護予防支援事業にとってみれば、その利用者を初めて担当することになるからです。
一方、地域包括支援センターの委任を受けている居宅介護支援事業所が変更になった場合は、初回加算が行われません。アセスメントを行う地域包括支援センターにとっては、居宅介護支援事業所が変更になったとしても、その利用者を初めて担当するわけではないからです。
このように初回加算は、新たにケアプラン等を作成する際に実施するアセスメント等に対する評価なのです。
退院・退所加算とあわせて算定はできない
初回加算は、退院・退所加算と合わせた算定はできません。
退院・退所加算とは、医療連携の強化・推進を目的として行われるものです。病院や介護保険施設等からの退院・退所にあたって情報共有を行ったことを評価します。
情報共有とは、利用者の退院・退所の際に病院・診療所・介護保険施設などの施設職員と面談して利用者に関する必要な情報を提供してもらい、ケアプラン作成やサービス利用の調整を行うことです。
同一の退院・退所に対して一回を限度に、医療連携の方法や回数に応じた区分について加算が算定できます。
退院・退所加算ができる条件は以下の通りです。
- 退院または退所をし、自宅で居宅サービスあるいは地域密着サービスを利用する場合
- 入院あるいは入所期間中に行った連携方法や回数に応じて一回まで算定できる
- 利用者が退院あるいは退所してから7日以内に情報を得ている
- 入院中にカンファレンスに参加した場合には、その日時、場所、内容、出席者などをケアプランに記録する
以上の条件を満たさずに退院・退所加算をする場合は、初回加算ができないので注意が必要です。
再契約の場合は算定できない
利用者に対して初めて対応をする際の手間などを評価するのが、初回加算の本来の趣旨です。そのため再契約をした場合のように、契約が実質的に継続していると判断できる場合には算定できません。
一定の空白期間を置いたあとに再契約をした場合も同様です。

居宅介護支援の初回加算は、新規のケアプラン作成時に適用される重要な加算ですが、その要件を正しく理解することが必要です。「新規」といっても、単に新しく契約した場合だけでなく、「要支援から要介護への変更」や「要介護状態区分が2区分以上変化した場合」など、具体的な要件を満たしていることが算定の条件となります。
初回加算は適用できるケースとできないケースが明確に分かれており、誤って算定しないよう注意が必要です。また、運営基準減算が適用されている期間や、退院・退所加算との併用は認められていないため、細かなルールの確認を怠らないことが大切です。
ケアマネジャーとして、正しい算定ルールを理解し、適切に運用することは、利用者への質の高いサービス提供にもつながります。適用漏れがないよう、定期的に最新の介護報酬改定を確認し、制度の正確な運用を心がけましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。
すでに介護ソフトを導入していている方も、介護ソフトの入れ替えを検討している方も、自身に最適なプロダクトを選ぶために重要な4つのポイントを解説していますので是非ご活用ください。
まとめ|居宅介護支援の初回加算を正しく理解し、適切に算定しよう
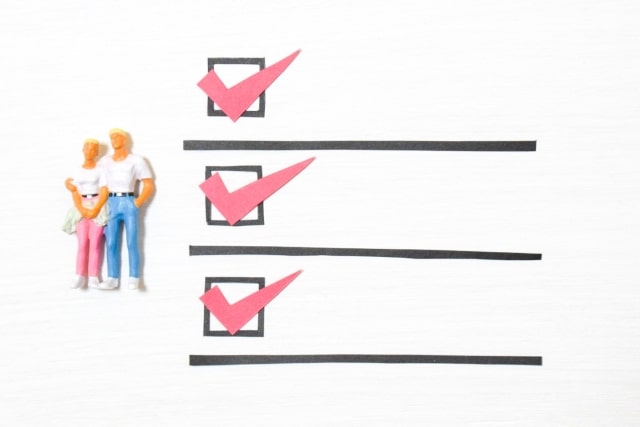
居宅介護支援の初回加算は、新規のケアプラン作成時に適用される重要な加算です。ただし、算定には新規作成の条件や要介護状態の大幅な変化など、明確な要件を満たす必要があります。
再契約時には適用不可であり、退院・退所加算との併用もできないなど、注意点も多いため、正しく理解した上で申請を進めることが重要です。
加算の適用漏れや記録の不備を防ぐためには、業務負担を軽減しながら正確なケアプラン管理ができる介護ソフトの活用もおすすめです。申請の効率化を図り、利用者にとって適切なケアを提供するためにも、介護システムの活用も検討してみてはいかがでしょうか?

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。