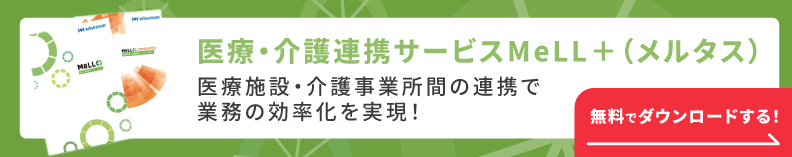訪問看護における多職種連携の必要性|連携機関と連携強化加算を徹底解説
2024.06.08
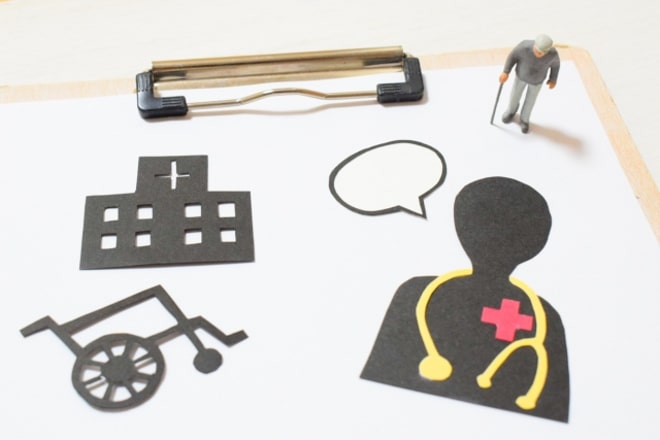
多職種連携を実施すれば、訪問看護ステーションと他の関連機関・職種を連携させて、スムーズな情報共有を実現できます。
しかし「訪問看護における多職種連携がなぜ必要か」「どのような施設と連携するのか」など、疑問に思う方は多職種連携の必要性を確認しておいてください。
本記事では、訪問看護における多職種連携の必要性について詳しく解説します。
主な連携機関と連携強化加算の算定要件も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
なお、株式会社ワイズマンでは円滑なコミュニケーションを実現したいとお考えの方に向けて「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料配布しています。
多職種スタッフ間でシームレスな連携を取りたいとお考えの方は是非ご活用ください。
目次
訪問看護における多職種連携とは

訪問看護における多職種連携とは、看護師や医師・ケアマネジャーなどさまざまな分野の職種が連携し、共通の目的を達成するために協力することを指します。
訪問看護では、利用者宅を訪問し適切なケアサービスを提供するために、医師やケアマネジャーの協力が必要です。
介護・看護・医療は密接な関係にあるため、相互に連携して情報を共有することで、利用者情報や実施するべきケア内容をスムーズに把握できます。
従業員の負担を軽減しながら利用者に高品質なケアサービスを提供するために、多職種連携が求められています。
多職種連携の必要性
多職種連携が求められている背景には、高齢者人口の増加が関係しています。
少子高齢社会が加速している現代では、介護士・看護師などケアサービスを提供する労働人口に対して、利用者となる高齢者の人口が多いです。
総務省の人口統計データによると、2025年2月1日時点で65歳以上の高齢者は3,622万人いることが判明しました。
| 年齢層 | 人口 | 割合 |
| 15歳未満 | 1,371万人 | 11.1% |
| 15~64歳 | 7,360万人 | 59.6% |
| 65歳以上 | 3,622万人 | 29.3% |
| 75歳以上 | 2,099万人 | 17.0% |
| 85歳以上 | 682万人 | 5.5% |
75歳以上の高齢者が2,099万人もいるため、介護・医療の需要が今後も増加していく見込みです。
在宅医療を必要とする利用者が増えている現代では、多職種連携によってスムーズな情報提供と高精度なケアサービスを実現させる必要があります。
地域包括ケアシステムとは
多職種連携の実施を検討する際には、地域包括ケアシステムの実現も視野に入れておきましょう。
地域包括ケアシステムとは、要介護状態になった人が住み慣れた地域で、自分らしく生きられるように地域の医療・介護機関が協力してサポートしていく体制のことです。
市町村などの自治体が主体となり、住まい・医療・介護・予防・生活支援などのサービスを包括的に提供します。
要介護者に住み慣れた地域で自分らしく暮らしてもらうためには、医療・介護などさまざまな職種が連携して、ケアサービスを提供する必要があります。
地域医療構想とは?訪問看護における役割との関係性
地域医療構想とは、高齢化や人口減少による医療ニーズの変化に対応し、医療機関の機能分化・連携を進めるための仕組みです。
具体的には、各地域における医療需要と病床の必要量を以下の4つに分類し、それぞれの役割を明確にしています。
| 高度急性期 | ・高度な治療 ・集中治療を提供する病院 |
| 急性期 | ・主に入院治療を行い、状態の安定を目指す病院 |
| 回復期 | ・リハビリなどを中心に、在宅復帰を支援する病院 |
| 慢性期 | ・長期的な療養が必要な患者を受け入れる医療機関 |
上記の分類を基に、各医療機関の機能や病床の必要量を「病床機能報告」として可視化し、各地域の「地域医療構想調整会議」で、今後の方向性について協議が行われています。
訪問看護との関係性
地域医療構想の実現には、病院・診療所・在宅医療のスムーズな連携が不可欠です。その中で訪問看護は、退院後の療養を支え、在宅生活を継続できるようにする役割を担っています。
特に、急性期や回復期の医療機関からのスムーズな退院支援を実現するためには、多職種連携による情報共有が必要です。訪問看護事業所は、医師やケアマネジャーと連携しながら、在宅での医療・介護サービスの調整が求められています。
参考:地域医療構想|厚生労働省
訪問看護と連携する主な職種
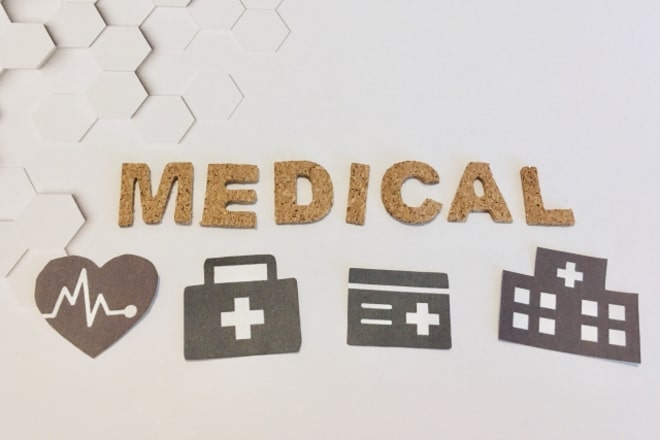
訪問看護と連携する職種は、主に次のとおりです。
- 医師
- 歯科医師
- 病院の看護師
- ケアマネジャー
- ソーシャルワーカー
- 訪問介護員(ホームヘルパー)
- 薬剤師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
それぞれの職種がどのように訪問看護と連携するのか、また求められる役割を解説しますので、多職種連携を実現させる参考にしてください。
医師
訪問看護サービスは医師が交付する指示書に基づいてケアを実施するため、医師との連携が必要です。
医師は訪問看護師より、利用者と関わる時間が少ないため、看護記録から容態や状態を把握しなければなりません。
医師と訪問看護師どちらにとっても、お互いに連携して協力する体制が必要不可欠であり、多職種連携を実現させることで高精度なケアを実施できます。
また利用者の容態が悪化したり緊急事態が発生したりと、訪問看護師だけでは判断できない局面に、医師からの的確な指示が必要です。
歯科医師
訪問看護と連携する職種として、歯科医師が挙げられます。
歯の治療や診察を求める利用者に訪問看護サービスを提供する際、歯科医師の協力が必要です。
訪問看護では、歯科診察だけでなく口腔のケアなどを行うケースもあるため、歯科医師と連携して適切な処置を施さなければなりません。
病院の看護師
訪問看護と病院の看護師が連携して、利用者へのケアを実施するケースがあります。
例えば、病院から退院した利用者が訪問看護を利用する際には、病院の看護師から利用者情報を共有してもらいます。
患者とその家族が安心して訪問看護サービスを受けられるよう、病院の看護師と連携して容態や症状・注意点などを把握しておく必要があります。
退院後のケアが必要な場合は、病院の看護師からの指示にしたがって適切にケアを実施しましょう。
ケアマネジャー
ケアマネジャーは介護支援専門員とも呼ばれており、医療や介護サービスを求める利用者がサービスを受けられるようマネジメントする職種です。
ケアマネジャーがサービスの計画書となるケアプランを作成し、サービス事業者との連携や調整を行うため、訪問看護を提供する際に連携が欠かせません。
利用者の容態の変化に気がついた際には、医師だけでなくケアマネジャーにも情報を共有・報告しておくことで、より利用者の容態に適したケアプランを作成できます。
ソーシャルワーカー
ソーシャルワーカーは、社会福祉士資格や精神保健福祉士資格を持つ相談員のことです。
医療や介護・福祉に関する相談を受けて、利用者の悩みを解決するため助言や調整を行います。
場合によっては訪問看護など他の職種と連携して、利用者に必用なサービスを提供することもあります。
訪問介護員(ホームヘルパー)
訪問介護員は、訪問看護師と同じく利用者の自宅を訪ねて、ケアサービスを実施する職種です。
訪問看護師が医療的なケアや管理を行うのに対して、訪問介護員は日常的な生活を援助します。
原則として訪問看護師が医療行為を行いますが、利用者への提供頻度が高い「喀痰吸引」「経管栄養」に関しては、訪問介護員が行うケースもあります。
訪問介護員が医療行為を行う際には、訪問看護師の指導のもとにケアを実施しなければなりません。
場合によっては訪問看護師と訪問介護員の双方が、同時に利用者を訪問してケアサービスを実施するケースもあります。
薬剤師
訪問看護では、利用者が薬の飲み忘れや管理ミス・過剰服用を避けるために、薬剤師と連携する必要があります。
薬物治療を適切に行うためにも、利用者やその家族に薬の管理や服用を指導する必要があります。
訪問看護師だけでなく薬剤師が一緒に利用者宅を訪問して、服薬指導を行うことが薬物治療を進める上で重要です。
万が一に薬による副作用が生じた場合には、医師や薬剤師と連携して適切な処置を実施しましょう。
理学療法士
理学療法士は、「Physical Therapist(PT)」とも呼ばれる職種で、主に利用者の身体機能の維持・向上を目的にサービスを提供します。
動いたり歩いたりなどの動作や運動によって、身体機能の問題をチェックし、自立した生活ができるよう指導します。
運動療法や物理療法などを行って利用者の身体的問題と向き合うため、訪問看護において重要な職種です。
訪問看護で身体的問題を解決するためには、理学療法士との連携が求められます。
作業療法士
作業療法士は、「その人らしい」生活を獲得するために、下記の業務を行う職種です。
- 基本的動作・能力の改善(運動や感覚・知覚、心肺や精神・認知などの心身機能などを訓練する)
- 応用的動作・能力の改善(食事やトイレ・家事など、日常で必要となる身辺動作や家事動作などを訓練する)
- 社会的適応・能力の改善(地域活動への参加、就労・就学で不便が出ないよう訓練する)
- 福祉用具指導・住環境の整備(日常生活を円滑に行うために車椅子や歩行器などの福祉用具の選び方や使い方についての指導する)
参照元|森ノ宮医療大学「作業療法士」|まるわかり医療の仕事図鑑」
作業療法士は、身体機能や日常生活・地域活動など、さまざまな観点から社会的生活を営めるようサポートします。
訪問看護では、リハビリや車椅子などの福祉用具を使うこともあるため、作業療法士との連携が必用です。
言語聴覚士
言語聴覚士は、コミュニケーションに問題がある利用者に訓練・指導・助言を行う職種です。
主に下記のような問題を抱えている利用者を対象にケアを実施します。
- 言語障がい
- 高次脳機能障がい
- 音声障がい
- 構音障がい
- 嚥下障がい
- 聴覚障がい
「話す」「聞く」などのコミュニケーションに関する機能だけでなく、嚥下障がいのように「食べる」に関する問題にも対応します。
コミュニケーションや食事に関する問題がある利用者に訪問看護を実施する際には、言語聴覚士と連携して適切なサービスを提供しましょう。
訪問看護における看護師の3つの役割

訪問看護において、看護師は多職種連携を円滑に進める重要な役割を担っています。訪問看護の現場で求められる看護師の役割は、大きく分けて3つあります。
利用者の健康状態を見守る役割
訪問看護師は、利用者の健康状態を日々観察し、異変があれば速やかに対応します。具体的には、以下のように状態を確認します。
- バイタルチェック(体温・脈拍・血圧・呼吸数など)を行い、利用者の基本的な健康状態を把握
- 利用者の行動や言動の変化を細かく観察し、心身の状態を評価
医師へ状態変化を報告し、適切な対応を促す
看護師は利用者に最も近い存在として、日常の変化を早期にキャッチし、迅速にケアする役割を果たします。
多職種間の連携を円滑にする役割
訪問看護師は、利用者を中心にさまざまな職種と情報を共有し、調整役としての役割を担います。具体的な役割は、以下のとおりです。
- 医師と密に連携し、適切なケアプランを策定・調整
- 理学療法士・作業療法士と協力し、利用者のリハビリ計画を支援
- 薬剤師と連携し、利用者の服薬状況を管理し、適切な服薬指導を実施
多職種間でのスムーズな連携が実現すれば、より質の高いケアを提供できるようになります。
在宅療養を支える指導・サポートの役割
利用者が自宅で安心して生活できるよう、看護師は適切な指導やサポートを行います。具体的な指導は、以下のとおりです。
- 服薬管理の指導(飲み忘れ防止や副作用の確認)を行い、治療の継続をサポート
- 家族への介護指導(移動補助・食事介助・清潔ケアなど)を行い、適切なケアができるよう支援
- 傷の手当や医療的ケア(褥瘡ケア・カテーテル管理・人工呼吸器管理など)の方法を指導
退院後や在宅療養中の利用者にとって、看護師の指導は生活の質を維持する上で欠かせないものです。
訪問看護における看護師の役割は多岐にわたり、多職種連携のために必要な存在です。他職種とのスムーズな連携を実現すれば、利用者の生活の質を向上させられるでしょう。
訪問看護で多職種連携を行うメリット

訪問看護で多職種連携を行うメリットは、次のとおりです。
- 高品質な看護サービスを提供できる
- 多角的な視点で課題を解決できる
- 幅広いリハビリニーズに対応できる
それぞれのメリットを確認して、多職種連携を実施するべきか検討しましょう。
高品質な看護サービスを提供できる
訪問看護で多職種連携を実施すれば、提供する看護サービスの質を高められます。
訪問看護では身体的な看護の他に、精神的なケアや服薬指導を行う場面もあり、専門的な知識が必要です。
理学療法士や作業療法士・言語聴覚士に薬剤師など、専門家と連携することで、訪問看護師だけでは実現できない高品質なサービスを提供できます。
利用者満足度の向上や容態回復のためにも、多職種連携は重要です。
多角的な視点で課題を解決できる
訪問看護において多職種連携を行うメリットは、多角的な視点で課題を解決できることです。
複数の職種が連携して看護サービスを提供することで、多角的な視点で課題を見つけられます。
それぞれの職種が専門性を発揮し、利用者の課題解決に向けて取り組むことで、早期解決・回復につながります。
訪問看護サービスの質を向上させるためにも、多角的な視点で物事を捉えられる多職種連携が必要です。
幅広いリハビリニーズに対応できる
訪問看護では、利用者の健康状態や生活環境に応じた多様なリハビリが求められます。特に、生活習慣病や認知症などの慢性疾患を抱える方が増えている現状では、一つの職種だけでは対応しきれないケースも少なくありません。
そこで、多職種連携の活用により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職が協力し、利用者のニーズに合ったリハビリを提供できます。
例えば、以下のような専門的なリハビリの実施により、利用者の身体機能や生活の質(QOL)向上につながります。
- 理学療法士:歩行訓練や筋力向上のリハビリを実施
- 作業療法士:日常生活動作(ADL)の向上を支援
- 言語聴覚士:摂食・嚥下リハビリを担当し、安全な食事をサポート
上記のように、それぞれの専門家が協力すれば、訪問看護師だけでは実現できない多角的なアプローチができます。結果として、利用者一人一人の症状や生活環境に応じた適切なリハビリを提供でき、訪問看護サービスの質を向上させることにつながります。
訪問看護の多職種連携における課題と対策法

訪問看護の多職種連携を実施する際には、次のような課題が生じます。
- スムーズに情報共有ができない
- 情報共有先や内容を把握できない
それぞれの課題に対する対策法を解説しますので、多職種連携を成功させるために実施しましょう。
【課題】スムーズに情報共有ができない
多職種連携を実現させる際に、各関連機関とスムーズに情報共有ができない課題が発生します。
各専門機関も他の業務を担当しているため、担当者と連絡が取れずに情報共有が遅れる可能性があります。
【対策法】情報共有をオンライン上で行うツールを導入する
多職種連携の情報共有をスムーズに行うために、ツールを活用するのがおすすめです。
メッセージツールやコミュニケーションツールを導入して、オンライン上で各関連機関と連携ができる体制を整えておけば、緊急性が高い用事でもスムーズに伝達できます。
【課題】情報共有先や内容を把握できない
多職種連携の課題として、情報共有先や内容を把握できないケースがあります。
専門的な助言を求める場合に「どの機関の誰に連絡を取れば良いのか」など、連携先を明確化しておかなければスムーズに情報共有ができません。
また多職種連携を実施する際にも、「どのような情報を共有するべきか」の内容が不明瞭な場合は、伝達する情報に悩んでしまう可能性があります。
【対策法】関係者間で不足している情報を提示し合う
多職種連携において情報共有先や内容を把握できていない場合は、関係者間で不足している情報を提示し合うことが大切です。
事前に担当者の名前や情報共有の内容を明確化し、各関連機関が情報を提示し合うことで、スムーズな情報共有を実現します。
連絡ノートの作成やコミュニケーションツールでのメモ機能など、利用者の状態やケアサービスのスケジュールを共有しておくことで、高品質なケアを実現できます。
なお、株式会社ワイズマンでは円滑なコミュニケーションを実現したいとお考えの方に向けて、「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
訪問看護における多職種連携を成功させるコツ

各職種が関わる多職種連携では、連携ミスやトラブルの発生を防がなければなりません。
訪問看護における多職種連携を成功させるためには、次の5つのコツを押さえておいてください。
- 共通の目的を設定する
- 職種間でのコミュニケーションを重視する
- 職種ごとの役割を把握する
- 自職種の専門性を活かす
- 多職種間での関係性を構築する
それぞれのコツを押さえて、訪問看護で多職種連携を成功させましょう。
共通の目的を設定する
訪問看護における多職種連携を成功させるために、まず共通の目的を設定することが大切です。
さまざまな職種が関わる多職種連携では、利用者がどのような課題を抱えてどのような生活を実現したいのか、共通の目的を把握しておく必要があります。
各関連機関の目的が異なっていると、職種間での意見の食い違いや連携ミスによって連携体制が崩壊する恐れがあります。
利用者やその家族を含む関連機関で、共通の目的を設定して訪問看護に取り組みましょう。
職種間でのコミュニケーションを重視する
訪問看護で多職種連携を成功させるコツは、職種間でのコミュニケーションを重視することです。
利用者に容態の変化が起きた際には、情報を共有して関連機関にすぐ情報を共有する必要があります。
情報共有が疎かになると、適切な処置ができない可能性があり、利用者の不利益につながります。
また職種間で使用している用語が異なる場合は、専門用語を使用することによる情報伝達ミスが生じないよう注意してください。
職種ごとの役割を把握する
訪問看護で多職種連携を実施する際には、職種ごとの役割を把握することが大切です。
各職種の専門性を生かして、どのようなケアを実施するべきか事前に話し合っておきましょう。
職種ごとの役割を把握しておくことで、利用者に適切な看護サービスを提供できます。
また利用者に対してどのような職種が関わっているのか、連携する関連機関を把握しておくことも大切です。
自職種の専門性を活かす
訪問看護で多職種連携を成功させるコツは、自職種の専門性を活かすことです。
多職種連携では、言語聴覚士・薬剤師など専門性の高い職種が連携するため、各機関が専門性を発揮しなければなりません。
自職種に求められているスキルや知識・役割を認識して、専門性を生かして利用者の課題を解決しましょう。
多職種間での関係性を構築する
訪問看護で多職種連携を行う際には、多職種間での関係性を構築しておきましょう。
関係性が構築できていない状態で多職種連携を行っても、スムーズにコミュニケーションが取れない可能性があります。
率直な意見やタイムリーな情報共有などを行うには、風通しの良い関係性を構築しておく必要があります。
各関連機関のスタッフ同士が円滑にコミュニケーションを取れるよう、オリエンテーションや打ち合わせを通じて、関係性を構築しておいてください。
介護・看護職員連携強化加算とは

介護・看護職員が連携して業務を遂行すると、介護保険・医療保険における介護・看護職員連携強化加算の算定対象になる可能性があります。
介護・看護職員連携強化加算を適用させるために、算定要件と単位数・注意点を把握しておきましょう。
介護・看護職員連携強化加算の算定要件
介護・看護職員連携強化加算の算定要件は、次のとおりです。
- 喀痰吸引などの業務をスムーズに行うために、業務に関する計画書と報告書を作成し、緊急時の対応について助言を行うこと。
- 訪問介護職員と訪問看護職員が同行して利用者宅を訪問し、介護・看護サービスを実施すること。また利用者に対する安全なサービス提供の体制を整備、連携体制を確保するための会議に参加すること。
- 訪問介護職員と訪問看護職員が同行し業務を行ったり会議に出席したりした記録をつけること。
- 24時間緊急時に対応できる体制を整えて、緊急時訪問看護加算を届出をしていること。
喀痰吸引など介護士と看護師が協力して実施する業務に関して、計画書と報告書を作成しておく必要があります。
さらに同行して業務を行ったり会議に参加したりと、連携して業務を遂行している記録をつけておくことが大切です。
介護・看護職員連携強化加算を受けるためには、緊急時訪問看護加算の届出も必要です。
介護・看護職員連携強化加算の単位数
介護・看護職員連携強化加算の単位数は、次のとおりです。
| 適用保険 | 介護保険 | 医療保険 |
| 1カ月ごとの単位数・算定料 | 250単位 | 2,500円 |
介護・看護職員連携強化加算の注意点
介護・看護職員連携強化加算を適用させるために、次のポイントに注意しておきましょう。
- 毎月1回目に同行または会議へ参加した日の、訪問看護を実施した日に単位数を加算する
- 訪問介護員に同行して喀痰吸引などを行った場合、通常の業務時間より時間がかかってもケアプランで定められた訪問看護費を算定する
- 訪問介護員の技術向上目的で同行業務を実施した場合は、加算算定がされない
介護・看護職員連携強化加算が適用される日付は、毎月1回目の同行訪問もしくは会議へ参加した日です。
さらに同行訪問によって業務時間が長引いた場合でも、ケアプランで定められた費用以上を請求できません。
また技術習得や研修目的で同行訪問は、本来の目的から外れるため、介護・看護職員連携強化加算の算定対象外です。

訪問看護における多職種連携の必要性は、高齢化の進行による在宅医療・介護の需要増加や、地域包括ケアシステムの推進と深く関わっています。訪問看護師は、利用者の日々の健康状態を把握し、医師・ケアマネジャー・リハビリ専門職などと連携しながら、質の高い在宅ケアを提供する役割を担っています。
しかし、情報共有の不足や連携の遅れが課題となるケースも少なくありません。これを解決するためには、明確な連携体制の構築、オンラインツールの活用、定期的なカンファレンスの実施などがポイントとなります。
また、介護・看護職員連携強化加算の活用により、訪問看護と訪問介護の連携を強化し、より包括的なケアの提供も可能になります。多職種連携を強化することで、利用者のQOL向上や医療・介護スタッフの負担軽減にもつながるため、積極的に取り組むことが望まれます。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので是非ご覧ください。
訪問看護の多職種連携を強化するには「MeLL+(メルタス)」がおすすめ

訪問看護の多職種連携を強化したいなら、ワイズマンが提供する「MeLL+(メルタス)」がおすすめです。
「MeLL+(メルタス)」は、法人間での連携を強化する多職種間コミュニケーションツールで、地域包括ケアシステムの実現を支援します。
「MeLL+(メルタス)」には、以下3種類があります。
- 法人内の連携ソリューションを実現する「MeLL+professional」
- 地域間の連携ソリューションを実現する「MeLL+community」
- 事業所と利用者家族の連携ソリューションを実現する「MeLL+family」
それぞれの機能を活用することで、スムーズな情報共有を実現し多職種連携に活用できます。
高精度な訪問看護を実現するために多職種連携を実施しよう
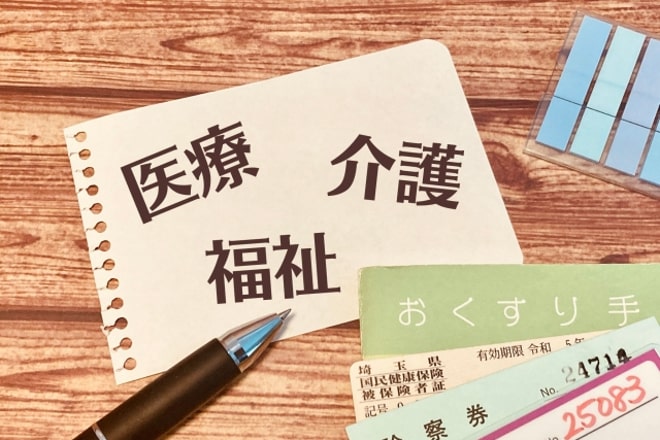
訪問看護における多職種連携を実施すれば、さまざまな専門機関が協力して高精度なケアサービスを実現できます。
利用者満足度の向上や家族への安心にもつながるため、訪問看護ステーションを運営する上で多職種連携は重要です。
さらに高齢者が増加している現代では、医療・介護の需要が高く、多職種連携によるスムーズな情報共有が求められています。
情報を共有しながら互いの専門性を発揮すれば、利用者の課題解決が可能です。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。