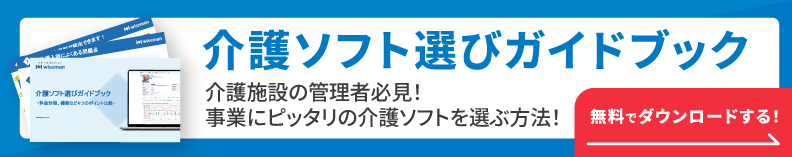老健で提供するリハビリテーションの内容とは?職種別の仕事内容や加算要件について解説
2022.12.05

老健は高齢者向けのリハビリテーション施設ですが、提供されるリハビリテーションの回数や時間に制限があるのをご存じでしょうか。老健で行われるリハビリテーションは、病院で行われるリハビリテーションとは内容が異なります。それは、リハビリテーションを行う目的がそれぞれ異なるためです。
ここでは老健で提供するリハビリテーション内容のほか、職種別の仕事内容や加算要件について解説しています。
なお、株式会社ワイズマンでは介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて「介護ソフト選びガイドブック」を無料配布しています。
介護ソフトの導入時によくある問題と対策についても記載していますので是非ご活用ください。
目次
老健で提供するリハビリテーションの内容

老健で提供するリハビリテーションの内容は、利用者の状態・目標によって異なるため、個別にメニューが作成されます。
リハビリテーション内容としては、起き上がりからベッドと車いす間の移乗、歩行訓練など日常生活が送れることを目指します。
リハビリテーション期間は3か月~6か月で、期間内に高齢者が在宅復帰を果たせるように支援します。
老健におけるリハビリテーションの人員体制

老健とほかの介護施設との違いは、医療ケアに力を入れているため、医師の常勤が義務つけられていることです。
さらに高齢者の在宅復帰を目的とするため、介護・看護・リハビリテーション専門職のほか、施設サービス計画書の作成を行う支援相談専門員や食事の提供を行う栄養士などで人員体制が組まれています。
具体的には、以下のような人員体制が必要です。
| 職種 | 役割 |
| 医師 | 健康管理・診断・治療・リハビリの指示 |
| 看護職員 | 医療処置・健康管理・緊急対応 |
| 介護職員 | 日常生活の支援(食事・排泄・移動など) |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 施設サービス計画の作成・調整 |
| 支援相談員 | 入所・退所調整、心理的・社会的支援 |
| 理学療法士 | 基本動作訓練(歩行・関節可動域・呼吸リハなど) |
| 作業療法士 | 日常生活動作訓練・精神的安定の支援 |
| 言語聴覚士 | 言語・嚥下(えんげ)機能訓練・コミュニケーション支援 |
| 栄養士 | 栄養管理・食事形態の調整・嚥下機能サポート |
それぞれ詳しく説明します。
医師
医師は、老健の利用者に対する医学的管理を担当します。具体的には、以下のような役割を果たします。
- 利用者の健康状態を把握し、診断や治療を行う
- 看護師やリハビリテーション専門スタッフと連携し、適切な指示を出す
- 利用者の病状が悪化した場合には、施設内で可能な範囲の治療を実施し、必要に応じて医療機関への紹介を行う
老健においては、医師がリハビリテーションの方向性を決定する重要な役割を担っており、他の職種と密接に連携を取ることが求められます。
看護職員
看護職員は、医師と連携しながら利用者の医学的管理をサポートします。主な業務には、以下のようなものがあります。
- 利用者の健康状態の観察と記録
- 医療処置(投薬管理、点滴、創傷処置など)の実施
- 緊急時の対応や医師への報告
- 他職種との情報共有
特に、老健では医療依存度の高い利用者が多いため、看護職員は重要な役割を担っています。
介護職員
介護職員は、利用者が日常生活を安全かつ快適に過ごせるよう支援します。具体的な支援には、以下のようなものがあります。
- 食事・排泄・入浴の介助
- 身体介護(移動・更衣など)
- 生活リハビリの補助
- 他職種との連携による利用者のケア
老健では、リハビリテーションを通じて在宅復帰を目指すため、介護職員もリハビリテーションの視点を持ち、利用者の生活機能向上に支援する役割を担います。
介護支援専門員
介護支援専門員は、利用者の希望や状態に応じて適切な介護サービスが提供されるよう調整を行います。
- 施設サービス計画書(ケアプラン)の作成
- 利用者や家族との面談、相談対応
- 介護サービスの選定・調整
- 居宅ケアマネジャーや他職種との連携
老健では、在宅復帰に向けた支援が重要となるため、施設内外の関係者と連携しながら、適切なサービスを提供できるよう調整する役割を担います。
支援相談員
支援相談員は、施設と地域、家族、利用者の間に立ち、円滑な連携を図る役割を担います。
- 入所前の相談・手続き
- 退所支援や在宅復帰のための調整
- 利用者や家族の心理的・社会的サポート
- 地域の医療・介護機関との連携
老健では、利用者がスムーズに入所・退所できるよう、医師やケアマネジャーと連携しながら支援を行います。利用者の不安や悩みを解消し、適切な介護サービスを受けられるようサポートするのも支援相談員の役割です。
リハビリテーション専門スタッフ【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士】
老健のリハビリテーションでは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが専門的な役割を果たします。
| 理学療法士 | 歩行訓練や関節可動域訓練など、基本動作能力の向上を目的としたリハビリテーションを提供転倒予防や痛みの管理呼吸リハビリテーションによる肺機能向上 |
| 作業療法士 | 日常生活動作(ADL)の向上を目的としたリハビリテーション手先の巧緻性を高める作業活動(貼り絵や手芸など)精神的な安定を図るためのプログラムの実施 |
| 言語聴覚士 | 言語機能や発声のリハビリテーション嚥下(えんげ)機能訓練による誤嚥(ごえん)の予防コミュニケーション能力の向上 |
リハビリテーション専門スタッフは、利用者の身体機能や生活状況を総合的に評価し、それぞれの専門分野に基づいた支援を提供します。
なお、個別の仕事内容に関しては、次章で詳しく解説します。
栄養士
栄養士は、利用者の健康状態を維持・向上させるため、栄養管理を行います。
- 栄養状態の評価(体重・血液検査・食事状況の確認など)
- 食事内容の計画と調整
- 嚥下機能や咀嚼能力に応じた食事形態の設定
- 医師や看護師、言語聴覚士と連携した栄養管理
老健では、利用者の状態に応じた適切な食事提供が求められるため、栄養士が多職種と連携しながら個別の対応を行います。
老健におけるリハビリテーションの人員体制は多職種が連携して成り立っています。それぞれの専門職が利用者の在宅復帰を支援するため、密接に協力しながら支援を提供しているのが特徴です。
老健におけるリハビリテーションの仕事内容

老健では、高齢者の在宅復帰を支援するために、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3つの専門職がリハビリテーションを担当します。それぞれの専門職が担う役割について、より具体的に解説していきます。
理学療法士|身体機能の維持・向上を支える
理学療法士は、主に基本動作能力の改善を目的としたリハビリテーションを行います。高齢者が自立した生活を送るためには、立つ・座る・歩くといった基本動作がスムーズにできなければなりません。そのため、理学療法士は以下のようなアプローチで支援を行います。
| 筋力トレーニング | 下肢や体幹の筋力を鍛え、歩行や移動能力を向上させる |
| 関節可動域訓練 | 関節の柔軟性を維持し、日常生活動作をスムーズに行えるよう支援 |
| 歩行訓練 | 杖や歩行器を使いながら、安全な歩行方法を習得 |
| 呼吸リハビリ | 呼吸機能が低下した利用者に対し、息切れを防ぐ呼吸法や運動を指導 |
老健では、病院での急性期リハビリと異なり、日常生活に直結する動作の改善が目的となるため、利用者一人ひとりの目標に応じたリハビリプログラムが作成されます。
作業療法士|身体機能の維持・向上を支える
作業療法士は、日常生活の動作(ADL)や趣味・社会参加(IADL)に関わるリハビリテーションを担当します。単に身体機能を回復させるだけではなく、利用者が自分らしい生活を続けられるように支援することが目的です。
| 日常生活動作訓練 | 食事・更衣・トイレ動作などの訓練を実施 |
| 手指の巧緻(こうち)性訓練 | ボタンの留め外しや書字など、細かい動作を改善 |
| 認知機能の活性化 | パズルや工作を通じて、認知機能の維持を図る |
| 精神面のサポート | 抑うつ傾向のある利用者に対し、作業活動を通じて気分の安定を促す |
老健では、利用者の「できること」を増やすために、本人の興味や希望を取り入れたリハビリを実施する必要があります。そのため、作業療法士は、利用者が楽しく続けられるリハビリプログラムを考えることが求められます。
言語聴覚士|食事とコミュニケーションの支援
言語聴覚士は、発声や言葉のリハビリに加え、飲み込み(嚥下)機能の改善も担う専門職です。高齢になると、脳血管疾患や加齢の影響で、話す・飲み込む機能が低下する場合があり、日常生活に大きな支障をきたします。
| 発声・構音訓練 | 声が出にくい、言葉がはっきりしないなどの問題に対処 |
| 言語訓練 | 失語症や認知症による会話の困難さを改善 |
| 嚥下訓練 | 食事中のむせを防ぎ、安全に食事を摂取できるよう指導 |
| 食形態の調整 | 飲み込みやすい食事形態を提案し、栄養士と連携 |
特に、誤嚥性肺炎を予防するための嚥下リハビリは、老健において重要な役割を果たします。食事の際にむせる頻度が多い利用者には、食べ方の指導や嚥下機能のトレーニングが行われます。
なお、株式会社ワイズマンではすでに介護ソフトを導入しているが、介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて、「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。ダウンロードしてご活用ください。
老健におけるリハビリテーションの頻度
老健では一般的に20分から30分のリハビリテーションを、週2回以上行う規定があります。ただし、入所してから3か月間に限り、短期集中リハビリテーションを週3回から毎日受けることが可能です。リハビリテーションの回数については、施設によって異なります。
なお、過去3か月以内に別の老健に入所されていた場合、短期集中リハビリテーションは受けることができません。
老健のリハビリテーションによる加算
老健で提供されるリハビリテーションには加算要件があり、加算要件はリハビリテーションの種類によって異なります。
短期集中リハビリテーション実施加算
短期集中リハビリテーション実施加算とは、老健に入所してから3か月間に集中的にリハビリテーションを実施することで発生する加算のことです。
| 単位数 | 240単位 |
| 算定要件 | ・医師もしくは医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを実施すること ・過去3ヵ月以内に老健に入所していない利用者に対して、入所日から3ヵ月以内に1週間に概ね3回以上、1日当たり20分以上のリハビリテーションを集中的に実施すること ※ただし過去3か月以内に老健に入所していても、下記の条件を満たす場合には算定が可能です。 ・4週間以上入院の再入所で、早期にリハビリテーションが必要な入所者 ・4週間未満の入院後に再入所し、脳梗塞や脳出血など特定の疾患がある入所者 |
(※)参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
在宅復帰・在宅療養支援機能加算
在宅復帰・在宅療養支援機能加算とは、在宅復帰支援を目的とする施設に対して、役割を評価する目的で設けられた加算のことです。
加算Ⅰと加算Ⅱに区分され、単位数と算定条件が異なります。
| 単位数 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)51単位在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)46単位 |
| 算定要件 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) ・介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)、介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅲ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)ユニット型介護保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)経過的ユニット型介護保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)のいずれかを算定していること ・在宅復帰・在宅療養支援等指標(※)により算定した数が「40以上」であること地域に貢献する活動を行っていること 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) ・介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)ユニット型介護保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)経過的ユニット型介護保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)のいずれかを算定していること ・在宅復帰・在宅療養支援等指標(※)により算定した数が「70以上」であること |
(※)参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算とは、適切なリハビリテーションを提供するためにS(Survey調査)、P(Plan計画)、D(Do実行)、C(Check確認)、A(Action改善)のサイクル構築とリハビリテーションの継続的な管理を評価する加算のことです。
| 単位数 | リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)60単位リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)150単位 |
| 算定要件 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) ・訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること ・指定訪問リハビリテーション事業所のPT、OT又はSTが、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業にかかる従業者に対し、リハビリ テーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) ・リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること ・訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、同意を得ること ・3月に1回以上、ハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること ・指定訪問リハビリテーション事業所のPT、OT又はSTが介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法 及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと ・以下のいずれかに適合すること (一)指定訪問リハビリテーション事業所のPT、OT又はSTが、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業にかかる従業者と指定訪 問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を 行うこと (二)指定訪問リハビリテーション事業所のPT、OT及びSTが、指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、 介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと ・上記のすべてに適合することを確認し、記録すること リハビリテーション会議は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者その他の 関係者が構成員となって実施される必要がある。 |

老健(介護老人保健施設)におけるリハビリテーションは、病院の急性期リハビリとは異なり、在宅復帰を目指した生活機能の向上が目的となります。そのため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職が連携し、個々の利用者に適したプログラムを提供することが重要です。
リハビリの効果を最大限に引き出すためには、短期集中リハビリテーションの活用や、リハビリマネジメント加算の要件を満たす適切な計画管理が欠かせません。加えて、日常生活の中で介護職員や看護職員がリハビリの視点を持って支援を行うことで、機能訓練の効果がより定着しやすくなります。
老健のリハビリは、多職種の密な連携が成功の鍵となります。職種ごとの役割を明確にし、定期的なカンファレンスや情報共有を徹底することで、利用者一人ひとりにとって最適な支援が提供できるよう心掛けましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。
すでに介護ソフトを導入していている方も、介護ソフトの入れ替えを検討している方も、自身に最適なプロダクトを選ぶために重要な4つのポイントを解説していますので是非ご活用ください。
まとめ|老健のリハビリテーションを活かし、利用者支援の質を高めよう!
老健では、医師やリハビリ専門スタッフ、介護職員などが連携し、利用者の生活機能向上と在宅復帰を目指したリハビリテーションを提供しています。リハビリの質を高めるには、職種ごとの役割を理解し、チーム全体での適切な支援が必要です。
また、リハビリテーションの加算は請求業務に大きく関わるため、制度を正しく理解し、適切な管理が求められます。加算要件を満たすためにも、日々のリハビリ計画の見直しや情報共有を徹底しましょう。
現場での実践を通じて、より効果的なリハビリテーションを提供し、利用者の在宅復帰を支援していきましょう!
情報連携が必要な現場では「ワイズマンの介護ソフト」をお使いいただくことで、計画的なケアマネジメントの実施が可能となります。軽減税率にも対応しているためスムーズに請求業務を行うことができ、作業効率化につながります。
もし、今働いている事業所に介護ソフトが導入されていないなら、業務効率化を図れるように担当者に導入を相談してみてください。これから老人保健施設で働かれるのであれば、事業所に介護ソフトが導入されているかチェックされることをおすすめします。
介護ソフトの資料請求や、デモンストレーションをご希望の方はこちらから簡単にお問い合わせいただけます。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。