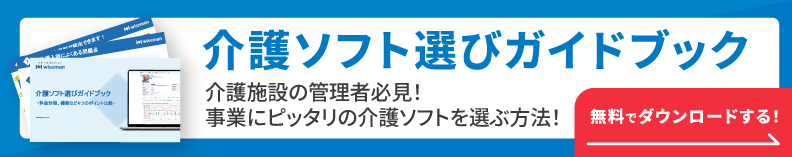老健(介護老人保健施設)の種類と特徴|入所条件やサービス内容も解説
2023.02.15

老健は、利用者が在宅生活の復帰を目指すための施設です。老健では、利用者が医師による医療ケアや作業療法士などからリハビリテーションを受けられます。また、老健には利用者一人ひとりに合わせた使い方ができるのも特徴です。
この記事では、老健の概要や基本的な老健の種類、入所条件や費用、サービス内容、利用するメリット・デメリット、働くメリット・デメリット、老健と特養の違いなどについて解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて「介護ソフト選びガイドブック」を無料配布しています。
介護ソフトの導入時によくある問題と対策についても記載していますので是非ご活用ください。
目次
そもそも老健とは?

老健は「介護老人保健施設」の略で、介護を必要する高齢者が在宅生活を送れるようサポートする施設です。医師による医学的管理の下、看護師・作業療法士・理学療法士などの専門スタッフが日常生活のサポート・リハビリテーションなどを行い、利用者の在宅復帰を目指します。
いわゆる「老人ホーム」のイメージがありますが、老健はあくまで心身機能を維持・回復し、自宅復帰を目指すための施設です。
そのため、原則として利用者の入居期間は3カ月~6カ月程度に限定されます。
ただし、利用者の状態によって入居期間が延長される場合もあります。
老健の種類

老健には以下の5種類があります。
- 超強化型老健
- 在宅強化型老健
- 加算型老健
- 基本型老健
- その他型老健
従来の老健は、在宅強化型・加算型・従来型の3種類でしたが、平成30年の介護保険法改正によってこの5種類に細分化されました。今後の老健のあり方を明確にし、利用者の在宅復帰や在宅療養のサポートをより充実させるためです。
本章では、老健の種類について解説します。
【前提】老健の種類における4つの要件
老健は、「在宅復帰・在宅療養支援等指標」という数値によって上記の5種類に分類されます。また、以下の4つの要件を満たしているかによって区分されます。
| 超強化型老健 | 在宅強化型老健 | 加算型老健 | 基本型老健 | その他型老健 | |
| ① 退所時指導 | 要件あり | 要件あり | 要件あり | 要件あり | いずれの要件も満たさない |
| ② リハビリテーションマネジメント | 要件あり | 要件あり | 要件あり | 要件あり | いずれの要件も満たさない |
| ③ 地域貢献活動 | 要件あり | 要件あり | 要件あり | 要件なし | いずれの要件も満たさない |
| ④ 充実したリハビリ | 要件あり | 要件あり | 要件なし | 要件なし | いずれの要件も満たさない |
| 在宅復帰・在宅療養支援等指標(最高値:90) | 70以上 | 60以上 | 40以上 | 20以上 | いずれの要件も満たさない |
次からは、それぞれの老健の概要を説明します。
超強化型老健
超強化型老健とは、在宅復帰・在宅療養支援等指標の値が70以上、かつ上記①〜④のすべての要件を満たしている老健を指します。老健の認定基準の中で最も厳しい条件をクリアしているため、在宅復帰率は高い傾向にあります。
超強化型老健は在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)など、さまざまな加算を取得できるうえに、1日に取得できる単位数が多い点が特徴です。
ただし、要件が厳しく設定されているため、慎重な運営が求められます。
在宅強化型老健
在宅強化型老健は、在宅復帰・在宅療養支援等指標の値が60以上、かつ①〜④のすべての要件を満たしている老健を指します。超強化型老健と同様、高い在宅復帰率を誇る老健です。
在宅強化型も超強化型老健と同様に、算定要件が厳しい傾向があります。
加算の取得の維持はもちろん、サービスの質の低下を防ぐためにも、高度な運営が求められます。
加算型老健
加算型老健は、在宅復帰・在宅療養支援等指標の値が40以上、かつ①〜③の3つの要件を満たしている老健を指します。
加算型老健は近年施設数が増えており、利用者数も多い老健です。
なお、老健は地域特性などの影響によって在宅復帰ができず、長期入居者が多い施設も少なくありません。
そのような状況を鑑み、近年は在宅療養支援機能の要件を満たせば加算型を目指せるような体系が実践されています。
基本型老健
基本型老健は、在宅復帰・在宅療養支援等指標の値が20以上で、①と②の2つの要件を満たしている老健です。
基本型老健は在宅復帰率がほかの3種類と比較して少なく、その分スタッフの業務負担が増加しやすい傾向があります。
そのため、スタッフの業務負担を考えながら、在宅復帰率の向上に取り組む必要があります。
なお、基本型老健を含め、どの区分にも当てはまらない老健は「その他型」に該当します。
老健の施設の特徴

老健の部屋のタイプには、大きく分けて従来型とユニット型の2種類があります。
本章ではそれぞれの特徴を解説するので、ぜひ参考にしてください。
従来型
従来型には「従来型個室」と「従来型多床室」があります。「従来型個室」は、ユニットケアが登場するまで介護施設で一般的であった居室形態です。個室のためにプライバシーの確保はできますが、各個室の前は廊下でホテルのようなつくりとなっており、構造面で「ユニット型個室」と大きく異なります。
一方「従来型多床室」は、入所者の生活サポートを効率的に行うために古くからある相部屋タイプの居室です。一つの部屋に2〜4人が入所することで集団ケアを可能にしている反面、プライバシーの確保は難しくなっています。
ユニット型
ユニット型には「ユニット型個室」と「ユニット型個室的多床室」があります。「ユニット型個室」は完全個室の居室で、ユニットケアを取り入れた比較的新しいタイプの居室です。1ユニット最大9人で、各個室がリビングなどの共有スペースを囲うように配置されており、自宅での生活空間に近い環境です。
一方「ユニット型個室的多床室」は、もともと一つの大部屋として使っていた居室を簡易的な仕切りで分割した準個室です。完全な個室ではないため防音は難しいですが、ある程度のプライバシーの確保が可能です。
老健の入所条件
老健の入所条件としては年齢要件と要介護度があり、以下の条件を2つとも満たす方が対象となります。
- 年齢要件:65歳以上であること
- 要介護度:1以上の要介護認定を受けていること
また、「支払い能力に問題がないこと」「保証人がいること」も入所にあたってチェックされます。
ただし、40〜64歳の方でも特定疾病の要介護認定を受けている場合は老健入所の対象となります。
もちろん、医療行為やリハビリが必要なく、生活支援などのみで十分な利用者は老健に入所できません。
老健の入所費用

老健は公的な介護保健施設であるため、初期費用である入所一時金はかかりません。入所費用の内訳は主に以下の3つです。
- 施設介護サービス費
- 居住費
- 食費
施設介護サービス費は老健で介護サービスを受けるのに必要な費用で、介護度が上がったり、リハビリなどのケアを受けたりすると、そのぶんかかる費用が高くなります。
居住費は、ユニット型や従来型などの居室タイプによって料金が異なるものです。一般的には、従来型よりもプライバシーを確保できるユニット型(個室)の方が高い傾向があります。なお、居住費は介護保険給付の対象にはなっていません。
食費は、施設で提供される食事に要する食材費や調理費の合計です。居住費と同様に介護保険給付の対象外です。
以下の表では、在宅強化型老健におけるユニット型の個室タイプと従来型の多床室タイプ(相部屋)の料金を比較しています。
- ユニット型個室
| 施設介護サービス費 | 居住費 | 食費 |
| 2〜3万円程度 | 6万円前後 | 4万円前後 |
- 従来型多床室
| 施設介護サービス費 | 居住費 | 食費 |
| 2〜3万円程度 | 1万円前後 | 4万円前後 |
費用はあくまで目安であり、施設によって異なります。また、費用面に不安がある方は、ケアマネジャーに相談しましょう。
老健のサービス内容

老健のサービス内容には、主に以下の4つがあります。
- リハビリ
- 医療ケアおよび看護
- 食事・入浴・排泄などの介護
- 相談・生活援助
それぞれのサービスについて、順番に解説します。
リハビリ
老健には理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが常駐しており、利用者が在宅生活に戻れるようにリハビリテーションに力を入れています。例えば、退院直後の自宅での生活に不安がある方には、老健はおすすめの施設です。
持病やケガなどの影響で在宅生活の復帰を目指す利用者にとって、老健が提供するサービスは重要です。
スムーズに在宅復帰できるよう、個々の利用者の状況を把握したうえで適切に対応する必要があります。
医療ケアおよび看護
常勤医師や看護師による医療ケアを受けられるのも老健の大きな特徴です。痰の吸引をしてもらったり、食べるのが難しい方には経管栄養などの医療処置をしてもらえたりします。
また、施設によってはターミナルケアなどのサービスを提供している場合があります。
利用者のニーズに合わせて、適切な医療ケアや看護を提供できるようにすることも、老健の運営において重要です。
食事・入浴・排泄などの介護
老健では、リハビリだけでなく日常生活に必要な身体介護を受けられます。例えば、食事介助・着替えの介助・おむつ交換・排泄介助・入浴介助などです。
食事の介助では、老健の食事は利用者に合わせたメニューで提供することが求められます。
利用者の健康状態や持病などを踏まえ、適切な栄養ケア計画を策定することで、より良い健康管理を実践することも、老健の重要な役目です。
一方で、老健は通常の介護サービスほど日常生活支援が充実していないケースがあるので注意しましょう。
相談・生活援助
利用者やその家族が問題を抱えている場合には、支援相談員やケアマネジャーに相談ができます。また、生活援助として利用者の居室のシーツ交換や清掃などをしてもらえるので、利用者の負担を減らせます。
利用者が快適な生活を送り、利用者の家族が不安を解消するうえで、相談・生活援助は不可欠なサービスです。
老健の活用方法

老健の活用方法は利用者の身体的状況に応じてさまざまですが、以下のように大きく分けて3つの活用方法があります。
- 施設サービスを受ける
- ショートサービスとして利用する
- デイケアを受ける
- 老健をより良く活用するうえでの参考にしてください。
施設サービスを受ける
老健の入所期間は原則3ヵ月です。期間中は、介護や看護、医療の提供や日常生活に復帰するためのリハビリテーションなどのサービスが提供されます。医学的管理が徹底された施設で、医師・看護師・理学療法士・作業療法士などの専門スタッフのサポートのもと、日常生活への復帰を目的とした訓練や介護サービスを受けられます。
ショートサービスとして利用する
自宅での介護や看護が一時的に難しくなった場合には、老健に短期的に入所してサービスを受けられるショートステイがおすすめです。ショートステイでは、一般の入所者と同様にリハビリや介護、看護などのサービスを受けられます。
家族のさまざまな事情によって介護をするのが難しくなる場合はもちろん、介護者のレスパイト(休息)としての利用も可能です。
デイケアを受ける
老健では、施設に入所せずにデイケア(通所リハビリ)を受けられます。デイケアでは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが通所リハビリテーションなどのサービスを提供します。
対象となるのは、要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受けた高齢者です。送迎サービスを提供している老健もあるので、遠方にお住まいの方でも気軽に利用できます。
なお、株式会社ワイズマンではすでに介護ソフトを導入しているが、介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて、「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。ダウンロードしてご活用ください。
【入所者向け】老健を利用するメリット

老健を利用することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?老健の利用を検討している方だけでなく、これから働く方やすでに働いている方も知っておくべき以下のメリットを紹介します。
- リハビリの整備が整っている
- 認知症でも入所できる
- 医師常駐のため安心できる
それぞれ順番に解説します。
リハビリの設備が整っている
老健にリハビリ施設が整っているのは大きなメリットです。リハビリテーションには歩行訓練だけでなく、起き上がり・ベッドから車いすへの移乗など、利用者の身体状況によってさまざまなものがあります。老健ではリハビリテーションに対応した機能訓練設備が充実しており、効率的で効果的なリハビリテーションを受けられます。
認知症でも入所できる
老健の入所条件は、原則として要介護1以上かつ65歳以上の高齢者であることです。しかし例外として、40〜64歳で若年性認知症などの特定疾病による要介護認定を受けている方でも入所できます。一定の条件を満たすことで老健に入所できるのは、利用者やその家族にとって大きなメリットです。
医師常駐のため安心できる
老健には医師が常駐しており、何かあったときにすぐに対応してもらえるため、安心して入所できます。また、看護師も常駐している老健が多く、必要な医療措置をその場で受けられます。医薬品も施設内で処方してもらえるため、薬局まで出向く必要がなく大変便利です。
【入所者向け】老健を利用するときの注意点

老健は、入所期間が満了となったら退去しなくてはいけません。老健の入所期間は原則として3ヵ月です。3ヵ月を経過するごとに利用者が在宅復帰可能かどうかの審査があり、復帰可能であると判断されると退所する必要があります。退所となれば、自宅での家族の受け入れ態勢を早期に整える必要もあるケースも想定されます。
また、老健に入所中は介護保険と医療保険のどちらか一方しか使えません。老健に入所中に介護サービス以外の医療行為が必要になれば介護保険から給付が行われます。しかし、外部の医療機関に入院が必要となるような場合には、医療保険を使えるように一旦退所する必要が出てくるため注意が必要です。
【介護士向け】老健で働くメリット

老健で働くメリットには以下のようなものがあります。
- リハビリの知識がつく
- 身体的な負担が少ない
- 専門家がいるので安心して働ける
これから老健で働いてみたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
リハビリの知識がつく
老健で働くと、リハビリの知識が身につきます。特に、利用者の在宅復帰に力を入れている老健は、リハビリに関する業務がほかの介護施設より多いものです。そのため自然とリハビリについての知識が豊富になるので、スキルアップにもつながります。リハビリの知識を身につけることで、介護の現場においても、寝返る・起き上がる・立ち上がる・歩くといったような利用者の日常生活の基本動作改善をサポートできるようになります。
身体的な負担が少ない
老健は、ほかの介護施設に比べると身体的な負担が少ない施設です。老健の利用者は在宅復帰を前提に入所しており、介護の度合いが低い方が多いためです。体力に自信のない方でも、老健であれば介護職の仕事を長期にわたって続けられる可能性が高まります。
専門家がいるので安心して働ける
老健には、常駐の医師や看護師に加え、理学療法士・作業療法士など、それぞれの分野の専門家がいる施設です。緊急時でも指示を仰げるため、経験が少ない方でも安心して働けます。それぞれの分野の専門家が連携を図ることで迅速に問題解決ができれば、利用者の安心にもつながります。
【介護士向け】老健で働くときの注意点

老健では利用者の入所期間は原則3ヵ月と決まっており、長期間の介護を想定していません。短い期間で利用者が変わるため、顔なじみになった頃に利用者が退去してしまうようなことも珍しくありません。
1人の利用者に対して長くサポートするような働き方を希望している方は、注意が必要です。就職・転職後のミスマッチを防ぐため、老健で働く前に実際の仕事内容などをしっかり確認することが大切です。
老健と特養(特別養護老人ホーム)との違い

ここでは、よく比較される特養と老健の違いについて見ていきましょう。
特養とは「特別養護老人ホーム」の略です。以下の表のように、入所要件や入所のしやすさ、入所期間、主なサービス内容に違いがあります。
| 老健(介護老人保健施設) | 特養(特別養護老人ホーム) | |
| 主なサービス内容 | 医療ケアやリハビリを提供し、利用者の在宅復帰を目指す | 身体介護や生活支援を中心として、利用者の自立をサポートする |
| 入所要件 | 原則65歳以上で、要介護1以上 | 原則65歳以上で、要介護3以上 |
| 入所のしやすさ | 待機者は少なく、遅くても数ヶ月程度で入所できる | 待機者は多く、数ヶ月〜数年待つこともある |
| 費用 | 6〜20万円程度(入所一時金なし) | 6〜13万円程度(入所一時金なし) |
| 設備 | 日常生活の設備に加えて、リハビリ施設が充実 | 日常生活に必要な設備を完備 |
| 入所期間 | 原則3ヶ月 | 終身の利用可 |

老健(介護老人保健施設)は、在宅復帰を目的としたリハビリ中心の施設であり、利用者の状態や地域のニーズに応じて適切に選択・運営することが求められます。また、リハビリの充実と医療ケアの強化によって、在宅復帰支援の質を向上させることが求められます。入所者が短期間で必要なリハビリを受け、円滑に在宅復帰できるよう、スムーズな受け入れと退所支援を行うことが不可欠です。そのためには、多職種が連携し、医師や看護師、リハビリ専門職、介護職が一体となって支援する体制を整えることが重要になります。
特に老健では、在宅復帰率の向上が施設の評価にも直結するため、医療やリハビリの充実を図ることが大切です。老健の特性や強みを活かしながら、利用者とその家族にとって最適なケアを提供できるよう、適切な運営を心掛けることが求められます。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。
すでに介護ソフトを導入していている方も、介護ソフトの入れ替えを検討している方も、自身に最適なプロダクトを選ぶために重要な4つのポイントを解説していますので是非ご活用ください。
老健の種類の把握は適切な運営を実現するうえで不可欠

老健はリハビリに重点を置き早期の在宅復帰を目指す施設です。入所だけでなく、ショートサービスやデイケアなど利用者の状況に合わせた利用ができます。入所期間は原則3ヵ月と短いですが、短期間でリハビリの成果を出すための環境が整っています。また、医師等も常駐しており、緊急時に対応してもらえるので、利用者だけでなくその家族も安心できるでしょう。
働く方の視点では、老健の業務内容は身体的な負担が少ないため、体力に自信がなくても続けやすい仕事といえます。ただし、リハビリテーションなどと並行して、入所の手続きや施設の稼働状況の把握、介護報酬請求や入金管理などの事務作業をこなす必要があります。日々、数多くの業務を的確にこなさなければいけないため、業務の効率化が不可欠です。
例えば、「ワイズマンの介護ソフト(介護老人保健施設管理システムSP)」は、入所手続きから入金管理までのあらゆる業務の効率化が可能です。また、全老健版ケアマネジメント方式R4システムにも対応しています。
介護ソフトの資料請求や、デモンストレーションをご希望の方はこちらから簡単にお問い合わせいただけます。
2022年現在、全国の老健施設の約4割がワイズマンの介護老人保健施設管理システムSPを導入しています。より働きやすい職場環境を実現するために、今後こうしたソフトは介護の現場でより必要とされていくでしょう。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。