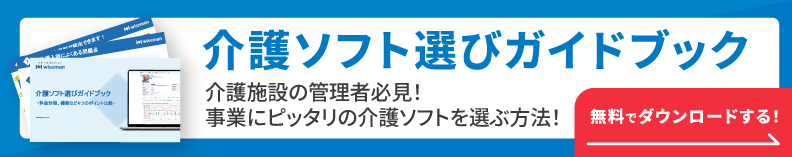老健(介護老人保健施設)のショートステイとは?特徴や1日の流れも解説
2023.06.01

短期入所療養介護(ショートステイ)とは、利用者が自宅で自立した日常生活を送れるよう、療養生活の質の向上と家族の介護の負担軽減などの目的で提供されるサービスのことです。
今回は老健のショートステイで働かれている方やこれから働こうと検討している方向けに、働く上でのメリットや注意点について解説します。ご自身の働く事業所に関する知識が深まりますので、ぜひ最後までお読みください。
なお、株式会社ワイズマンでは介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて「介護ソフト選びガイドブック」を無料配布しています。
介護ソフトの導入時によくある問題と対策についても記載していますので是非ご活用ください。
目次 [表示]
老健のショートステイとは?

ショートステイとは、短期間だけ施設に入居して介護サービスを受けることです。
特別養護老人ホームや有料老人ホームのほか、老健でも利用できます。
生活支援サービスを提供する生活短期入所生活介護と、生活支援のほか医療ケアを提供する短期入所療養介護の2種類があり、老健のショートステイは短期入所療養介護に分類されます。
なお、ショートステイは医療ケアを必要とする方も利用するため、老健や診療所が併設されていなければ運営できません。
老健のショートステイの特徴

老健のショートステイを利用するために必要な条件や利用期間、サービス内容についてあらためて確認しておきましょう。
利用できる方
老健のショートステイを利用できるのは、以下の条件に当てはまる方です。
- 65歳以上で要介護または要支援認定を受けた方
- 40歳以上64歳以下で特定疾病により、要介護認定を受けた方
要支援の認定を受けた方は、要介護状態への進行予防を目的とした介護予防短期入所生活介護が利用できます。
なお、老健以外の施設では、ショートステイを利用できる方の条件が微妙に異なる場合があります。
例えば有料老人ホームの場合、介護保険適用外のショートステイであれば要介護認定を受ける必要はありません。
利用できる期間
老健のショートステイは1泊2日から最大30日まで利用可能で、30日以上利用する場合は所定の手続きが必要です。
その場合、31日目は全額自己負担となり、翌日から介護保険が適用されます。なお、要介護度によって利用限度日数が定められています。
たとえ30日以内であっても、利用限度日数を超えた分は全額自己負担となるため、利用期間は事前に検討しておきましょう。
| 介護度 | 利用限度日数 |
| 要支援1 | 6日 |
| 要支援2 | 11日 |
| 要介護度1 | 17日 |
| 要介護度2 | 20日 |
| 要介護度3 | 28日 |
| 要介護度4 | 30日 |
| 要介護度5 | 30日 |
自己負担額
老健ショートステイの自己負担額は、要介護度や部屋のタイプ、自己負担割合によって異なります。
部屋のタイプは以下の3タイプがあります。
- 従来型個室(洗面台やトイレ付きの完全個室)
- 多床室(1床4部屋以下の相部屋)
- ユニット型個室(10人程度を1ユニットとした個室で共有スペースはユニット全員で使用)
部屋のタイプと要介護度別の自己負担額は以下のとおりです。
1日当たりの自己負担額(1割負担の場合)
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 |
| 要介護度1 | 752円 | 827円 | 833円 |
| 要介護度2 | 799円 | 896円 | 879円 |
| 要介護度3 | 861円 | 939円 | 943円 |
| 要介護度4 | 914円 | 991円 | 997円 |
| 要介護度5 | 966円 | 1,045円 | 1,047円 |
1日当たりの自己負担額(1割負担の場合)
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 |
| 要介護度1 | 1,504円 | 1,654円 | 1,666円 |
| 要介護度2 | 1,598円 | 1,792円 | 1,758円 |
| 要介護度3 | 1,722円 | 1,878円 | 1,886円 |
| 要介護度4 | 1,828円 | 1,982円 | 1,994円 |
| 要介護度5 | 1,932円 | 2,090円 | 2,094円 |
1日当たりの自己負担額(3割負担の場合)
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 |
| 要介護度1 | 2,256円 | 2,481円 | 2,499円 |
| 要介護度2 | 2,397円 | 2,688円 | 2,637円 |
| 要介護度3 | 2,583円 | 2,817円 | 2,829円 |
| 要介護度4 | 2,742円 | 2,973円 | 3,988円 |
| 要介護度5 | 2,898円 | 3,135円 | 3,141円 |
提供できるサービス内容

老健ショートステイでは、以下のサービスを提供します。
- 症状の確認と療養上の世話
- 装着されている医療機器の調整・交換
- リハビリテーション
- 認知症利用者のケア
- 緊急時の受け入れ
- 急変時対応
- ターミナルケア
- 日常生活上の世話・介護
- 生活相談・助言
それぞれのサービス内容について、しっかり確認しましょう。
病状の確認と療養上の世話
利用者の病状や負傷状態の確認や処置・経管栄養や痰吸引・インスリン注射などの療養上の世話を行います。
老健には医師や看護師が常駐しているため、医療ケアの提供が可能です。
また、高齢の利用者の場合、服用している薬の自己管理を適切にできないケースがあります。
そのため、老健では内服薬の管理も行うなど、利用者の健康維持のサポートも老健の重要な役目です。
なお、施設によってはより高度な医療ケアを提供している場合もあります。
ただし、老健は医療機関ではないため、手術やX線検査のような特定の設備が必要な医療行為や、高度な服薬・注射などには対応していないことが一般的です。
装着されている医療機器の調整・交換
利用者が使用している医療機器の調整・交換を行います。
老健では持病を持つ利用者のために必要な各種ケアに加え、在宅酸素療法・ストーマ器具の交換・人工呼吸器の管理など、専門的な処置も実施されます。
いずれも医者や看護師でなければ対応できない処置であるため、介護スタッフによる代行はできません。
リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職が機能回復訓練やリハビリテーションを行います。
老健は複数の専門職が在籍しているため、ほかの介護施設と比較してリハビリテーションに多くの時間を費やせる点が特徴です。
リハビリテーションは利用者の健康状態に合わせ、適切な計画を立てて実践することが重要です。
利用者の在宅復帰のタイミングを左右するサービスであるため、利用者に合わせた具体的な目標を設置し、効果的なケアを提供する必要があります。
認知症利用者のケア
認知症利用者を受け入れできる老健は多く、専門的なケアを提供する施設も珍しくありません。
特に複数の利用者が同居するユニット型は、利用者の顔見知りを集められるので、環境の変化による影響を最大限抑えられます。
緊急時の受け入れ
突発的な家庭の事情により、在宅介護ができない場合の受け入れを行います。
老健は24時間スタッフが常在しているため、ケアプランにない緊急時の受け入れに対応しやすい施設です。
ただし、老健では手術やMRIの利用などのような、高度な医療行為には対応できません。
そのため、利用者の状態によっては受け入れができないケースもあります。
急変時対応
施設利用中に利用者の急変があった場合、医師の判断で協力医療機関に対して診察依頼または専門機関の紹介を行います。
利用者の急変時対応は、老健に求められる重要なサービスの一つです。
多職種で連携し、スムーズな対応を心がけましょう。
近年は老健と医療機関のより緊密な連携強化が課題となっています。
厚生労働省の分科会でも、老健を含めた高齢者施設と医療機関のさらなる連携強化が議論されました。
その過程でICT化によるD X推進が、効果的な対策として挙げられています。
参照:高齢者施設等と医療機関の連携強化(改定の方向性)|厚生労働省
ターミナルケア
終末期を迎えた利用者のケアおよび看取りを行います。
在宅復帰を目指す老健において、本来ターミナルケアは必須のサービスではありません。
しかし、近年は多職種が連携する老健にターミナルケアや看取りのサービスを求める利用者が増えています。
その影響もあり、昨今はターミナルケアを提供する老健が増加しました。
老健のターミナルケアは、在宅復帰後にショートステイなどを利用して受けるケースが一般的です。
通常の介護サービスの延長線上で実施されますが、医師や看護師を含めた多職種のサポートを提供できる、利用者が必要な医療ケアを受けられる点がメリットです。
関連記事:「老健のターミナルケア加算とは?算定要件や注意点などを解説」
日常生活上の世話・介護
食事・入浴・排泄介助など日常生活に必要な支援を行います。
老健では利用者が不自由なく過ごせるよう、日常生活上の世話や介護を提供することが求められます。
さらに老健は利用者100人に1人につき、栄養士を配置しなければならないうえに、毎日の食事は栄養士の監修が必須です。
また、利用者の持病や嚥下能力に合わせてメニューを提供する必要があります。
生活相談・助言
自宅での療養生活に関する相談受付およびアドバイスを行います。
生活相談や助言の対象は利用者だけではありません。
利用者の家族も生活相談・助言の対象であり、在宅復帰後の対応や適切なサポートの方法をアドバイスすることも、老健の重要な役目です。
もちろん、利用者の家族の介護に対する不安や疑問を解消することも欠かせません。
なお、株式会社ワイズマンではすでに介護ソフトを導入しているが、介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて、「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。ダウンロードしてご活用ください。
老健のショートステイの仕事内容

老健のショートステイでは、サービスの提供を行うために以下のような専門職員が働いています。
- 医師
- 看護師や准看護師
- 機能訓練指導員
- 介護職員
- 栄養士や調理師
- 生活相談員
- 施設管理者
本章では、それぞれの専門職員の仕事内容について解説するので、ぜひ参考にしてください。
医師
利用者の健康管理や指導、相談の受付を行います。
老健における医師は、医学的な見地から利用者の健康状態を管理し、適切な医療ケアを提供することが求められます。
老健に配置される医師は施設管理医とも呼ばれ、利用者の診断・治療を行いつつ、看護師・准看護師や機能訓練指導員への指示を出します。
老健において、医師は単純な指示役ではありません。
医師は多職種が在籍するチームを調整、運用するコーディネーターのような役割を担っています。
看護師や准看護師
利用者に対する医療的ケアのほか、バイタルチェックや医療的処置、服薬管理を行います。介護職員と協力して業務を行うこともあります。
老健の看護師・准看護師は多職種との連携に加え、介護的な視点からも利用者のサポートを実施する役目です。
そのため、実際にケアを提供するチームのリーダーのような立場になるケースも珍しくありません。
もちろん、通常の看護師・准看護師のように医師が提供する医療ケアのサポートも行います。
機能訓練指導員
機能訓練指導員は、在宅復帰のスピードを左右する重要な職種です。
利用者の状態に合わせた機能的訓練を計画・実施するほか、生活機能の維持や回復に努めます。
機能訓練指導員に該当する職種には、以下のようなものがあります。
| 理学療法士(PT) | 日常的な動作を中心とした運動機能の回復・維持をサポートする。 |
| 作業療法士(OT) | 手の動きなど身体的機能に加え、社会的適応力のような精神的機能の回復・維持をサポートする |
| 言語聴覚士(ST) | 発話機能のような言語コミュニケーションや嚥下能力などの回復・維持をサポートする。 |
老健では、上記のような専門性を持った職種が、利用者の状態に合わせた適切なサポートを提供します。
介護職員
利用者の入浴・排泄・食事など身体介助のほか、レクリエーションの企画や実施を行います。
介護職員は老健における福祉系の職員の中心となる職種です。
ただ介護サービスを提供するだけでなく、多職種と協働し、より充実したサービスを提供することが求められます。
栄養士や調理師
利用者の健康状態や既往歴に合わせた献立の作成のほか、食事形態の調整を行います。
栄養者・調理師もまた、多職種と連携したサービスを提供する職種です。
多職種と協働し、利用者の状態を踏まえて献立を作成することにより、利用者の食事面を全般的にコーディネートする必要があります。
例えば嚥下能力が低い利用者には、言語聴覚士と連携して献立を考案するなど、場面に応じた柔軟に対応することが求められます。
生活相談員
新規利用者の受け入れ、利用者やご家族の生活相談、レクリエーションの企画を行います。
また、利用者が受けるサービスの契約の手続きを実施することや、老健に在籍する多職種だけでなく公的機関との連携なども、生活相談員の仕事です。
生活相談員はケアマネージャーと混同されますが、実際は異なる職種です。
ケアマネージャーは利用者の状況や家族のニーズに合わせたケアプランの作成が主な役目です。
対して、生活相談員は施設の利用者を対象としたサービスを提供します。
施設管理者
利用者やご家族の対応、設備管理や収支管理、関係機関との連絡・調整を行います。
施設管理者は施設運営に必要な業務だけでなく、多職種それぞれの立場を踏まえたうえで、適切なマネージメントを実施する職種です。
加えて、災害などの非常事態が発生した際に、利用者やその家族への説明や、関係各所への指示出しを行うことも、施設管理者の重要な仕事です。
なお、老健の施設管理者は原則として医師である必要があります。
ただし、施設の状況によっては医師以外の職種が施設管理者を担ったり、兼務が許されたりする場合があります。
老健のショートステイの1日の流れ

老健のショートステイで働く介護職員の1日の流れを紹介します。
| 時刻 | 業務 | 業務内容 |
| 8:00 | 出勤 | 夜勤者の申し送り、情報共有、予定確認 |
| 9:00 | 口腔ケア、入浴準備 | 食事を終えた利用者の口腔ケア、入浴準備 |
| 10:00 | 機能訓練 | 必要に応じて補助を行う |
| 11:00 | 排泄介助 | 排泄介助やバイタルチェック |
| 12:00 | 昼食、口腔ケア | 配膳・食事介助・服薬介助・口腔ケア |
| 14:00 | レクリエーション | 利用者の誘導、準備・後片付け |
| 15:00 | ティータイム | 菓子やお茶の提供、食事介助・後片付け |
| 16:00 | 送迎 | 帰宅される方の送迎 |
| 16:40 | 介護記録、清掃 | 利用者の様子を記録、施設の清掃・後片付け |
| 17:00 | 退勤 | 夜勤者への引継ぎを行い、退社 |
なかでも介護記録は重要です。利用者が受けた介護サービスはもちろん、その日の健康状態や活動状況などを記録します。介護記録の記載や保存は介護保険法で定められていることや、申し送りの際に情報が正しく不足なく共有できるように記録しなくてはいけません。
手書きで記録を残す場合は、時間も手間もかかってしまい、記入ミスの懸念もあります。そのため、ケア記録支援ソフトなどを上手に活用すると日々の記録がスムーズに行えます。
ワイズマンの施設・特定施設・通所サービス向け ケア記録支援ソフトは、利用者様の健康状態や介護状況をその場で記録・参照できます。ソフトの詳細は以下からご覧ください。
>>「施設・特定施設・通所サービス向け ケア記録支援ソフト」

介護老人保健施設(老健)のショートステイは、在宅介護を支える重要なサービスの一つです。要介護者が短期間入所し、医療ケアやリハビリ、生活支援を受けることで、自立した生活の維持や家族の介護負担軽減を目的としています。特に医師や看護師が常駐し、医療依存度の高い利用者の受け入れが可能である点が、他の短期入所施設との大きな違いです。
老健のショートステイでは、多職種が連携し、利用者の健康状態やADL(日常生活動作)に応じた適切なケアを提供します。具体的には、バイタルチェックや服薬管理、リハビリテーション、認知症ケア、ターミナルケアなど、包括的な支援が行われます。
短期間の利用でも、適切なケアプランのもとで生活機能の維持・向上を図ることが求められます。そのため、医療と介護の連携を強化し、利用者にとって最適な環境を提供することが重要です。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。
すでに介護ソフトを導入していている方も、介護ソフトの入れ替えを検討している方も、自身に最適なプロダクトを選ぶために重要な4つのポイントを解説していますので是非ご活用ください。
利用者により良いサービスを提供するうえで老健のショートステイは重要

老健のショートステイが持つ特性上、利用者の情報は常に最新に保つ必要があります。利用者の医療依存度が高いうえに、短期間で入れ替わりが繰り返されるためです。
また、さまざまな職種が利用者のケアに関わるため、情報共有にはスピードが重要です。特に夜間に急変した際の対応遅れは、利用者の生命にかかわります。
こういった環境でも、介護ソフトを導入しておくことで、バイタル測定値をタブレット端末に直接反映させることができます。タブレット端末から記録が行えることで、情報共有の効率化も図ることができます。
さらに見守りシステムを活用すれば、夜勤職員の定期巡回の負担軽減につながるうえ、寝ている利用者を起こしてしまうこともありません。
もし、今働かれている事業所で介護ソフトが導入されておられないようでしたら、業務効率化を図れるように担当者に導入を相談してみてください。
介護ソフトの資料請求をご希望の方は、こちらから簡単にお問い合わせいただけます。お気軽にお問い合わせください。
>>「介護老人保健向けソフト(介護老人保健施設管理システムSP)」
>>「短期入所生活介護事業所向け介護ソフト(短期入所生活介護管理システムSP)」

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。