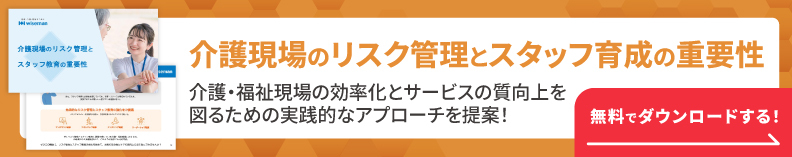処遇改善加算とは?仕組みや種類から取得における注意点まで徹底解説
2024.12.19

処遇改善加算の複雑な仕組みがよくわからない
2024年の制度改正への対応が不安
職員の待遇改善を図りたいけれど、具体的な方法がわからない
介護業界では深刻な人材不足が続いており、多くの施設長や管理者の方々が職員の確保と定着に頭を悩ませています。
処遇改善加算は、この課題を解決するための制度ですが、その仕組みや申請手続きの複雑さに戸惑う方も少なくありません。
本記事では、処遇改善加算の基本的な仕組みから2024年度の制度改正のポイント、具体的な申請手続きまで、現場の管理者の視点に立って詳しく解説します。
制度を正しく理解し、適切に活用すれば、職員の待遇改善と人材確保の両立を実現できるでしょう。
効率的な運用方法を学ぶことで、事務作業の時間を半分以下に削減できます。職員の待遇改善を着実に進め、人材確保・定着の成果を上げていきましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは、介護現場でのリスク管理やスタッフの教育について課題を感じている方に向けて「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場の効率化とサービスの質向上を図るための実践的なアプローチを提案しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
処遇改善加算とは?仕組みと種類をわかりやすく解説

処遇改善加算とは、介護職員のキャリアアップの仕組みづくりや職場環境の改善に取り組む事業所に対して支給される介護報酬の加算制度です。
介護人材の確保と定着を目的とし、職員の待遇改善に活用できます。
介護業界では長年、人材の確保と定着が大きな課題となってきました。
この課題に対応するため、2009年に介護職員処遇改善交付金が創設され、介護報酬への上乗せ支給という形で処遇改善対策が開始されました。
その後、2012年には現在の介護職員処遇改善加算として制度が整備され、より体系的な人材育成の仕組みへと発展しています。
制度の導入により、事業所では以下のような取り組みが可能になりました。
- 職員の給与水準の改善
- キャリアパス制度の整備
- 職場環境の改善
- 研修体制の充実
- 福利厚生の拡充
処遇改善加算を活用した事業所では、さまざまな形で職員の待遇改善が実現されています。
例えば、資格取得支援制度を導入し、職員のスキルアップを支援する事業所が増えています。
職場環境の面では、休暇取得の促進や労働時間の適正管理など、働きやすい環境づくりに取り組む事業所が増加中です。
処遇改善加算は、単なる給与改善の制度ではありません。
職員のやりがいを高め、キャリア形成を支援し、働きやすい職場環境を整備するための総合的な取り組みを後押しする制度といえるでしょう。
訪問介護事業所における処遇改善加算の詳細については「訪問介護における処遇改善加算|単位数・計算方法や算定要件を解説」をご覧ください。
処遇改善加算の基本的な仕組み
処遇改善加算は、介護サービス事業所の介護報酬に一定割合を上乗せして支給される制度です。
この加算を通じて、職員の賃金改善ができる仕組みとなっています。
職員の待遇改善を運用する主な流れは、以下のとおりです。
| 加算の算定方法 | 介護報酬に一定割合(加算率)を上乗せ 毎月の介護報酬と一緒に事業所へ支給 継続的な支給により安定した運用が可能 |
| 加算金の使途 | 受け取った加算額は全額を賃金改善に充当 基本給、手当、賞与など給与面での改善 計画に基づいた配分の実施 |
このように処遇改善加算は、介護報酬への上乗せ支給という形で、確実に職員の待遇改善につながる仕組みとなっています。
処遇改善加算の種類と加算区分
処遇改善加算は、事業所の取り組み状況に応じて3つの区分があり、要件を多く満たすほど職員1人当たりの支給額が増える仕組みです。
加算額は、介護職員数をもとに算出される「加算率」と事業所の総報酬から計算されます。
職員の育成や職場環境の改善に積極的に取り組む事業所ほど、より多くの加算を受けられます。
加算区分による支給額や要件をまとめると以下のとおりです。
| 加算区分 | 支給額(1人当たり月額) | 要件 |
| 加算(Ⅰ) | 37,000円相当 | ①経験・資格に応じた昇給の仕組み ②職位・職責に応じた任用要件 ③資質向上の研修計画すべてを満たす |
| 加算(Ⅱ) | 27,000円相当 | ①経験・資格に応じた昇給の仕組み ②職位・職責に応じた任用要件2つを満たす |
| 加算(Ⅲ) | 15,000円相当 | ①か②のどちらか1つを満たす |
このように、段階的な区分により、事業所は現在の体制に合わせた加算を選択できます。
また、より上位の区分を目指して計画的に取り組みを進めることで、職員の待遇改善を段階的に実現できる仕組みとなっています。
制度の目的
介護業界では、人材の確保・定着が長年の課題となっています。
その解決に向けて、この制度では主に3つの目的を掲げています。
具体的な目的は、以下のとおりです。
| 介護職員の賃金水準向上 | 他産業と比較して低い賃金水準の改善 安定的な収入の確保 |
| 介護人材の確保・定着の促進 | 新規人材の採用促進 既存職員の定着率向上 キャリアパスの明確化 |
| 介護サービスの質の向上 | 職員の意欲向上 安定的なサービス提供 利用者満足度の向上 |
このように処遇改善加算は、単なる賃金改善だけではなく、介護業界全体の発展を見据えた制度となっています。
職員の待遇改善を通じて、介護サービスの質を高め、業界全体の底上げを図ることを目指しています。
2024年度の処遇改善加算改正のポイント

2024年度の処遇改善加算改正では、介護職員の処遇改善を目的に、これまでの加算制度が大幅に見直されました。
ここでは2024年度の主な改正ポイントとして、以下の2つを解説します。
- 処遇改善加算の算定要件と対象者
- 処遇改善加算の新たな賃金配分ルール
それぞれ詳しく説明します。
処遇改善加算の算定要件と対象者
2024年6月からの新制度では、これまでの3つの加算が一本化され、4段階の新しい加算体系となります。
新制度は、事業所の取り組み状況に応じて段階的な加算率を設定し、より充実した処遇改善を目指しています。
新制度の加算区分と要件は、以下のとおりです。
| 新加算区分 | 加算率 | 主な要件 |
| 加算(Ⅰ) | 22.4% | 経験技能のある介護職員を一定割合以上配置(訪問介護:介護福祉士30%以上) 加算(Ⅱ)の要件もすべて満たす |
| 加算(Ⅱ) | 18.2% | 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上職場環境の更なる改善、見える化 加算(Ⅲ)の要件もすべて満たす |
| 加算(Ⅲ) | 14.5% | 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備 加算(Ⅳ)の要件もすべて満たす |
| 加算(Ⅳ) | 12.4% | 加算額の7.2%以上を月額賃金で配分 職場環境の改善 賃金体系等の整備及び研修の実施 |
新制度により、事業所は自らの状況に応じた加算区分を選択しつつ、より上位の区分取得を目指して計画的に取り組みを進められます。
加算率は段階的に設定されており、要件を満たすことで着実な処遇改善を実現できる仕組みとなっています。
処遇改善加算の新たな賃金配分ルール
2024年6月から、処遇改善加算の賃金配分ルールが大きく変わります。
よりわかりやすく、使いやすい仕組みへと変更されます。
これまでは処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算と3つの異なる加算制度が存在し、それぞれに配分ルールがありました。
この複雑な仕組みを整理し、事業所の事務負担を軽減するため、制度が一本化されることになりました。
新制度での主な変更点は、以下のとおりです。
| 新しい配分ルールの特徴 | 経験・技能のある職員に重点配分 事業所の判断で職種間の柔軟な配分が可能 |
| 移行期間の配慮 | 2024年6月~2025年3月は経過措置期間 急激な変更による影響を緩和 段階的に新制度へ移行 |
| 今後の予定 | 2025年4月から新制度に完全移行 新しい賃金体系の整備が必要 |
制度改正により、事業所の運営管理者の負担が減り、職員にとっても理解しやすい仕組みとなります。経過措置期間を活用して、計画的な準備を進めることが必要です。
なお、介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方に向けて、「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
処遇改善加算の申請手続き

処遇改善加算を適用するためには、事業所ごとに申請が必要です。
ここでは、申請の流れや必要書類について解説していきます。
申請での全体の流れ
処遇改善加算の申請は、2024年度は新旧制度の移行期となるため、特に注意が必要です。
年間を通じた計画的な手続きが求められます。
申請から実績報告までの一連の流れを適切に実施すれば、確実な加算の取得と職員への処遇改善を実現できるでしょう。
2024年度の主な手続きの流れは、以下のとおりです。
| 計画段階(4月期限) | 処遇改善計画書の作成 全職員への計画内容の周知 計画書の提出(4月15日締切) ※新加算は6月15日まで変更届出が可能 |
| 体制の整備 | 加算変更に伴う体制届の提出 指定権者の定める期限を要確認 必要書類の準備 |
| 実施・報告段階 | 計画に沿った施策の実行(年度中) 実績報告書の作成(翌年4月~) 報告書の提出(翌年7月31日締切見込) |
手続きを円滑に進めるため、厚生労働省が提供する専用書式や参考資料の活用をおすすめします。
また、指定権者によって独自の書式が定められている場合もあるため、必ず確認が必要です。
事業所の規模に応じた計画書や、初めて取得する事業所向けの書式など、さまざまな資料が用意されているため、自事業所に適した様式を選択しましょう。
詳しくは、厚生労働省の「令和6年度の申請方法・申請様式」を確認してください。
必要書類
処遇改善加算の申請には、算定前の届出書類と算定後の実績報告書の提出が必要です。
特に2024年度は制度改正に伴い、すべての事業所で体制届の提出が求められます。
適切な処遇改善を実施し、確実に加算を受けるためには、各書類を期限内に漏れなく提出しなければなりません。
必要期限と提出書類をまとめると以下のとおりです。
| 提出時期 | 必要書類 | 注意事項 |
| 算定前 | 処遇改善計画書体制等状況一覧表(体制届) | 2024年6月以降は全事業所で体制届が必要 事業規模や区分で様式が異なる |
| 算定後 | 実績報告書 | 新規届出の初年度は提出不要 事業規模で様式が異なる |
各書類は事業所の規模や算定する区分によって様式が異なります。
必ず事業所に適した様式を使用し、指定された期限までに提出するようにしましょう。
処遇改善加算取得における注意点

処遇改善加算取得において、以下のような注意点があります。
- 事業所別の加算率の違いと確認方法
- 加算の対象とならないケースと対象職員
- 効率的な加算管理
それぞれ詳しく説明します。
事業所別の加算率の違いと確認方法
処遇改善加算の金額は、サービス種別ごとに定められた加算率と、事業所の介護報酬に基づいて計算されます。
適切な収入計画のためには、自事業所の加算率を正確に把握する必要があります。
加算額の計算の主な流れは以下のとおりです。
- 月の総単位数を算出(処遇改善加算分を除く)
- 総単位数に加算率を乗算
- 算出された単位数に地域区分単価を乗算
加算率は、サービス種別や加算区分によって異なります。正確な加算率は、厚生労働省が公表している「別紙1表1-1、表1-2」で確認できます。
また、2024年4・5月は旧制度の加算率が適用されるため、別途確認が必要です。
加算額の試算の際は、必ず最新の公式資料で自事業所のサービス種別の加算率を確認し、直近の介護報酬実績をもとに計算し、より正確な収入見込みを立てるようにしましょう。
移行期の収入変動にも注意が必要です。
加算の対象とならないケースと対象職員
処遇改善加算はすべての介護事業所・職員が対象となるわけではありません。事業所の種類や職種によって対象外となるケースがあります。
この加算は介護職員の処遇改善を目的としており、改正により、すべての職種への配分が認められるようになっています。
例えば、訪問看護ステーションは看護師が中心となってサービスを提供するため、加算の対象外です。
職員についても、直接介護サービスの提供に関わる職員のみが対象です。
ただし、雇用形態による区別はなく、常勤職員はもちろん、非常勤やパートタイム職員も同様に加算の対象となります。
対象になるケースと対象外のケースをまとめると以下のとおりです。
| 対象 | 対象外 | |
| サービス事業所 | 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護 特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 など | 訪問看護 訪問リハビリテーション 福祉用具貸与/販売 居宅療養管理指導 居宅介護支援 介護予防支援 |
| 職員 | 介護職員(直接介護に従事) 常勤/非常勤/パート問わず | ケアマネージャー 生活相談員 栄養士 事務員 |
処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的とした制度であり、受け取った加算は介護職員の賃金改善に充てる必要があります。対象となる職員の範囲を正しく理解し、適切な賃金改善計画を立てることが必要です。
非対象職員への配分は認められていないため、事業所は慎重な運用が求められます。
※参照:介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)|厚生労働省
効率的な加算管理
処遇改善加算の運用には、計画書の作成から実績報告まで、継続的な書類管理が必要です。効率的な管理体制を整えれば、事務負担を軽減し、確実な運用が可能となるでしょう。
加算に関する書類作成や管理は煩雑になりやすく、特に給与計算や実績管理には多くの時間と労力が必要です。
例えば、毎月の給与計算時に加算額の振り分けを手作業で行うと、ミスが発生するリスクが高まります。
職員の入退職や勤務時間の変更があった際の調整作業も大きな負担となるでしょう。
これらの業務を効率化すれば、運営管理者の負担を減らし、より明確な処遇改善の実施につながります。
効率的な加算管理の主なポイントは、以下の3つが挙げられます。
| 書類作成・管理の効率化 | 計画書や報告書の雛形を作成し、記入方法を手順書化 提出書類や記載事項の漏れを防止 過去の書類をすぐに参照できる整理方法の確立 年間スケジュールを可視化 |
| ICTツールの活用 | 給与計算ソフトの導入 クラウド型の文書管理 スケジュール管理 ツールの利用記録・報告のデジタル化 |
| 職員への配分管理 | 職員の経験年数や資格に応じた配分基準の設定 毎月の給与計算を自動化 四半期ごとの実績チェックの実施 |
このような効率的な管理体制を構築できれば、書類の作成ミスや提出遅れを防ぎ、確実な加算の取得・運用が可能となります。
特に、ICTツールを活用すれば、給与計算や書類作成にかかる時間を削減できます。例えば、給与計算ソフトの導入により、複雑な加算額の計算を自動化し、作業時間の短縮と正確性の向上を実現できるでしょう。
定期的な確認と見直しを行いながら、事業所に合った効率的な管理体制を構築していくような運用が大切です。

「今後介護報酬があがることはありません」と、ある厚労省関係者は断言していました。人口は減少し、高齢者は増え続ける日本の現状を考えると、何の違和感もありません。基本報酬を緩やかに下げつつ、加算報酬を新設・拡充していくのが、厚労省の常套手段となっています。実際にプラス改定後も介護事業者の収益が上がらないのは、基本報酬が減り、要件の難しい加算を算定できない事業所が多いことが要因に挙げられます。介護事業においては加算算定の重要性は増す一方です。処遇改善加算に限らず、加算は取りこぼすことなく、なるべく上位区分を算定することが、介護事業経営の基本です。処遇改善加算の上位区分は、事業規模が大きくないとなかなか算定が難しいものとなっており、こうした面でも国は介護事業の大規模化へ誘導していることがわかります。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
処遇改善加算を理解し人材不足解消につなげよう
処遇改善加算は、介護職員の待遇改善を通じて、人材確保と定着を促進するための制度です。
2024年6月からの制度改正では、これまでの3つの加算制度が一本化され、よりわかりやすく、使いやすい仕組みへと変更されます。
この制度の基本的な仕組みは、介護報酬に一定割合を上乗せして支給され、それを職員の賃金改善に充てることで、継続的な待遇改善を実現します。
毎月の介護報酬と一緒に支払われることで、安定的な運用が可能です。
2024年度の制度改正では、加算率や要件が明確化され、事業所の取り組み状況に応じた4段階の区分が設定されました。この新しい仕組みにより、事業所は自らの状況に合わせて適切な区分を選択できます。
ただし、実務面では注意すべき点もあります。サービス種別によって加算率が異なること、対象となる事業所や職員の範囲が限定されていることなどを正しく理解しなければなりません。
また、関連する書類の作成や管理を効率的に行うことも大切です。
新制度への移行期間を有効に活用し、必要な準備を計画的に進めることで、より充実した職員の処遇改善を実現できます。
処遇改善加算を効果的に活用し、職員が安心して働き続けられる環境づくりを進めていきましょう。

監修:伊谷 俊宜
介護経営コンサルタント
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。