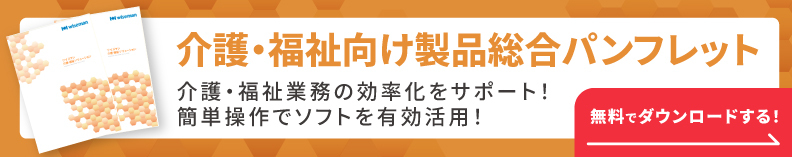地域包括ケアシステムの取り組み事例5選!仕組みやポイントを解説
2025.04.27

地域包括ケアシステムの取り組みは、高齢化が進む日本において避けては通れない課題です。
介護施設や在宅支援を担う現場では、介護職員の人手不足や医療との連携の難しさなどが主な課題です。
そんな中、各地の自治体では、地域の実情に合わせた創意工夫で、ケアの質を高める取り組みが実践されています。
本記事では、全国の先進事例を5つ紹介しながら、地域包括ケアシステムの仕組みや構成要素、4つの助、実行のためのポイントなどを解説します。
自施設でも活用できるポイントを見つけ、より良い介護体制の構築につなげていきましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
目次
地域包括ケアシステムの取り組み事例5選
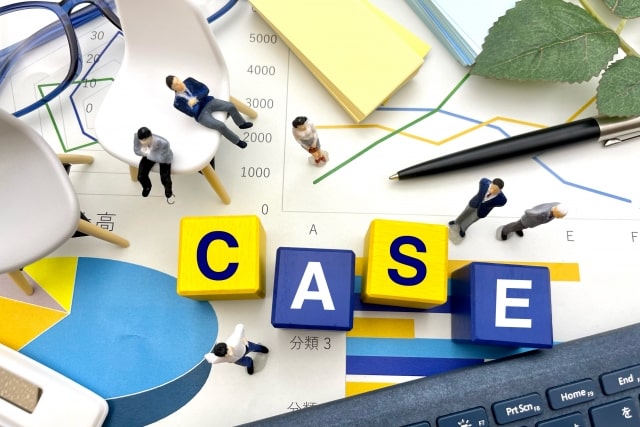
ここでは、厚生労働省の先行事例の中から、実際の現場でも参考にしやすい5つの取り組みを紹介します。自社施設で地域包括ケアを実践するうえでの参考として、ぜひご活用ください。
参考:地域包括ケアシステム構築へ向けた取組事例|厚生労働省
【熊本県上天草市】ICT活用で医療・介護の情報共有を効率化
熊本県上天草市の湯島地区では、高齢化率が50%を超える中、地理的な制約から十分な介護サービスが受けられない課題を抱えていました。
そこで、地域の住民が主体となり、高齢者が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるよう、在宅生活の基盤づくりに本格的に取り組んでいます。
この取り組みでは、以下のような活動が実施されました。
- 住民による検討委員会を立ち上げ、全世帯へニーズ調査を実施
- 介護予防拠点として、島内の旅館を改修し「つどい処よんなっせ」を整備
- 島内で11名のホームヘルパーを養成し、地域の介護力を確保
- 高齢単身世帯など31世帯に緊急通報システムを無償設置し、見守り体制を強化
- 裁縫や茶話会、体操など、住民が主体となった介護予防活動を定期開催
特に印象的なのは、住民自身が声を上げ、支え合う仕組みを一から作り上げたことです。
「島内で住み続けたい」の想いを大切に、福祉サービスや介護予防を地域全体で支える姿勢が、多くの地域のモデルになる取り組みと言えるでしょう。
【新潟県長岡市】小地域完結型のサポートセンターを活用
長岡市では、地域の高齢者が住み慣れた環境で安心して暮らせるよう「小地域完結型」の支援体制を構築しています。
この取り組みが重要なのは、施設でも自宅でもない「第三の選択肢」として、地域に根ざした暮らしを継続できる環境を整えている点にあります。
住み慣れた町内で、必要な支援を切れ目なく受けられる体制は、将来の利用者層となる団塊世代にとっても安心材料です。
実際には、以下のような工夫がされています。
- 市内に13カ所のサポートセンターを設置
- 医療・介護・住まい・予防・生活支援をワンストップで提供
- 地域包括支援センターや民間の配食・生活支援事業者と連携
- 地元住民との交流を目的に、祭りやイベントの場を共有
- 小規模多機能施設が地域の子どもたちの遊び場にもなっている
サービスの質や利便性だけではなく、地元住民との信頼関係づくりにも注力していることが特徴です。施設を開放して町内会の会合に利用してもらうなど、地域との距離を縮める工夫が随所に見られます。
地域との共生を前提にした運営スタイルは、今後の介護サービスの新しい形として注目されており、多くの自治体にとって参考になる事例です。
【三重県四日市市】在宅医療と介護の連携強化で在宅ケアを推進
高齢者の孤立を防ぎ、住み慣れた地域で暮らし続ける環境を整えるためには、地域の力を結集した包括的な支援体制が必要です。
四日市市では、社会福祉法人や自治会と連携し、空き店舗を活用した「孤立化防止拠点」を整備するなど、医療・介護・生活支援を地域全体で支えるモデルを構築しています。
取り組みのポイントは、地域に根差した既存の資源を活かしながら、住民同士のつながりを深め、支援のネットワークを広げている点です。社会福祉法人が中心となり、地域住民の自主的な活動と組み合わせることで、持続可能な支援体制を実現しています。
具体的な内容は、以下のとおりです。
- 大型団地内の空き店舗を活用し、地域の「集いの場」として再生
- 総合相談、食の確保、見守りなどを担う孤立化防止拠点を設置
- 地域住民・自治会が主体の会員制組織「ライフサポート三重西」を設立
- 配食サービスや買い物支援など、安価で柔軟な日常生活支援を提供
- 市や地域包括支援センターが側面支援を実施し、活動基盤を支える
上記取り組みにより、高齢者の閉じこもり防止や生活支援が推進され、地域全体で支え合う文化が根付いてきています。
今後は、成功したモデルを他地域にも展開し、面的な広がりを持たせることが期待されています。
【東京都世田谷区】都市型地域包括ケアの成功モデル
都市部であっても、高齢者が安心して暮らし続けられる地域包括ケアの実現は可能です。
東京都世田谷区は、行政と地域住民、NPOや企業など多様な主体が連携し、都市型の地域包括ケアモデルを確立しています。
世田谷区の特徴は、5つの構成要素(医療・介護・予防・住まい・生活支援)をバランスよく取り入れた体制づくりにあります。
主な取り組みは、以下のとおりです。
| 医療 | 在宅医療の体制整備を目的に、医療連携推進協議会を設置 |
| 介護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及を推進 |
| 予防 | 高齢者の居場所づくりや社会参加による介護予防の推進 |
| 住まい | 認知症高齢者グループホームや都市型老人ホームの整備 |
| 生活支援 | 住民団体・社会福祉協議会が主体となった支援活動の展開 |
約70の団体が連携する「せたがや生涯現役ネットワーク」が立ち上がり、高齢者が役割を持って社会と関わり続けられるような環境づくりも進んでいます。
都市部の高齢化に対応しながら、地域資源を活かし、持続可能なケアの仕組みを築いている点で、世田谷区は他自治体にとっても参考になる先進事例と言えるでしょう。
【鳥取県南部町】地域ぐるみの介護予防で高齢者支援を強化
鳥取県南部町では、地域の力を活かして、低所得の高齢者や独居高齢者でも安心して暮らせる仕組みを構築しています。
この地域では、既存の空き家や公的施設を改修し「地域コミュニティホーム」として活用しています。
生活支援サービスや見守り、配食を地域住民が担い、必要に応じて外部の医療・介護サービスを組み合わせる体制が整えられました。
特に、LSA(ライフサポートアドバイザー)が中心となり、随時相談に応じる体制が整備されています。
主なポイントは、次のとおりです。
- 空き家を活用した低所得者向けの住まい整備
- 配食・見守りなどの生活支援を地域ボランティアが担う
- 医療機関や介護事業所と必要なサービスを連携
- 地域交流スペースを備えた共同生活で孤立を防止
- 施設運営は、町の補助と家賃収入で費用を抑えた持続可能な仕組み
取り組みにより、年金暮らしの高齢者でも自宅のように安心して暮らせる環境が構築されました。事業は地域主導で進められており、行政は補助金とマッチング支援でバックアップしています。
南部町のような中山間地域では、住民主体の仕組みづくりが必要です。他の自治体にとっても、介護予防と住まいの両立をめざす好事例と言えるでしょう。
地域包括ケアシステムの仕組み

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように設計された支援体制です。医療や介護、予防、住まい、生活支援などの要素を一体的に整備し、自立支援と地域共生の実現を目的としています。
制度の中身を理解するには、単なるサービスの集合体ではなく、それぞれの機能がどう連携し、どのように支え合っているかを知ることが大切です。
ここからは、地域包括ケアシステムがどのような仕組みで成り立っているのかを、構成要素や支援の考え方も交えて整理していきます。
地域包括ケアシステムの5つの構成要素
高齢者が地域で安心して暮らすには、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つの要素がバランスよく整っていることが欠かせません。
地域包括ケアシステムでは、これらの要素を単体で考えるのではなく、「住まい」を基盤に他のサービスが連動する形で、生活の質を高めることを目指しています。
5つの要素の概要は、以下のとおりです。
| 住まい | ・自宅や高齢者向け住宅など ・尊厳やプライバシーが保たれ、本人の希望や経済状況に合った環境の確保が必要 |
| 医療 | ・かかりつけ医や地域の病院が連携 ・在宅医療から急性期医療まで切れ目のない対応が可能に |
| 介護 | ・訪問介護や通所介護、施設介護など ・利用者の状態に応じて柔軟に選択・組み合わせることで在宅生活を支援 |
| 予防 | ・地域交流の促進などにより、できるだけ介護が必要ない状態を維持 |
| 生活支援 | ・見守りや配食、買い物支援、安否確認など ・住民やボランティア、NPOが支え手となり、地域ぐるみで暮らしを支援 |
5つの構成要素は、それぞれ単独で機能するのではなく、互いに補完し合うことではじめて機能します。
例えば、介護サービスの利用中に医療的な支援が必要となれば、すぐにかかりつけ医と連携する体制を整えるなど、横の連携が必要です。
仕組みが整うことで、高齢者は住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができます。
地域包括ケアを支える4つの助
地域包括ケアシステムを安定して機能させるには、サービスだけではなく、地域全体の「助け合い」の意識と仕組みが欠かせません。
その支えとなるのが、「自助/互助/共助/公助」の4つの助です。
以下に、4つの助の概要を整理してみましょう。
| 分類 | 内容 | 具体例 |
| 自助 | 自分のことは自分でする意識 | ・健康管理 ・生活リズムの維持 ・市販サービスの活用 |
| 互助 | 家族や地域の人との助け合い | ・ご近所同士の見守り ・ボランティア活動 ・NPOの支援 |
| 共助 | 制度に基づいた相互扶助 | ・介護保険 ・医療保険などの社会保障制度 |
| 公助 | 国や自治体による支援 | ・福祉サービス ・生活保護 ・公的機関の相談支援 |
地域包括ケアシステムは一つの支援に依存するのではなく、4つの助け合いを組み合わせることで、多様なニーズに対応できるよう設計されています。
高齢者が「どこで、誰と、どう暮らすか」を自分で選べる社会をつくるために、支える力を社会全体で分かち合う仕組みが、地域包括ケアの理想と言えるでしょう。
地域包括支援センターの主な業務
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるには、身近に相談できる窓口が欠かせません。そこで重要となるのが、地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは、介護や医療、福祉に関する相談に幅広く対応し、個々の状況に応じた支援をコーディネートしてくれます。
地域包括支援センターの主な業務は、以下のとおりです。
| 総合相談支援 | 介護や健康、福祉に関する悩みへの対応 本人だけではなく、家族や近隣住民からの相談にも応じる |
| 権利擁護 | 高齢者虐待の早期発見と対応・成年後見制度の案内や支援 消費者被害への予防啓発 |
| 介護予防ケアマネジメント | 要支援者へのケアプラン作成支援 介護予防サービスの利用調整 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援 | 地域のケアマネジャーへの支援 医療/介護/福祉機関との連携促進 |
地域包括支援センターは、地域における「困りごとの最初の相談先」「地域づくりの推進役」としての役割を担っています。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
地域包括ケアシステムが求められる背景

少子高齢化が急速に進む日本では、介護を取り巻く課題が年々深刻化しています。施設中心の介護サービスだけでは限界が見えてきており、地域全体で高齢者を支える新たな仕組みの構築が急務とされています。
その背景の社会的要因は、以下のとおりです。
- 高齢化の進行による社会課題
- 家族介護の負担増加
- 施設介護だけでは対応が難しくなっている現状
それぞれの要因を確認していきましょう。
高齢化の進行による社会課題
地域包括ケアシステムが求められる背景には、高齢化の進行による社会課題があります。
高齢化の進行により、これまでの介護・医療体制では支えきれない地域が増えつつあります。
支援を必要とする高齢者が急増する一方で、担い手となる現役世代は減少中です。社会保障制度の維持や、地域によるケア体制の強化が課題になっています。
2070年には日本の総人口が9,000万人を下回り、高齢化率は39%に達すると推計されています。2025年には75歳以上の人口が18%に、2040年には65歳以上が全体の35%になると見込まれており、社会構造そのものの見直しが必要です。
人口推移からもわかるように、地域で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の重要性が、これまで以上に高まっています。
家族介護の負担増加
家族介護の負担増加は、地域包括ケアシステムが求められる背景の一つです。
なぜなら、介護を家族だけで担うことには限界があり、精神的・身体的・経済的な負担が重くなりやすいからです。
特に、以下のような現状が指摘されています。
- 核家族化が進み、複数世帯が同居する世帯が減少している
- 独居老人や高齢夫婦のみの世帯が増加している
- 仕事と介護の両立に悩む「ビジネスケアラー」が増えている
- 介護費用や在宅対応の準備に追われ、経済的な負担も大きくなっている
上記のような状況では、家族だけで介護を担い続けるのは困難でしかありません。そのため、地域包括ケアシステムの中で介護事業所やケアセンター、地域支援センターなどが連携し、家族を支える体制を整えることが求められています。
地域全体で家族介護を支えるしくみの構築が、今後ますます重要になるでしょう。
施設介護だけでは対応が難しくなっている現状
施設介護だけで高齢者ケアをまかなうのは、もはや限界に近づいています。介護施設の定員や人材に制約があり、すべての高齢者を受け入れることが難しいからです。
具体的な課題としては、以下のようなものがあります。
- 特別養護老人ホームの入所待ちが各地で常態化
- 介護職員の人材確保が困難
- 現場の負担が増している
- 認知症や要介護度の高い高齢者に対する柔軟な対応が求められている
上記のような課題から、地域で支える体制づくりが急務とされています。
地域包括ケアシステムを活用し、住まい・医療・介護・予防・生活支援を組み合わせた包括的な支援が、今後のスタンダードになるでしょう。
自治体や施設が地域包括ケアに取り組むためのポイント

地域包括ケアシステムを実効性のあるものにするためには、自治体や施設が主体的に取り組むことが欠かせません。
制度や枠組みが整っていても、現場での実践が伴わなければ、地域に根ざした支援体制にはつながりません。
ここでは、医療・介護・住民の連携を深めながら、現場で実践すべき具体的なポイントを整理します。
医療と介護の連携を強化する
地域包括ケアシステムを円滑に機能させるには、医療と介護の連携が必要です。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるには、日々の介護と医療的な支援の両方が密接に関わっているからです。
例えば、訪問診療を実施する医師と介護スタッフが連携して情報を共有し、体調変化の早期発見や、必要な処置への迅速な対応が可能になります。
在宅療養中の利用者に対し、急変時に連携先の医療機関と連動できる体制が整っていれば、家族の安心感にもつながるでしょう。
ICTを活用して業務の効率化を図る
ICTの活用は、介護現場の業務効率化に直結します。なぜなら、記録や連携、見守りといった業務の多くが手作業に依存しており、職員の負担が大きいからです。
例えば、以下のようなICTツールが介護現場で導入されています。
| 介護記録ソフト | 記録を自動で集計し、加算要件にも対応可能 |
| 見守りセンサー | バイタルの異常や転倒を検知し、リアルタイム通知が可能 |
| タブレット端末の共有 | 訪問スタッフが現場から直接入力し、情報共有を即時化 |
| クラウド型ケアプラン管理システム | 多職種間で同一のデータを閲覧・更新可能 |
| AIチャットボット | 家族からの問い合わせに自動応答し、事務負担を軽減 |
ICTを導入すれば業務の無駄を削減でき、スタッフが本来のケアに注力しやすくなります。
現場の声を反映したツールを取り入れ、日々の業務に活用していきましょう。

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための重要な仕組みです。今後、高齢化がさらに進む中で、持続可能な体制の確立が求められます。特に、ICTの活用による医療・介護の連携強化や、地域住民の主体的な関与が不可欠です。また、多職種協働の推進により、包括的な支援の実現が期待されます。
一方で、介護人材の不足や財政負担の増大といった課題も山積しています。特に、都市部では単身高齢者の増加、地方では医療・介護資源の不足が深刻です。こうした問題に対応するためには、ボランティアやNPO、企業など多様な主体の連携が不可欠です。今後は、地域ごとの特性に応じた柔軟なシステム構築が鍵となるでしょう。
持続可能な地域包括ケアの実現には、「支える側」と「支えられる側」の境界をなくし、共生社会を目指す意識の醸成が求められます。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
まとめ|地域包括ケアシステムの取り組み事例を参考に施設運営に取り入れよう
地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自立した暮らしを続けるために欠かせない仕組みです。
全国の自治体では、地域の特性や課題に合わせて、さまざまな創意工夫を重ねながら取り組みが進められています。
例えば、ICTの活用による情報共有や高齢者の居場所づくり、地域住民と協働した生活支援体制の構築など、多様な実践例が挙げられます。
実践例は、介護施設や在宅支援を担う事業者にとっても、自社の体制づくりに役立つでしょう。
特に、医療・介護・住まい・予防・生活支援の5つの要素が連携して機能するためには、職員一人ひとりがその接点を担えるよう意識を高め、地域の中での役割を果たすことが求められます。
今回紹介した事例を参考に、地域全体で支える介護のあり方を改めて見直してみてください。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。